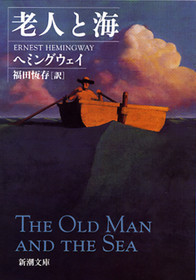副島種臣
2005年12月16日
なみログ at 22:10 | 芸術
2005年12月16日(金)佐賀新聞朝刊26頁より
副島種臣の没後百年を記念して佐賀市の県立美術館で開催される、
蒼海 副島種臣 全心の書展 (1月1日縲・月29日)
にちなんで、佐賀新聞の26面に副島種臣の人生と書についての連載があっていた。
今日の5本目の連載で終りだ。
副島種臣といえば、佐賀七賢人の一人だが、鍋島直正、大隈重信、江藤新平、佐野常民くらいまでは知っている人も多いと思うが、副島種臣となるとうろおぼえに覚えているひとも多いだろう。(島義勇や大木喬任よりは馴染み深いと思うが)
という私も副島種臣については、まったく知らない。
副島種臣は七賢人として明治政府に仕えたことで知っていたが、書家としての副島はほとんど知らなかった。恥ずかしいかぎりである。
仕事柄、書家としての副島種臣のことを少し知るようになり、改めてその人となりにも少し関心がでてきた。
書のこともまったく無知なので、どうしようもないが、今日の連載のなかに、副島の手習いの書生に向けていった助言がエピソードとして載っている。佐賀新聞から引用すると、
仮に「村」を書くなら、ほかのことは全部忘れ、初めの一の棒を全心を込めてできるだけ遅く、これより遅くは書けない位に遅く書く。今度は縦の棒を同じく気を込めて出来るだけ遅く書く。書というものは大体、間架結構(全体的なバランス)を頭にえがいて書いてはいけない。どんなに形が悪くても、少しぐらい歪んでもそれは後の問題だ
全心を込めて書く。気を込めて書く。
小学校や中学校の書道の時間にそういって教えた先生はいなかったなあ。全体のバランスを考えたり、できるだけ手本に真似て書くのに苦労していた。
どのような気持ちで書くかなんて、誰もいわなかった。
出来るだけ遅く書く。
とうのも新鮮だ。いかに早く済ませるか、いかに便利に済ませるかばかりのようなご時世で、いかに遅く書くか、というのはいいな。
できるだけ遅く読む。気を込めて読む。できるだけ遅く書く。気を込めて書く。
文学への取り組みにもあっていいと思う。
スロー読書。スロ読。遅読。・・・
副島種臣の没後百年を記念して佐賀市の県立美術館で開催される、
蒼海 副島種臣 全心の書展 (1月1日縲・月29日)
にちなんで、佐賀新聞の26面に副島種臣の人生と書についての連載があっていた。
今日の5本目の連載で終りだ。
副島種臣といえば、佐賀七賢人の一人だが、鍋島直正、大隈重信、江藤新平、佐野常民くらいまでは知っている人も多いと思うが、副島種臣となるとうろおぼえに覚えているひとも多いだろう。(島義勇や大木喬任よりは馴染み深いと思うが)
という私も副島種臣については、まったく知らない。
副島種臣は七賢人として明治政府に仕えたことで知っていたが、書家としての副島はほとんど知らなかった。恥ずかしいかぎりである。
仕事柄、書家としての副島種臣のことを少し知るようになり、改めてその人となりにも少し関心がでてきた。
書のこともまったく無知なので、どうしようもないが、今日の連載のなかに、副島の手習いの書生に向けていった助言がエピソードとして載っている。佐賀新聞から引用すると、
仮に「村」を書くなら、ほかのことは全部忘れ、初めの一の棒を全心を込めてできるだけ遅く、これより遅くは書けない位に遅く書く。今度は縦の棒を同じく気を込めて出来るだけ遅く書く。書というものは大体、間架結構(全体的なバランス)を頭にえがいて書いてはいけない。どんなに形が悪くても、少しぐらい歪んでもそれは後の問題だ
全心を込めて書く。気を込めて書く。
小学校や中学校の書道の時間にそういって教えた先生はいなかったなあ。全体のバランスを考えたり、できるだけ手本に真似て書くのに苦労していた。
どのような気持ちで書くかなんて、誰もいわなかった。
出来るだけ遅く書く。
とうのも新鮮だ。いかに早く済ませるか、いかに便利に済ませるかばかりのようなご時世で、いかに遅く書くか、というのはいいな。
できるだけ遅く読む。気を込めて読む。できるだけ遅く書く。気を込めて書く。
文学への取り組みにもあっていいと思う。
スロー読書。スロ読。遅読。・・・