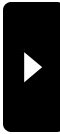スポンサーサイト
ベスト電器がヤマダ電機に。。
今日の日経新聞の一面には、ヤマダがベストを買収というニュースが。
ベスト電器といえば、福岡博多発の大型量販店で福岡、佐賀にはおなじみの量販店だった。日経によると1979年から96年までは全国No.1の売上を誇っていたというくらい勢いがあった。
家電量販店は、コジマがビッグの子会社になければ生き残れなくなったのにも驚いたが、、
ヨドバシやビッグカメラ、ヤマダは、ECだけでなく、OtoOのビジネスモデルの確立にも力を入れているので、ますます囲い込みが進むだろう。
家電量販店だけでなく、価格戦略の度合いが強い量販店は、EC化率を引き上げることと、OtoOへのIT戦略をどのように進めていくか、戦略が問われそうだ。
ベスト電器といえば、福岡博多発の大型量販店で福岡、佐賀にはおなじみの量販店だった。日経によると1979年から96年までは全国No.1の売上を誇っていたというくらい勢いがあった。
家電量販店は、コジマがビッグの子会社になければ生き残れなくなったのにも驚いたが、、
ヨドバシやビッグカメラ、ヤマダは、ECだけでなく、OtoOのビジネスモデルの確立にも力を入れているので、ますます囲い込みが進むだろう。
家電量販店だけでなく、価格戦略の度合いが強い量販店は、EC化率を引き上げることと、OtoOへのIT戦略をどのように進めていくか、戦略が問われそうだ。
産学官交流セミナー西京信用金庫
新宿の西京信用金庫で開催されているセミナーに来た。
早稲田大学社会連携室が佐賀偉人伝の大隈重信を紹介している。
有田焼の日本応援キャンドル ソーサーも紹介。
サッカーファミリーはうらやましい!
サッカーのファンは、ファミリーと呼ぶそうだ。
僕はいまでこそサガン鳥栖を応援しているが、ずっと野球が好きだった。少年野球もやっていたし、観るのも好きで、仕事でも、いまでは伝説?のホークスの応援ビデオ作ったりした。
話は、サッカーファミリーに戻るけど、
サッカーファミリーはうらやましい。
先日、某仕事関係の知人と、某飛び込み営業の若手営業マンを、新宿で引き合わせることになった。
二人を引き合わせようと思ったのは、どちらもサッカーに関係した趣味というか仕事というか、サッカーが好きな二人だったからだ。
新宿の某喫茶店。
「はじめまして●●といいます」と若手。
「はじめまして●●です」と僕の知人。
「え~っ!?まじっすか。まさか、まじっすか!」と若手。
「どうしたの?」と知人。&僕。
「ツイッターフォローしてるかもです! ●●さんですよね?」
「そうそう。え、フォローしてんの?」と知人。
「めっちゃしてますよ!(喜)」と若手。
「・・・(笑顔)」知人。
「フォローしてるか、検索してみよ。なんて検索したら出んの?」 と知人。
「●●●・・・で検索してもらえれば出ます」と恐縮したように若手。
(検索する知人)
・・・数秒後
「あ、ホンマや!(笑)」
いやあ、なんか凄い出会いを目の前で目撃してしまい、その出会いをセッティングし、そして、そこに居合わせている僕。
サッカーファミリーは、ええなあ。と
ちなみに僕は昔、隠れジャイアンツファンだった。(笑)
僕はいまでこそサガン鳥栖を応援しているが、ずっと野球が好きだった。少年野球もやっていたし、観るのも好きで、仕事でも、いまでは伝説?のホークスの応援ビデオ作ったりした。
話は、サッカーファミリーに戻るけど、
サッカーファミリーはうらやましい。
先日、某仕事関係の知人と、某飛び込み営業の若手営業マンを、新宿で引き合わせることになった。
二人を引き合わせようと思ったのは、どちらもサッカーに関係した趣味というか仕事というか、サッカーが好きな二人だったからだ。
新宿の某喫茶店。
「はじめまして●●といいます」と若手。
「はじめまして●●です」と僕の知人。
「え~っ!?まじっすか。まさか、まじっすか!」と若手。
「どうしたの?」と知人。&僕。
「ツイッターフォローしてるかもです! ●●さんですよね?」
「そうそう。え、フォローしてんの?」と知人。
「めっちゃしてますよ!(喜)」と若手。
「・・・(笑顔)」知人。
「フォローしてるか、検索してみよ。なんて検索したら出んの?」 と知人。
「●●●・・・で検索してもらえれば出ます」と恐縮したように若手。
(検索する知人)
・・・数秒後
「あ、ホンマや!(笑)」
いやあ、なんか凄い出会いを目の前で目撃してしまい、その出会いをセッティングし、そして、そこに居合わせている僕。
サッカーファミリーは、ええなあ。と
ちなみに僕は昔、隠れジャイアンツファンだった。(笑)
東北地方太平洋沖地震 関連情報リンク
東北地方太平洋沖地震についての災害情報
- 【全国情報】
- 【安否情報確認】
- 災害用 ブロードバンド伝言板(web171)
- 各携帯サービス:NTTドコモ / au / ソフトバンク
- 【被災地域の地域ブログリンク】
フェイスブック
県職員の在宅勤務
2008年6月26日(木)佐賀新聞朝刊20頁より
佐賀県職員が在宅勤務を試行するということで、3ヶ月間の一回目の施行期間が終わるとある。
記事によると、週4日まで在宅勤務を計画できるとあり、ただし実際に在宅勤務にあてられた日数は週1日だったとのこと。
在宅勤務を試行したのは、都道府県庁では佐賀が初めてということで、今後の取り組みも注目される。
個人的には在宅勤務でもいい会社は在宅でもいいのではないか、と思う。
ただ記事中にもあるが、疎外感や孤独感がある、というアンケート結果も納得する。
外回りの営業だって直行直帰が続くと、疎外感や孤独感を感じることがあるだろう。
私はけっこうというか、かなり大丈夫なほうなので、そういう気持ちはほとんど抱いたことがないが、
今日の記事だけでは、在宅勤務が個人にとって、社会にとってどうメリットがあるかというのは深くは書かれていなかったので、わからないが、会社や社会の立場だけでなく、家庭や子供の目線でみたときにどうなのかとか、年老いた両親を持つ家庭にとってどうなのか、という視点も必要だろう。
個人的には働き方はどうだっていいと思う。朝が遅かろうが、早かろうが、帰りが早かろうが、遅かろうが。
ただ、朝礼って案外馬鹿に出来ないもので、朝礼をちゃんとできている会社は伸びるんじゃないかな、と思ったりしている。
課題だ。
佐賀県職員が在宅勤務を試行するということで、3ヶ月間の一回目の施行期間が終わるとある。
記事によると、週4日まで在宅勤務を計画できるとあり、ただし実際に在宅勤務にあてられた日数は週1日だったとのこと。
在宅勤務を試行したのは、都道府県庁では佐賀が初めてということで、今後の取り組みも注目される。
個人的には在宅勤務でもいい会社は在宅でもいいのではないか、と思う。
ただ記事中にもあるが、疎外感や孤独感がある、というアンケート結果も納得する。
外回りの営業だって直行直帰が続くと、疎外感や孤独感を感じることがあるだろう。
私はけっこうというか、かなり大丈夫なほうなので、そういう気持ちはほとんど抱いたことがないが、
今日の記事だけでは、在宅勤務が個人にとって、社会にとってどうメリットがあるかというのは深くは書かれていなかったので、わからないが、会社や社会の立場だけでなく、家庭や子供の目線でみたときにどうなのかとか、年老いた両親を持つ家庭にとってどうなのか、という視点も必要だろう。
個人的には働き方はどうだっていいと思う。朝が遅かろうが、早かろうが、帰りが早かろうが、遅かろうが。
ただ、朝礼って案外馬鹿に出来ないもので、朝礼をちゃんとできている会社は伸びるんじゃないかな、と思ったりしている。
課題だ。
佐賀大学で講義
朝8時40分開始の1限目、佐賀大学で講義をしてきた。
特別な講義ではなくて、社会人の方の話を聞いてみよう、というもので、
Webビジネスのこと、Webビジネスの課題を考えるというもの。
準備していた内容が少しばかり難しかったかもしれない。。
一番伝えたかったことは、
<消費型社会生活>と<創造型社会生活>のこと。
インターネットをうまく活用することで、より創造型な社会生活を送る。
そのためにはどのような課題があり、どうやってそれを解決していけばいいのか、
を議論して考えてもらう、というのが昨日考えていた思惑だったのだが。。
今日聴講した学生に、なにかを伝えることができていればいいんだけれど。。
せんたく発足 横尾多久市長も
2008年3月4日(火)佐賀新聞1頁より
普段は政治ネタはあまり触れないことにしている。
しかしながら、政治をテレビで見たり新聞でみたりするのは大好きで、
家に帰るのも、報道ステーションに間に合うように帰っているのではないか、と一部の方から疑いを持たれていたりする。
<せんたく>という政策集団ができたという記事が載っている。
正式には、『地域・生活者起点で日本を選択する国民連合(せんたく)』だそうだ。長い・・・
坂本竜馬の乙女に宛てた手紙の文言にある<洗濯>と、<選択>をかけたもので、竜馬好きがうようよいそうな政治家の考えるネーミングだな、と思ったりする。
多久市の横尾市長も名を連ねていて、横尾市長のコメントも新聞に載っていた。
具体的になにがどうなるのかはわからないが、注目してみてみたい。
なんか、ネタ不足丸出しのコラムになってしまった。。
普段は政治ネタはあまり触れないことにしている。
しかしながら、政治をテレビで見たり新聞でみたりするのは大好きで、
家に帰るのも、報道ステーションに間に合うように帰っているのではないか、と一部の方から疑いを持たれていたりする。
<せんたく>という政策集団ができたという記事が載っている。
正式には、『地域・生活者起点で日本を選択する国民連合(せんたく)』だそうだ。長い・・・
坂本竜馬の乙女に宛てた手紙の文言にある<洗濯>と、<選択>をかけたもので、竜馬好きがうようよいそうな政治家の考えるネーミングだな、と思ったりする。
多久市の横尾市長も名を連ねていて、横尾市長のコメントも新聞に載っていた。
具体的になにがどうなるのかはわからないが、注目してみてみたい。
なんか、ネタ不足丸出しのコラムになってしまった。。
唐津くんちエピソード
2007年10月28日(日)佐賀新聞朝刊22頁より
唐津くんちが、11月2日の宵山から始まる。
■唐津観光協会サイト
佐賀新聞紙面では、今日から特集が組んであり、神事について書かれていた。
内容は佐賀新聞を読んでもらったほうがよいだろう。
さて、唐津というと、私も唐津市立外町小学校に一年生のときだけ通ったが、それからすっかり唐津のことは遠い記憶になってしまっている。
幼稚園は唐津幼稚園に年長のとき通った。いまもあるのかどうか知らないが、唐津城の近くにあったような記憶が。独楽を作る工場も近くにあって、独楽作りの見学があったと思う。ほかには浜が近いので、浜辺の散歩もあった。うみがめにも遭遇したような。(卵生みに来ていたのかな)
唐津幼稚園へは、和多田というところからバスで通っていた。バスといっても、幼稚園のバスではなく、乗り合いの昭和バスだ。定期券を持って、アパートから一人でバス停に出て、子供ばかりで、ときには独りでバスに乗っていっていた。親はバス停にさえついて来ていなかった。
いまから思えば、昔はそういうもんだったのだろう。送り迎えとかは必要なかったんだろう。私の親がほったらかし過ぎなのかも知れないけど。。
話は飛ぶが、二年生か三年生のときに、唐津のときの友達の家に多久から遊びに行って、半日を過ごしたことがある。
そのとき、友達の家に、さらに友達が訪ねてきて、唐津くんちの曳山を粘土で作った、工作の作品を持ってきた。(唐津の小学校では曳山の絵とか粘土作りとかが授業であった)
浦島太郎と亀の曳山だった。
おおきさは、両手の手のひらで抱えるくらい。
ラジコンカーくらいかな。
曳山の台車の車輪部分は、トイレットペーパーの芯を使ってあり、粘土の曳山に紐をつけて、引きずると動くという凝ったものだった。本当にしくみは良くできていた。
が、肝心の浦島太郎と亀の、亀の部分がひよこみたいな出来だったので、「ひよこ」「ひよこ」と、なじって馬鹿にしていたら、その友達が急に泣き出して、帰るといって帰り出した。
玄関の踊り場を、紐を引きずりながら帰るその友達の後姿がなんともかわいそうで、さらには追い討ちをかけるように、
ポロッと、台車のトイレットペーパーの芯が外れてしまった。。
たしか、それを拾いもせずに、帰っていった。
唐津くんちというと、いまでもこのエピソードを思い出す。
せっかく作った粘土作品に悪態をついてすいませんでした。。
唐津くんちが、11月2日の宵山から始まる。
■唐津観光協会サイト
佐賀新聞紙面では、今日から特集が組んであり、神事について書かれていた。
内容は佐賀新聞を読んでもらったほうがよいだろう。
さて、唐津というと、私も唐津市立外町小学校に一年生のときだけ通ったが、それからすっかり唐津のことは遠い記憶になってしまっている。
幼稚園は唐津幼稚園に年長のとき通った。いまもあるのかどうか知らないが、唐津城の近くにあったような記憶が。独楽を作る工場も近くにあって、独楽作りの見学があったと思う。ほかには浜が近いので、浜辺の散歩もあった。うみがめにも遭遇したような。(卵生みに来ていたのかな)
唐津幼稚園へは、和多田というところからバスで通っていた。バスといっても、幼稚園のバスではなく、乗り合いの昭和バスだ。定期券を持って、アパートから一人でバス停に出て、子供ばかりで、ときには独りでバスに乗っていっていた。親はバス停にさえついて来ていなかった。
いまから思えば、昔はそういうもんだったのだろう。送り迎えとかは必要なかったんだろう。私の親がほったらかし過ぎなのかも知れないけど。。
話は飛ぶが、二年生か三年生のときに、唐津のときの友達の家に多久から遊びに行って、半日を過ごしたことがある。
そのとき、友達の家に、さらに友達が訪ねてきて、唐津くんちの曳山を粘土で作った、工作の作品を持ってきた。(唐津の小学校では曳山の絵とか粘土作りとかが授業であった)
浦島太郎と亀の曳山だった。
おおきさは、両手の手のひらで抱えるくらい。
ラジコンカーくらいかな。
曳山の台車の車輪部分は、トイレットペーパーの芯を使ってあり、粘土の曳山に紐をつけて、引きずると動くという凝ったものだった。本当にしくみは良くできていた。
が、肝心の浦島太郎と亀の、亀の部分がひよこみたいな出来だったので、「ひよこ」「ひよこ」と、なじって馬鹿にしていたら、その友達が急に泣き出して、帰るといって帰り出した。
玄関の踊り場を、紐を引きずりながら帰るその友達の後姿がなんともかわいそうで、さらには追い討ちをかけるように、
ポロッと、台車のトイレットペーパーの芯が外れてしまった。。
たしか、それを拾いもせずに、帰っていった。
唐津くんちというと、いまでもこのエピソードを思い出す。
せっかく作った粘土作品に悪態をついてすいませんでした。。
図書館は問題解決の糸口を探す場所である(←長いな)
2007年10月18日(木)佐賀新聞朝刊20頁より
20面の記者日記に、下記のようなことが書いてある。
「多機能トイレを使おうと備え付けのボタンを押したけど、反応はなかった。何度も押した末に来た掃除担当の人から、勝手にボタンを押さないでよ、と言われてしまって」
障害者就職相談会に訪れた車椅子の男性が語ったものという。
その施設が、「UD適合証」が交付されている施設だったので、反応のないボタンを修理もせずに放っておいていることに管理のあり方が問われている。もちろん記者の感想のように、ハードの管理だけではなく、管理のあり方のソフト面もだ。
コラムの見出しが、「数字だけ」ではなく・・・ となっていることも考えさせられる。
分かり易く数字で達成目標を掲げるのはいいが、果たしてその数字を達成した先にあるものや、数字では計ることのできないソフト面の充実や、生活環境の向上などといった具体的な便益はおざなりにされてはいないだろうか。
「数字だけ」ではなく・・・ というので、思い浮かべるのが、図書館の利用率の件だ。
佐賀県は図書館先進県としてスローガンを掲げているが、県民一人当たりの貸し出し数が多いとか、利用者数が多いとかいうのは、図書館先進県として達成する最終目標ではないはずだ。
図書館先進県の先には、実用書でも文学でも、本を読むことで、人と人が幸せに暮らせるようになるとか、暮らし向きが豊かになるとか、文化芸術が活発化するとか、起業が増えるとか、健康に暮らせるとか、犯罪率が下がるとか、そういった変化がおきてくるのが期待するものだろう。
ふと思ったのだが、
<Webは問題解決の道具である>
という主題を掲げて、Webビジネスに取り組んでいるが、
<図書館は問題解決の糸口を探す場所である>
といえないか。
なみログは、『図書館応援宣言』をしてます!!
20面の記者日記に、下記のようなことが書いてある。
「多機能トイレを使おうと備え付けのボタンを押したけど、反応はなかった。何度も押した末に来た掃除担当の人から、勝手にボタンを押さないでよ、と言われてしまって」
障害者就職相談会に訪れた車椅子の男性が語ったものという。
その施設が、「UD適合証」が交付されている施設だったので、反応のないボタンを修理もせずに放っておいていることに管理のあり方が問われている。もちろん記者の感想のように、ハードの管理だけではなく、管理のあり方のソフト面もだ。
コラムの見出しが、「数字だけ」ではなく・・・ となっていることも考えさせられる。
分かり易く数字で達成目標を掲げるのはいいが、果たしてその数字を達成した先にあるものや、数字では計ることのできないソフト面の充実や、生活環境の向上などといった具体的な便益はおざなりにされてはいないだろうか。
「数字だけ」ではなく・・・ というので、思い浮かべるのが、図書館の利用率の件だ。
佐賀県は図書館先進県としてスローガンを掲げているが、県民一人当たりの貸し出し数が多いとか、利用者数が多いとかいうのは、図書館先進県として達成する最終目標ではないはずだ。
図書館先進県の先には、実用書でも文学でも、本を読むことで、人と人が幸せに暮らせるようになるとか、暮らし向きが豊かになるとか、文化芸術が活発化するとか、起業が増えるとか、健康に暮らせるとか、犯罪率が下がるとか、そういった変化がおきてくるのが期待するものだろう。
ふと思ったのだが、
<Webは問題解決の道具である>
という主題を掲げて、Webビジネスに取り組んでいるが、
<図書館は問題解決の糸口を探す場所である>
といえないか。
なみログは、『図書館応援宣言』をしてます!!
九州大学の薬草研究所が玄海町に
2007年9月8日(土)佐賀新聞朝刊1頁より
東松浦郡玄海町が、九州大学の薬用植物の栽培研究施設を誘致する。
という記事が載っている。
へえー。
新聞によると、どうやら国内で使用される薬草のうち、90%以上は海外からの輸入品ということで、国内での栽培研究には注目が集まっているとのこと、
これも知らなかった。漢方薬は、もともとが中国だろうから中国からの輸入品も多いとは推測できるが、それにしても原材料となる薬草が90%輸入植物とは。。
ヨモギとかアロエとかも輸入のようだ。
アロエは実家では、縁側の鉢に植わっていたので、皮膚が弱いのでたまに汁をつけたりしていたのだけれど、家庭でつける分は量はそれほどいらないが、数年前からアロエヨーグルトがコンビニででてくるようになって、アロエドリンクとかも。これは、かなりのアロエが消費されているんだろうな、とは思っていた。
ちょっとグーグルで調べてみると、アロエはタイが生産国としては多いようだ。
話は戻って、九大の薬草研究所のことだが、薬草を商品化するような、たとえば健康食品や、化粧品など、そういう企業が玄海町に出てくる可能性もあるということだろう。玄海町にとって産業発展につながるという期待があるのも当然だ。
東松浦郡玄海町が、九州大学の薬用植物の栽培研究施設を誘致する。
という記事が載っている。
へえー。
新聞によると、どうやら国内で使用される薬草のうち、90%以上は海外からの輸入品ということで、国内での栽培研究には注目が集まっているとのこと、
これも知らなかった。漢方薬は、もともとが中国だろうから中国からの輸入品も多いとは推測できるが、それにしても原材料となる薬草が90%輸入植物とは。。
ヨモギとかアロエとかも輸入のようだ。
アロエは実家では、縁側の鉢に植わっていたので、皮膚が弱いのでたまに汁をつけたりしていたのだけれど、家庭でつける分は量はそれほどいらないが、数年前からアロエヨーグルトがコンビニででてくるようになって、アロエドリンクとかも。これは、かなりのアロエが消費されているんだろうな、とは思っていた。
ちょっとグーグルで調べてみると、アロエはタイが生産国としては多いようだ。
話は戻って、九大の薬草研究所のことだが、薬草を商品化するような、たとえば健康食品や、化粧品など、そういう企業が玄海町に出てくる可能性もあるということだろう。玄海町にとって産業発展につながるという期待があるのも当然だ。
馬インフルエンザが佐賀競馬でも・・・
2007年8月31日(金)佐賀新聞朝刊26頁より
佐賀競馬場でも馬インフルエンザが。。
なんでも、新聞記事によると、計103頭(30日現在)。
おいおいおーい。
と、佐賀競馬のサイトを見ると、
明日、あさっては、開催とな。
とりあえず、競馬ファンにとってはよかったか。
ということで、競馬のことはこれくらいにして、
16面の「天神通信」というコラムに、
サッカーJリーグの1県1チーム時代について書かれた記事がある。
先日、サガン鳥栖を見に行ったからというわけではないが、プロリーグのある地域はいいな、と思った。
サッカーでも野球でも(昨日投稿の相撲でも)、生でスポーツが見れる環境というのはいい。
佐賀北高が甲子園で優勝したが、県予選はみどりの森野球場で開催されていたわけで、500円で試合を見れた。
(毎年大体決勝か、準決勝は見にいっていたんだけど、今年は見に行かなかった。。)
話が脱線したが、コラムによると、各県1つずつJリーグチームができると、その経済波及効果も大いに期待できるとある。
(九州ダービーとなると、千人単位でサポーターが移動するという想定)
なるほど。
という枕ではないが、あさって、9月2日(日)は、18時から鳥栖スタジアムで、九州ダービーのアビスパ福岡戦だ!!
佐賀競馬場でも馬インフルエンザが。。
なんでも、新聞記事によると、計103頭(30日現在)。
おいおいおーい。
と、佐賀競馬のサイトを見ると、
明日、あさっては、開催とな。
とりあえず、競馬ファンにとってはよかったか。
ということで、競馬のことはこれくらいにして、
16面の「天神通信」というコラムに、
サッカーJリーグの1県1チーム時代について書かれた記事がある。
先日、サガン鳥栖を見に行ったからというわけではないが、プロリーグのある地域はいいな、と思った。
サッカーでも野球でも(昨日投稿の相撲でも)、生でスポーツが見れる環境というのはいい。
佐賀北高が甲子園で優勝したが、県予選はみどりの森野球場で開催されていたわけで、500円で試合を見れた。
(毎年大体決勝か、準決勝は見にいっていたんだけど、今年は見に行かなかった。。)
話が脱線したが、コラムによると、各県1つずつJリーグチームができると、その経済波及効果も大いに期待できるとある。
(九州ダービーとなると、千人単位でサポーターが移動するという想定)
なるほど。
という枕ではないが、あさって、9月2日(日)は、18時から鳥栖スタジアムで、九州ダービーのアビスパ福岡戦だ!!
男性の育児休業取得者ってどれくらいいるの?
2006年7月11日(火)佐賀新聞朝刊1頁より
佐賀県が、子育て宣言企業をPRする。
そんな記事が載っていた。
記事によると、子育てと仕事の両立支援の一環で、「子育て宣言企業・事業所」に手を上げてもらい、県のホームページで紹介しようというもの。
基準としては、男性の育児休業取得者がいるということだ。
少子高齢社会を背景としたさまざまな施策の一環で、女性が子供を産みやすくするために、男性の育児休業を推進するという話だろう。
果たしてどれくらいの企業があるのか。実際に県内で育児休業を取得した男性の割合が、03年度で0.5%、04年度で0.4%だったと記事にある。
ちなみに、女性は03年度で88.0%と、高いか低いかは判らないが、高いようだ。
(この場合、12%の女性は、育児休業をとってもいいくらいなのに取らずに働いていたということなのか??)
男性が育児休業をとる企業がどれくらい出てくるかどうかまったく検討もつかないが、そういう制度があるだけではダメで、実際に2日以上の取得者がいないと登録されないということなので、県内にどのくらいの企業数があるのか結果を見てみたい。
佐賀県が、子育て宣言企業をPRする。
そんな記事が載っていた。
記事によると、子育てと仕事の両立支援の一環で、「子育て宣言企業・事業所」に手を上げてもらい、県のホームページで紹介しようというもの。
基準としては、男性の育児休業取得者がいるということだ。
少子高齢社会を背景としたさまざまな施策の一環で、女性が子供を産みやすくするために、男性の育児休業を推進するという話だろう。
果たしてどれくらいの企業があるのか。実際に県内で育児休業を取得した男性の割合が、03年度で0.5%、04年度で0.4%だったと記事にある。
ちなみに、女性は03年度で88.0%と、高いか低いかは判らないが、高いようだ。
(この場合、12%の女性は、育児休業をとってもいいくらいなのに取らずに働いていたということなのか??)
男性が育児休業をとる企業がどれくらい出てくるかどうかまったく検討もつかないが、そういう制度があるだけではダメで、実際に2日以上の取得者がいないと登録されないということなので、県内にどのくらいの企業数があるのか結果を見てみたい。
子育て応援の店
2006年6月28日(火)佐賀新聞朝刊28頁より
少子化問題で、いろいろと国の施策、地域の施策が行なわれている。
そんな中、今日の佐賀新聞に、子育て家庭を応援するための、「子育て応援の店」事業についての記事が載っている。
九州北部5県が連携を図り、「子育て応援の店」を募集する。
子育て家庭の生活者が、子育て応援の店を利用すると、割引サービスを得られるというもので、まずは生活者特典が受けられますよーというしくみ。
子育て応援の店側のメリットがよく見えないが、子育て応援の店ということで、利用者が増えるのを狙うというものだろう。
それから、同じ28面に、新田舎主義の提起として、長崎県大学院助教授の中村氏の文章が載っている。
文章の中で興味深いのは、
これからは農村が戦略を持てば豊かに暮せる時代。
という箇所で、野菜直売所でも一億円、二億円を売り上げるところもある、とあり、それが県内に二、三十箇所もあれば大きな産業になる、とある。
まあ、文学的な視点で問い掛けるならば、一億、二億売る野菜直売所の生活が、果たしてただそれだけで豊かなのかどうか、というところには疑問が残るが、どう豊かになりたいのかのイメージができていさえすれば、一億、二億売るような野菜直売所であれば、十分豊かに暮せるだろう。
企業誘致だけではなく、そのような地場の産業を開発していくことが、景気の波にも左右されない、企業誘致だけに依存せずに、別の戦略を持つべきだ、という考えは賛同したい。
豊かに暮らすというときの「豊かさ」のビジョンは何なのか。金なのか、自然なのか、コミュニティーなのか。もちろんそういったいくつもの要素かもしれない。
長くなりました・・・
少子化問題で、いろいろと国の施策、地域の施策が行なわれている。
そんな中、今日の佐賀新聞に、子育て家庭を応援するための、「子育て応援の店」事業についての記事が載っている。
九州北部5県が連携を図り、「子育て応援の店」を募集する。
子育て家庭の生活者が、子育て応援の店を利用すると、割引サービスを得られるというもので、まずは生活者特典が受けられますよーというしくみ。
子育て応援の店側のメリットがよく見えないが、子育て応援の店ということで、利用者が増えるのを狙うというものだろう。
それから、同じ28面に、新田舎主義の提起として、長崎県大学院助教授の中村氏の文章が載っている。
文章の中で興味深いのは、
これからは農村が戦略を持てば豊かに暮せる時代。
という箇所で、野菜直売所でも一億円、二億円を売り上げるところもある、とあり、それが県内に二、三十箇所もあれば大きな産業になる、とある。
まあ、文学的な視点で問い掛けるならば、一億、二億売る野菜直売所の生活が、果たしてただそれだけで豊かなのかどうか、というところには疑問が残るが、どう豊かになりたいのかのイメージができていさえすれば、一億、二億売るような野菜直売所であれば、十分豊かに暮せるだろう。
企業誘致だけではなく、そのような地場の産業を開発していくことが、景気の波にも左右されない、企業誘致だけに依存せずに、別の戦略を持つべきだ、という考えは賛同したい。
豊かに暮らすというときの「豊かさ」のビジョンは何なのか。金なのか、自然なのか、コミュニティーなのか。もちろんそういったいくつもの要素かもしれない。
長くなりました・・・
パートナーデー(4月14日)はオレンジデー??
2006年3月1日(水)佐賀新聞朝刊17頁より
今日から3月。ブログの更新もずいぶんとまばらになってしまっているが、
さがファンの出店ショップ、肉の味好のブログが2月は1日も欠かすことなく更新されたのを知ると、わがブログは、ほぼ毎日などとうたっておりながら、なんというテイタラクな。と思ってしまう。。
さて、2月14日がバレンタインデー、3月14日がホワイトデー、それでは4月14日は?
パートナーデー
なんだそりゃ?初めて聞いた、という方。もぐりですぞよ。
パートナーデーは、佐賀市が提唱している記念日で、男女支えあうことや、パートナーを互いに大切に思うという意味をこめて、この日を作った。
そんでもって、佐賀市では、パートナーデーに、大切な人に贈る、「一言メッセージ」を募っている。
最優秀賞には、大人の部が賞金2万円! 子供の部(中学生以下)が図書カード5千円分を贈る。
応募方法は、はがきに、三十字以内で、一言メッセージを書いて、佐賀市役所男女共同参画室まで送る。
住所まで書くと、〒840-8501 佐賀市栄町1の1 市男女共同参画室まで
(※応募者資格があって、市内在住か、市内勤務者に限るとあるので、県外の方はごめんなさい)
パートナーデーは、佐賀市が提唱したものだが、その後の広がりはどうかと、グーグルで検索してみたら、どうやら、パートナーデーは、愛媛県から始まったオレンジデーというものとドッキングで浸透が始まりつつあるようで、ぼちぼちオレンジデーという商戦があっているようだ。。
ちょっとちょっと、オレンジといえば、愛媛には負けるかもしれないが、佐賀もみかんの一大産地じゃないか!
パートナーデーとオレンジデー。なにかうまくリンクしあって、広がりがでてくれば面白い。
■オレンジデー
パートナーデーも、ウィキペディアに書き込みしないとならないなあ。。といっても、書き込んだことないんだよなあ。。
今日から3月。ブログの更新もずいぶんとまばらになってしまっているが、
さがファンの出店ショップ、肉の味好のブログが2月は1日も欠かすことなく更新されたのを知ると、わがブログは、ほぼ毎日などとうたっておりながら、なんというテイタラクな。と思ってしまう。。
さて、2月14日がバレンタインデー、3月14日がホワイトデー、それでは4月14日は?
パートナーデー
なんだそりゃ?初めて聞いた、という方。もぐりですぞよ。
パートナーデーは、佐賀市が提唱している記念日で、男女支えあうことや、パートナーを互いに大切に思うという意味をこめて、この日を作った。
そんでもって、佐賀市では、パートナーデーに、大切な人に贈る、「一言メッセージ」を募っている。
最優秀賞には、大人の部が賞金2万円! 子供の部(中学生以下)が図書カード5千円分を贈る。
応募方法は、はがきに、三十字以内で、一言メッセージを書いて、佐賀市役所男女共同参画室まで送る。
住所まで書くと、〒840-8501 佐賀市栄町1の1 市男女共同参画室まで
(※応募者資格があって、市内在住か、市内勤務者に限るとあるので、県外の方はごめんなさい)
パートナーデーは、佐賀市が提唱したものだが、その後の広がりはどうかと、グーグルで検索してみたら、どうやら、パートナーデーは、愛媛県から始まったオレンジデーというものとドッキングで浸透が始まりつつあるようで、ぼちぼちオレンジデーという商戦があっているようだ。。
ちょっとちょっと、オレンジといえば、愛媛には負けるかもしれないが、佐賀もみかんの一大産地じゃないか!
パートナーデーとオレンジデー。なにかうまくリンクしあって、広がりがでてくれば面白い。
■オレンジデー
パートナーデーも、ウィキペディアに書き込みしないとならないなあ。。といっても、書き込んだことないんだよなあ。。
呼子に場外舟券場計画だってさ
2006年2月24日(金)佐賀新聞朝刊26頁より
唐津競艇といえば、競艇場の中でも、海ではない競艇場として珍しく、いや珍しくないのかもしれないが、建物もきれいで、いや、いまもきれいかどうか知らないが(10年以上行った事がないので)、ともかく唐津競艇は、きれいな競艇場というイメージがある。
※福大のときに、福岡競艇に行った事があるが、いわゆる老朽化した競艇場という雰囲気ありありだったのを覚えている。(もちろん福岡競艇もその後きれいになっているだろうが)
そんな唐津競艇を運営している唐津市が、場外舟券場を呼子に開設する計画があるという。
ほほう。
舟券場のイメージは、三日月町(小城市)にあるような、レース中継をする大型施設ではなく、レース中継をしない、舟券だけが買える施設で、宝くじ売り場みたいなものだという。
すでに唐津市の駅ちかくにあるアルピノで設置されているとあり、1開催の平均売上が200万円くらいあるとのこと。(採算ライン40万円だと)
ほほう。
個人的には競馬は嫌いではない。嫌いではないですよ。パチンコは嫌いですが。あ、競馬の話ではないか。
しかし競艇も不景気なのか、レジャーの多様化なのか、人気が低迷しておるようで。唐津市もなんとかしないとならないということでしょう。
記事には、治安悪化のために、地元保護者らの反対の声があると書いてある。
治安悪化を決めつけるのもどうかと思うのだが、その意見はわかる。
唐津競艇といえば、競艇場の中でも、海ではない競艇場として珍しく、いや珍しくないのかもしれないが、建物もきれいで、いや、いまもきれいかどうか知らないが(10年以上行った事がないので)、ともかく唐津競艇は、きれいな競艇場というイメージがある。
※福大のときに、福岡競艇に行った事があるが、いわゆる老朽化した競艇場という雰囲気ありありだったのを覚えている。(もちろん福岡競艇もその後きれいになっているだろうが)
そんな唐津競艇を運営している唐津市が、場外舟券場を呼子に開設する計画があるという。
ほほう。
舟券場のイメージは、三日月町(小城市)にあるような、レース中継をする大型施設ではなく、レース中継をしない、舟券だけが買える施設で、宝くじ売り場みたいなものだという。
すでに唐津市の駅ちかくにあるアルピノで設置されているとあり、1開催の平均売上が200万円くらいあるとのこと。(採算ライン40万円だと)
ほほう。
個人的には競馬は嫌いではない。嫌いではないですよ。パチンコは嫌いですが。あ、競馬の話ではないか。
しかし競艇も不景気なのか、レジャーの多様化なのか、人気が低迷しておるようで。唐津市もなんとかしないとならないということでしょう。
記事には、治安悪化のために、地元保護者らの反対の声があると書いてある。
治安悪化を決めつけるのもどうかと思うのだが、その意見はわかる。
動物夜間病院
2006年1月20日(金)佐賀新聞朝刊13頁より
犬が大の苦手な私だが、最近のペットに関する情報には目を瞠る。
(犬にはよく吠えられるたちなのだ・・正直いって怖い)
20日の佐賀新聞の福岡スポットの面に、動物病院の夜間病院が、想定外の活況とある。

http://www.pet99.net/
ドメインがウケる!
記事によると九州初の動物夜間病院として、2004年にオープンした、「福岡夜間救急動物病院」が好評のようだ。(福岡市博多区月隈)
わざわざ高速道路を飛ばして、佐賀や唐津、北九州からもペットをつれた飼い主が来るという。
なんでも同病院は、福岡県獣医師会の有志57人が出資して設立した組織が運営しているとのことで、獣医師会で要望の多かったアンケートに基づいて設立にいたったようだ。
先日東京へ出張したときに聞いたのは、ペットのトリマー店が、どこも予約でいっぱいで、まだまだトリマー店は足りていないという話だ。
へえ・・と思ったのだが、福岡でもそんな事情なんだろうか?
佐賀市内とかが案外、店舗が少なくて、予約で一杯かもしれない。
それから、日経流通新聞にいつだった、ペット用のトレーニングジムみたいなものが写真付の記事で紹介されていた。運動不足の犬だとかが、プールで泳いだりするものだ。
あと、ペット専用のレストランとかも載っていたような。
自分がペットが苦手だというだけで、その辺の事情にはまるっきり疎いので、ペット事情については、だれかにちょっと調べてもらいたいものだ。
犬が大の苦手な私だが、最近のペットに関する情報には目を瞠る。
(犬にはよく吠えられるたちなのだ・・正直いって怖い)
20日の佐賀新聞の福岡スポットの面に、動物病院の夜間病院が、想定外の活況とある。

http://www.pet99.net/
ドメインがウケる!
記事によると九州初の動物夜間病院として、2004年にオープンした、「福岡夜間救急動物病院」が好評のようだ。(福岡市博多区月隈)
わざわざ高速道路を飛ばして、佐賀や唐津、北九州からもペットをつれた飼い主が来るという。
なんでも同病院は、福岡県獣医師会の有志57人が出資して設立した組織が運営しているとのことで、獣医師会で要望の多かったアンケートに基づいて設立にいたったようだ。
先日東京へ出張したときに聞いたのは、ペットのトリマー店が、どこも予約でいっぱいで、まだまだトリマー店は足りていないという話だ。
へえ・・と思ったのだが、福岡でもそんな事情なんだろうか?
佐賀市内とかが案外、店舗が少なくて、予約で一杯かもしれない。
それから、日経流通新聞にいつだった、ペット用のトレーニングジムみたいなものが写真付の記事で紹介されていた。運動不足の犬だとかが、プールで泳いだりするものだ。
あと、ペット専用のレストランとかも載っていたような。
自分がペットが苦手だというだけで、その辺の事情にはまるっきり疎いので、ペット事情については、だれかにちょっと調べてもらいたいものだ。
阪神大震災と網の目の考え
2006年1月17日(火)佐賀新聞朝刊23頁より
阪神大震災から丸11年。
被災者200人のアンケートによると、85%の人が「風化を感じる」とある。(共同通信社調べ)
そういう私も風化を感じるひとり。。
なみログでも何回か書いたが、阪神大震災が起きた2月中旬。神戸市鷹取中学校避難所に着いた。校庭にはいくつもの運動会でみるテントが並び、車もびっしりと停まっていた。運動会でみるテントは、いくつかのテントは青いビニールシートでぐるりと横を巻かれ、中には救援物資がどっさりと詰まっていた。
鷹取中学校避難所で一番忘れてはならないと思ったことば。
「ボランティアは網の目からこぼれ落ちる人たちを助けてあげること。それがボランティアに求められる」
本当のところの意味はいまもって当っているかどうかわからないが、「網の目」とは行政だったり、規則だたり、社会の仕組みだったり、経済だったりするのだろう。
そして、今思うのは、「網の目」はボランティアそれ自身であることもあるということ。
ボランティアが行なう活動自体がいつのまにか網の目になったとき、そこからこぼれ落ちた方に目配りをすることもボランティアの役割。
網の目になる側を否定しているのではない、だれでもいいので、だれか一人以上の人が、いつもいまどこが網の目になりつつあるのか、どこが網の目なのかを注意深く意識しておくことが大切だということ。
最近、そういうことを考えたりする。
阪神大震災から丸11年。
被災者200人のアンケートによると、85%の人が「風化を感じる」とある。(共同通信社調べ)
そういう私も風化を感じるひとり。。
なみログでも何回か書いたが、阪神大震災が起きた2月中旬。神戸市鷹取中学校避難所に着いた。校庭にはいくつもの運動会でみるテントが並び、車もびっしりと停まっていた。運動会でみるテントは、いくつかのテントは青いビニールシートでぐるりと横を巻かれ、中には救援物資がどっさりと詰まっていた。
鷹取中学校避難所で一番忘れてはならないと思ったことば。
「ボランティアは網の目からこぼれ落ちる人たちを助けてあげること。それがボランティアに求められる」
本当のところの意味はいまもって当っているかどうかわからないが、「網の目」とは行政だったり、規則だたり、社会の仕組みだったり、経済だったりするのだろう。
そして、今思うのは、「網の目」はボランティアそれ自身であることもあるということ。
ボランティアが行なう活動自体がいつのまにか網の目になったとき、そこからこぼれ落ちた方に目配りをすることもボランティアの役割。
網の目になる側を否定しているのではない、だれでもいいので、だれか一人以上の人が、いつもいまどこが網の目になりつつあるのか、どこが網の目なのかを注意深く意識しておくことが大切だということ。
最近、そういうことを考えたりする。
ニート問題で嬉野高で出張授業
2005年10月21日(日)佐賀新聞朝刊21頁より ←誰かに真似されている
フリーターやニートの問題は、年々問題が大きくなってきている。
フリーターというのが流行り出した頃は、バブル期であるということを聞いたことがあるが、フリーターという言葉から抱く印象には、自由という印象があって、その頃は今のように切実な問題といった印象はまったく無かったような気がする。
フリーターという言葉がもっていた「自由」という印象。その「自由」という印象の言葉の裏に、もう一つ重要なキーワードがセットになっていたと私は思っている。
それは、「若さ」ということ。
「若さ」は、当時のフリーターを考えるときには、あたりまえのように定義の中に内包されていたから、あえて、「若い」ということに注目することはなかっただろう。
もう若くない者がフリーターであったり、ニートであるというのが問題といえば問題ということなのではないか。
もちろん若い人がフリーターやニートであるというのが社会問題としてあるようだが、20歳後半までに自分の進む道を決めることができればいいと思ったりするが・・甘いか。
私も25歳で初めていまの会社に就職した部類なので。。
アサヒコムを見ていたら、脱ニートにブログ活用という記事があった。
なんでも、ブログに自分の日記をつけていったり、アフェリエイトやオークションに参加していたら、他者とのつながりができて、外に出るようになり、就職の機会に恵まれた。ということらしい。
昔から、何かに必ずなりたい、という人は直接的に行動を起していたと思うが、あまりにもマニュアル主義が横行して、横紙破りな行動に出る人が少なくなってきているような気がする。
自分を売り込もうと思えば、直接会社を訪問したり、手書きの手紙を送ることだったり、いろいろ作戦を考えるのが当たり前ではないだろうか。大体多くの人はそうやっていると思うのだが・・
フリーターの人やニートの人(こういう言い方も変だが)で、ブログやアフェリエイトや、オークションや、ネットショップやってみようかな、と思っている人は、どんどんやった方がいい。相談してくれたら、手伝いまっせー。
というか、なみログの左メニューにあるように人材も募集しているし・・
フリーターやニートの問題は、年々問題が大きくなってきている。
フリーターというのが流行り出した頃は、バブル期であるということを聞いたことがあるが、フリーターという言葉から抱く印象には、自由という印象があって、その頃は今のように切実な問題といった印象はまったく無かったような気がする。
フリーターという言葉がもっていた「自由」という印象。その「自由」という印象の言葉の裏に、もう一つ重要なキーワードがセットになっていたと私は思っている。
それは、「若さ」ということ。
「若さ」は、当時のフリーターを考えるときには、あたりまえのように定義の中に内包されていたから、あえて、「若い」ということに注目することはなかっただろう。
もう若くない者がフリーターであったり、ニートであるというのが問題といえば問題ということなのではないか。
もちろん若い人がフリーターやニートであるというのが社会問題としてあるようだが、20歳後半までに自分の進む道を決めることができればいいと思ったりするが・・甘いか。
私も25歳で初めていまの会社に就職した部類なので。。
アサヒコムを見ていたら、脱ニートにブログ活用という記事があった。
なんでも、ブログに自分の日記をつけていったり、アフェリエイトやオークションに参加していたら、他者とのつながりができて、外に出るようになり、就職の機会に恵まれた。ということらしい。
昔から、何かに必ずなりたい、という人は直接的に行動を起していたと思うが、あまりにもマニュアル主義が横行して、横紙破りな行動に出る人が少なくなってきているような気がする。
自分を売り込もうと思えば、直接会社を訪問したり、手書きの手紙を送ることだったり、いろいろ作戦を考えるのが当たり前ではないだろうか。大体多くの人はそうやっていると思うのだが・・
フリーターの人やニートの人(こういう言い方も変だが)で、ブログやアフェリエイトや、オークションや、ネットショップやってみようかな、と思っている人は、どんどんやった方がいい。相談してくれたら、手伝いまっせー。
というか、なみログの左メニューにあるように人材も募集しているし・・
ネット時代の新聞
2005年10月12日(水)佐賀新聞朝刊19頁より
ネット時代の新聞
というテーマで、ひろばという読者投稿欄の特集が組まれている。
新聞が紙できたあの形の新聞のことであるという意識は、読者の投稿を読む限りでは、すでになさそうだ。
アサヒコムは、朝日新聞の紙面が仮になかったとしても、新聞であるという認識は大方の見方とみていいだろう。
ということで、オンラインでの新聞も含めて、ネット時代の新聞、と考えると、何だろうか?と考える。
取材力は、既存の新聞はさすがに強い。一般市民もあることに専門的に精通したひとはいるが、組織された取材力、個人としての取材力という点では新聞の強みはあるだろう。
今日の佐賀新聞などといって、なみログを書いているが、私が自ら経験(聞くことも含めて)したことをブログで書こうとするなら、とてもじゃないが続きそうにない。
ということで強い取材力をバックにした記事には期待したい。
それに、地域の情報はやはり地域に密着した取材網がないと吸い上げることはできないだろう。
大手の新聞が取材しない、地域にとって大事なことを知らせるという点では、地域の新聞に期待するところは大きい。
あー、またもやつまらんコメントになってしまった。。
(十年前までは本気で新聞記者志望だったので、新聞に対して思っていることをひとつだけ書くと、、ジャーナリズムであってほしいと思う。
ジャーナリズムとは何か? 辞書ででてくるジャーナリズムの意味以外に、私が考えるジャーナリズムとはこういうことではないか、という勝手な定義がある。 が、それは書かない。)
ネット時代の新聞
というテーマで、ひろばという読者投稿欄の特集が組まれている。
新聞が紙できたあの形の新聞のことであるという意識は、読者の投稿を読む限りでは、すでになさそうだ。
アサヒコムは、朝日新聞の紙面が仮になかったとしても、新聞であるという認識は大方の見方とみていいだろう。
ということで、オンラインでの新聞も含めて、ネット時代の新聞、と考えると、何だろうか?と考える。
取材力は、既存の新聞はさすがに強い。一般市民もあることに専門的に精通したひとはいるが、組織された取材力、個人としての取材力という点では新聞の強みはあるだろう。
今日の佐賀新聞などといって、なみログを書いているが、私が自ら経験(聞くことも含めて)したことをブログで書こうとするなら、とてもじゃないが続きそうにない。
ということで強い取材力をバックにした記事には期待したい。
それに、地域の情報はやはり地域に密着した取材網がないと吸い上げることはできないだろう。
大手の新聞が取材しない、地域にとって大事なことを知らせるという点では、地域の新聞に期待するところは大きい。
あー、またもやつまらんコメントになってしまった。。
(十年前までは本気で新聞記者志望だったので、新聞に対して思っていることをひとつだけ書くと、、ジャーナリズムであってほしいと思う。
ジャーナリズムとは何か? 辞書ででてくるジャーナリズムの意味以外に、私が考えるジャーナリズムとはこういうことではないか、という勝手な定義がある。 が、それは書かない。)