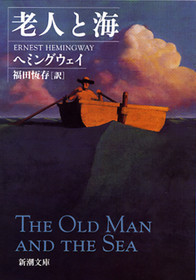田舎の文化は保障されているかについて
2005年11月30日
なみログ at 20:16 | 芸術
2005年11月30日(水)佐賀新聞朝刊15頁より
演劇・イベントの文化時評(劇団「空のフラクタル」代表 栗原氏)に、興味深い論考がしてある。
著名な演劇の演出家が、「日本における田舎文化への保障は憲法違反である」といったことを受けたもので、それに対し栗原氏は、都会の文化芸術に触れる機会と、田舎ではその機会が少ないということを根底に議論するのではなく、田舎に根ざした文化や芸術の発信という点では、けっして都会に劣らないのではないかと論じている。
都会とか田舎とかいうのもやぼったいような感じがする。
都会にはないものが田舎にあり、田舎にないものが都会にある。それでいいのではないかとぶっきらぼうに考える。
例えば、私の好きな小説家は、昭和岸壁派を自ら名乗り、辺境という雑誌を創り、西九州である長崎や佐賀を舞台に数々の小説を世に出した。
彼が小説のパン種として扱ったものの多くは地方の土俗的な民衆の生活であり、文化だった。
そういう小説群を読むと、田舎ゆえに存在する文化や芸術が確固としてあり、そこに住む私たちも含めた人間の生活が、都会だとか田舎だとかの議論に関係なく、豊かに存在することを知ることができる。
栗原氏の論考と同じ意味だが、田舎の文化というときに消費する文化があるかないかを論議してもはじまらない、危機意識をもつとすれば、消費する文化の量ではなく、創造する文化の機会があるかどうかだ。
と、ここまで書いたところで、文化時評の上段の美術(野中氏)を読むと、青木龍三氏の文化勲章授章と酒井田柿右衛門氏の旭日中綬章授章の吉報に触れ、亡くなった陶磁器デザイナーの森正洋氏を偲ぶ話が書かれていて、クリエイターとして生きる態度について、美の本質を見極めることについて書かれている。
演劇・イベントの文化時評(劇団「空のフラクタル」代表 栗原氏)に、興味深い論考がしてある。
著名な演劇の演出家が、「日本における田舎文化への保障は憲法違反である」といったことを受けたもので、それに対し栗原氏は、都会の文化芸術に触れる機会と、田舎ではその機会が少ないということを根底に議論するのではなく、田舎に根ざした文化や芸術の発信という点では、けっして都会に劣らないのではないかと論じている。
都会とか田舎とかいうのもやぼったいような感じがする。
都会にはないものが田舎にあり、田舎にないものが都会にある。それでいいのではないかとぶっきらぼうに考える。
例えば、私の好きな小説家は、昭和岸壁派を自ら名乗り、辺境という雑誌を創り、西九州である長崎や佐賀を舞台に数々の小説を世に出した。
彼が小説のパン種として扱ったものの多くは地方の土俗的な民衆の生活であり、文化だった。
そういう小説群を読むと、田舎ゆえに存在する文化や芸術が確固としてあり、そこに住む私たちも含めた人間の生活が、都会だとか田舎だとかの議論に関係なく、豊かに存在することを知ることができる。
栗原氏の論考と同じ意味だが、田舎の文化というときに消費する文化があるかないかを論議してもはじまらない、危機意識をもつとすれば、消費する文化の量ではなく、創造する文化の機会があるかどうかだ。
と、ここまで書いたところで、文化時評の上段の美術(野中氏)を読むと、青木龍三氏の文化勲章授章と酒井田柿右衛門氏の旭日中綬章授章の吉報に触れ、亡くなった陶磁器デザイナーの森正洋氏を偲ぶ話が書かれていて、クリエイターとして生きる態度について、美の本質を見極めることについて書かれている。