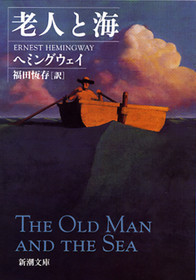読書の効用を理解するのは大人から
2004年08月09日
なみログ at 00:15 | 芸術
2004年8月8日佐賀新聞朝刊1面より
読書離れが進んでいる。
活字離れではない。読書離れだ。県教委が昨年実施した生徒の読書状況の調査結果によると、高校二年生の5割が月に0冊という結果が出ている。この結果を受けて、県は「子ども読書活動推進計画」を基に対策に乗り出すとある。
読書の大切さというのは、大人になってから次第に理解できるようになったが、高校生の頃を振り返ると、私自身もまったく読まなかった内の一人だ。なぜ読書をしなかったか。読書の楽しさを知らなかったという単純な理由があげられる。先生でも友達でも家族でもいいから、だれかが読書の楽しみというものを伝えてあげることができれば、いまよりももっと読むようになるのではと思う。
読書の楽しさというのを伝えるのはむずかしい。うまく伝えることのできる人はどれくらいいるだろう。だれも読書の楽しさを明確に伝えることができぬまま、生徒の自主性にまかせるしか方法がない、というのが現状ではないだろうか?
桑原武夫という人が書いた「文学入門」という本がある。古い本だけれど、文学の面白さについては分かりやすく解説してある。他にもいろいろ読書の効用について書かれた本いくつもある。こういう本をまず大人が読み、十分に理解してから、子どもたちに伝えていく必要がないだろうか。
読書離れが進んでいる。
活字離れではない。読書離れだ。県教委が昨年実施した生徒の読書状況の調査結果によると、高校二年生の5割が月に0冊という結果が出ている。この結果を受けて、県は「子ども読書活動推進計画」を基に対策に乗り出すとある。
読書の大切さというのは、大人になってから次第に理解できるようになったが、高校生の頃を振り返ると、私自身もまったく読まなかった内の一人だ。なぜ読書をしなかったか。読書の楽しさを知らなかったという単純な理由があげられる。先生でも友達でも家族でもいいから、だれかが読書の楽しみというものを伝えてあげることができれば、いまよりももっと読むようになるのではと思う。
読書の楽しさというのを伝えるのはむずかしい。うまく伝えることのできる人はどれくらいいるだろう。だれも読書の楽しさを明確に伝えることができぬまま、生徒の自主性にまかせるしか方法がない、というのが現状ではないだろうか?
桑原武夫という人が書いた「文学入門」という本がある。古い本だけれど、文学の面白さについては分かりやすく解説してある。他にもいろいろ読書の効用について書かれた本いくつもある。こういう本をまず大人が読み、十分に理解してから、子どもたちに伝えていく必要がないだろうか。
この記事へのコメント
読書こそ、人生最大の楽しみである。
私は幼時、「講談社の絵本」からスタートした。国民学校、中学時代、大日本雄弁會講談社の物語本に親しんだ。本格的な読書は高校時代、友人から借りた「大地上、中、下」3巻本。これで近眼になった。
読書は生活環境に大きく左右される。姉二人が本好きで影響を受けた。次いで友人関係。
自分は面白いと感じた本は友人にも読んで貰い、その面白さを共有したいと思い、読んだ本は次々に貸した。だから戻ってこない本が随分あった。
今は図書館での読書が中心。但し好きな作家、加賀乙彦、辻邦夫などは購入して書架に列んでいる。
Posted by 村山 at 2004年08月09日 12:54
村山様コメントありがとうございます。
読書は生活環境に大きく左右される、ということ、そのとおりだと思っています。
Posted by なみ at 2004年08月10日 13:45
アクセスして見て、辻邦生と書くべき所が、邦夫となっていた。訂正してお詫びします。
辻邦生は「安土往還記」で、魅了されて以来、長編は、随分と読んだ。最高に感銘を受けたのは「背教者ユリアヌス」。これに触発されて、ギボンの「ローマ帝国衰亡史」を読んだ。また、「春の戴冠」を読み、フィレンツエのサンタ・マリア・デルフィオーレ(花の聖母寺)に参堂、暗殺の場面を思い浮かべた。
晩年の「西行花伝」は辻邦生の念願の大作であったろう。圧倒される思いで読了した。
-----
PING:
TITLE: 活字離れや本を読まないことを“問題視すること”に対し、一編集者として反論します! ※よーく見てね、活字離れや本を読まないことへの反論なんてな凡人タイトルじゃないからね!
URL: http://sex-therapy.cocolog-nifty.com/editor/2005/10/post_5e38.html
IP: 202.248.237.137
BLOG NAME: 元フリーター編集者の出版日記
DATE: 10/28/2005 07:17:10 PM
<中高年、本離れ進む…読売世論調査>に、編集者として真っ向から反論。編集者だからといって活字離れを問題視しているかというと、わたしは違う。編集者だからこそ、活字離れがどうした?! なにがわるい?! と思う。その理由とは……?
Posted by 村山 at 2004年08月13日 08:59