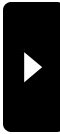スポンサーサイト
冷血(高村薫)
高村薫氏の冷血(上)を読み始める。
第一章の、事件から読み進めるが、どうにも頭に入ってこない。
第二章の、警察から読もう。合田雄一郎がどう立ち回るか。
(なんかレディージョーカーのときと違って、なかなか合田の立場で読めない。。。苦労するな、こりゃ。)
第一章の、事件から読み進めるが、どうにも頭に入ってこない。
第二章の、警察から読もう。合田雄一郎がどう立ち回るか。
(なんかレディージョーカーのときと違って、なかなか合田の立場で読めない。。。苦労するな、こりゃ。)
やきものが登場する物語
なみログ読者のみなさん。おはようございます。
うまか陶というサイトの
やきものが登場する物語を紹介します。
http://www.umakato.jp/archive/bookreview/index.html
現在は、更新がストップしていますが、やきものにスポットをあてた小説紹介も、
こうしてまとまると魅力ありますよね。
うまか陶というサイトの
やきものが登場する物語を紹介します。
http://www.umakato.jp/archive/bookreview/index.html
現在は、更新がストップしていますが、やきものにスポットをあてた小説紹介も、
こうしてまとまると魅力ありますよね。
富士山頂梧竹の碑見学ツアー
富士山が世界遺産に登録されたということで、何気に富士山のことを考えていたら、
そうやん!書聖といわれた中林梧竹さんの、碑があるやん!
と昨夜突如思い出した。
ということで、ネットで検索してみたら、
小城市のWebサイトで、碑を見に行く、
富士山登山ツアー募集中というのを発見!
以下、小城市のWebサイトより。
書聖・中林梧竹没後100年記念事業 富士山頂梧竹の碑見学とソラマチ・浅草3日間参加者募集!
更新日:2013/05/16
平成25年8月は、小城市出身の書家で書聖ともいわれる中林梧竹の没後100年にあたります。この記念すべき年に、富士山頂の浅間大社奥宮の前にある梧竹建立の「鎮國之山」と書かれた銅碑を見学に行きませんか?
http://www.city.ogi.lg.jp/main/9780.html.html
そうやん!書聖といわれた中林梧竹さんの、碑があるやん!
と昨夜突如思い出した。
ということで、ネットで検索してみたら、
小城市のWebサイトで、碑を見に行く、
富士山登山ツアー募集中というのを発見!
以下、小城市のWebサイトより。
書聖・中林梧竹没後100年記念事業 富士山頂梧竹の碑見学とソラマチ・浅草3日間参加者募集!
更新日:2013/05/16
平成25年8月は、小城市出身の書家で書聖ともいわれる中林梧竹の没後100年にあたります。この記念すべき年に、富士山頂の浅間大社奥宮の前にある梧竹建立の「鎮國之山」と書かれた銅碑を見学に行きませんか?
http://www.city.ogi.lg.jp/main/9780.html.html
十代の方へ後悔しないための読書案内
(独読日記ブログで投稿したものを拝借して。)
十代に読んでいればよかったと、二十代になって後悔した本をつらつらと並べておくと、
登山家の野口健氏が、本書を読んだのがきっかけで登山家になったのは有名な話。これから世界へ出てみたい若者にはとくにおすすめ。
村上龍が長崎県佐世保市の高校生三年生の頃を描いた自伝的小説(かな?)。校舎にバリケードを作り立て篭るなど、学生運動の影響下でなんでもありの青春小説。
大学のテニス部に所属する主人公とその仲間たち。恋愛や友情などを等身大で書いた青春小説。高校生におすすめの一冊。
東京で新聞配達所に住み込んでいる偽大学生の少年。地図に×を付け、手当たり次第に爆破のいたずら電話をかける。巻末の松本健一氏の解説文で、<若いこと>、<無名であること>、<貧乏であること>、が英雄になる人物の三要素だといわれる、と書かれている。※およそほとんどの若者にそのチャンスがあると思わせる。。
古い作家の部類に入るが、若い女性にはとても人気のあった作品。騙されたと思って読んでみてください。
太宰治はやっぱり凄い。時代背景が古いのですっと頭に入らないかもしれないが、人の気持ちの機微を見事に書いている。またユーモアや風刺のセンスも抜群。勘違いしている人も多いが、けっして暗いばかりの作家ではない。魚服記、猿ヶ島など掲載。
戦後の日本の男性作家は、大江健三郎の影響を受けた人が多いと思う。村上龍しかり、中上健次しかり。
ちょっと難しいかもしれないが。とりあえず。
十代に読んでいればよかったと、二十代になって後悔した本をつらつらと並べておくと、
 | 青春を山に賭けて (文春文庫)著作者:植村 直己 出版社:文藝春秋 価 格:580 円 |
登山家の野口健氏が、本書を読んだのがきっかけで登山家になったのは有名な話。これから世界へ出てみたい若者にはとくにおすすめ。
 | 69 sixty nine (文春文庫)著作者:村上 龍 出版社:文藝春秋 価 格:480 円 |
村上龍が長崎県佐世保市の高校生三年生の頃を描いた自伝的小説(かな?)。校舎にバリケードを作り立て篭るなど、学生運動の影響下でなんでもありの青春小説。
 | 青が散る〈下〉 (文春文庫)著作者:宮本 輝 出版社:文藝春秋 価 格:490 円 |
大学のテニス部に所属する主人公とその仲間たち。恋愛や友情などを等身大で書いた青春小説。高校生におすすめの一冊。
 | 十九歳の地図 (河出文庫 102B)著作者:中上 健次 出版社:河出書房新社 価 格:525 円 |
東京で新聞配達所に住み込んでいる偽大学生の少年。地図に×を付け、手当たり次第に爆破のいたずら電話をかける。巻末の松本健一氏の解説文で、<若いこと>、<無名であること>、<貧乏であること>、が英雄になる人物の三要素だといわれる、と書かれている。※およそほとんどの若者にそのチャンスがあると思わせる。。
 | TUGUMI(つぐみ) (中公文庫)著作者:吉本 ばなな 出版社:中央公論社 価 格:480 円 |
古い作家の部類に入るが、若い女性にはとても人気のあった作品。騙されたと思って読んでみてください。
 | 晩年 (新潮文庫)著作者:太宰 治 出版社:新潮社 価 格:546 円 |
太宰治はやっぱり凄い。時代背景が古いのですっと頭に入らないかもしれないが、人の気持ちの機微を見事に書いている。またユーモアや風刺のセンスも抜群。勘違いしている人も多いが、けっして暗いばかりの作家ではない。魚服記、猿ヶ島など掲載。
 | 死者の奢り・飼育 (新潮文庫)著作者:大江 健三郎 出版社:新潮社 価 格:460 円 |
戦後の日本の男性作家は、大江健三郎の影響を受けた人が多いと思う。村上龍しかり、中上健次しかり。
 | 異邦人 (新潮文庫)著作者:カミュ 出版社:新潮社 価 格:420 円 |
ちょっと難しいかもしれないが。とりあえず。
筑紫美主子
昨日、東京神保町の古書街にて、佐賀にわかの劇団座長であった筑紫美主子の半生を描いた本をみつけ、買った。
筑紫美主子。
小さいとき、多久小侍(多久原)の中尾神社境内で開かれた芝居を観にいった記憶がある。
あの一座は、筑紫美主子一座だったのかどうか。
佐賀弁が通じないところでは公演も大失敗に終わることがあったようだが、佐賀県内ではどの土地にいっても、絶大な人気を博したとある。
掛け芝居といったりするそうだが、台本どおりに決められた台詞をいうだけではなく、その日、その場の雰囲気で、観客に声を掛け、ときにやりとりをしたりしながら、話を進めていく芝居だそうだ。
演じ手と観客とが一体となった空間が出来上がり、笑いと泪に包まれる。
ござに寝そべり泪を流しながら洟をかむ。そんな光景だ。
筑紫美主子。
小さいとき、多久小侍(多久原)の中尾神社境内で開かれた芝居を観にいった記憶がある。
あの一座は、筑紫美主子一座だったのかどうか。
佐賀弁が通じないところでは公演も大失敗に終わることがあったようだが、佐賀県内ではどの土地にいっても、絶大な人気を博したとある。
掛け芝居といったりするそうだが、台本どおりに決められた台詞をいうだけではなく、その日、その場の雰囲気で、観客に声を掛け、ときにやりとりをしたりしながら、話を進めていく芝居だそうだ。
演じ手と観客とが一体となった空間が出来上がり、笑いと泪に包まれる。
ござに寝そべり泪を流しながら洟をかむ。そんな光景だ。
岡本太郎記念館
アトリエがそのままにしてあり岡本太郎の息遣いが感じられた。
二階の蔵書になにをかいわんや
かれはいたって論理的な芸術家だ。
異次元のスケールで解読不能かのようなアウトプットとパフォーマンスこそ
ピカソを超えるための彼独自のポーズというのか
飢餓海峡映画 感想
飢餓海峡の映画。
正直イマイチだった。
三国連太郎は、よかった。
何がいけなかったのか、原作を読んでいるので、ストーリーのあらましは知っているわけだが、それが仇となったのか、冒頭から説明が過ぎてしまい、なにか弁士による無声映画を見せられているような、紙芝居を見せられているような、そんな感じがした。
しかし、説明がなければ、話の筋も掴めないかもしれないので、なんともはがゆい感じがするが。
それから、ほぼ原作通り、津軽海峡での遭難事故、大火、杉戸八重の十年、犬飼多吉の十年と犯罪、が網羅されており、平均的に描かれている点では筋が分かりやすかった半面、どうしても伝えたいところがどこなのか、監督の思いが希薄になってしまった感が否めない。
いっそのこと、前半の遭難事故と大火あたりははしょってしまい、十年たった今と、犬飼多吉の歩んだ壮絶な前半生をもっと深く描いた方がよかったのかもしれない。
もちろん、八重だって壮絶な前半生を生きているわけで、どちらの立場にたったとしても心を打つ作品には仕上がると思う。
原作を読んだかぎりにおいては、飢餓海峡は、津軽海峡を指すだけではなく、犬飼多吉こと樽見京一郎の、虐げられた故郷での極貧の生活、北海道の過酷な自然条件に涙をのんだ開拓生活。そのすべてが、かれの飢餓海峡であり、八重の前半生もまた飢餓海峡の連続でもあったということだと感じる。
ラストシーンでは樽見京一郎(三国連太郎)が、津軽海峡を渡る連絡船の上から海上に身を投げて終わるのだが、なんともいえない後味の悪さだけが残るだけで、三時間の映画の中に、ぼくはどこにも救いの光を見つけることができなかった。
映画飢餓海峡を観に武雄文化会館へ
十三人の刺客
今週は、火曜日から東京へ。木曜日の夕方から大阪へ移動し、昨日は19時まで大阪だった。
さすがに疲れた。けど、東京、大阪で、おかげさまで仕事があるだけでもありがたい。
昨日の大阪は、堂島近くの某高層ビルの2●階と11階で別々の会社で打ち合わせ。もともと2●階にある会社様とコンサルティング契約をいただいていて、定期訪問しているのだが、とあるところから大阪で相談にのってほしいところがあるということで、場所を尋ねたら、なんと同じビルの11階だということに。
なんと効率的な移動距離だろうかしらん。
とまあ、枕の文章にしてはだらだらととりとめの無いことを書いてしまった。
さて、タイトルの、『十三人の刺客』
見た方も多いだろう。
『いやね、武者震いって奴ですよ』
とこぶしを抑えながらいう役所広司の演技には熱いものを感じた。
それに、松方弘樹の演技も際立っていた。
とても見ごたえのある映画だった。
※横溝正史にはまっている。獄門島⇒八つ墓村⇒犬神家の一族(現在途中)
昨夜の吉本隆明
昨夜、NHK教育テレビで吉本隆明の講演の模様があっていた。
アマゾンでDVDも買えるようだ。
吉本隆明のことはあまり知らないけど、夏目漱石のことを書いた評論があってそれを読んでいたので、興味深くテレビをみた。
芸術的言語論というのが主題で、思った以上に判りやすい内容だった。
桑原武夫氏の書いた第二芸術論に対する小林秀雄氏の批評の解説は、ぼくも、桑原武夫氏の本を一冊読んでいたので議論の論点がよく判った。(たった一冊だが・・・)
いろいろと考えることができた番組だった。
アマゾンでDVDも買えるようだ。
吉本隆明のことはあまり知らないけど、夏目漱石のことを書いた評論があってそれを読んでいたので、興味深くテレビをみた。
芸術的言語論というのが主題で、思った以上に判りやすい内容だった。
桑原武夫氏の書いた第二芸術論に対する小林秀雄氏の批評の解説は、ぼくも、桑原武夫氏の本を一冊読んでいたので議論の論点がよく判った。(たった一冊だが・・・)
いろいろと考えることができた番組だった。
ハックルベリィ・フィン
マークトウェインのハックルベリィ・フィンの冒険
読んだことある人はどれくらいいるだろうか。
トム・ソーヤの冒険が、テレビアニメで人気を博し、ちょうどぼくたちの世代は、再放送も含めて何回も見た経験があるだろう。
ただ、小説となると、案外読んでいないし、さらに、ハックルベリィ・フィンの冒険を読んだ人は案外少ないのではないか。
そういうぼくも、本棚には買って並べていたが、先日読書会で取り上げることになり、ようやく読むことになった。
読むことになったきっかけは、池澤夏樹の「世界文学を読みほどく」という本に、いくつかの世界文学が取り上げられていて、そのなかに、ハックルベリィ・フィンの冒険が解説されていて、池澤氏の解説に惹かれたということもある。
それと、読むきっかけになった最大の要因は、ヘミングウェイが、ハック~の出版後50年に、以下のような言葉を述べていることを知ったからだ。
アメリカの現代文学はすべてマーク・トウェインの「ハックルベリー・フィン」という一冊の本から出発している・・・それ以前にはなにもなかった。それ以後にもこれに匹敵するものはなにもない。
初めて、ハックルベリィ・フィンの冒険を読んでみて、これはすごい小説だな、と思った。のちに影響を受けた作家が多いのも納得できる。初版が1885年なので、日本では明治18年。夏目漱石の吾輩は猫であるが、1905年だそうなので、その文学としての完成度の高さには驚かされる。
いつの時代もそうかもしれないが、目まぐるしく様相が変化する現代において、とくに閉塞感でいっぱいの日本で、ハック的生き方というものを捉えなおしてみることも面白いのかもしれない。
読んだことある人はどれくらいいるだろうか。
トム・ソーヤの冒険が、テレビアニメで人気を博し、ちょうどぼくたちの世代は、再放送も含めて何回も見た経験があるだろう。
ただ、小説となると、案外読んでいないし、さらに、ハックルベリィ・フィンの冒険を読んだ人は案外少ないのではないか。
そういうぼくも、本棚には買って並べていたが、先日読書会で取り上げることになり、ようやく読むことになった。
読むことになったきっかけは、池澤夏樹の「世界文学を読みほどく」という本に、いくつかの世界文学が取り上げられていて、そのなかに、ハックルベリィ・フィンの冒険が解説されていて、池澤氏の解説に惹かれたということもある。
それと、読むきっかけになった最大の要因は、ヘミングウェイが、ハック~の出版後50年に、以下のような言葉を述べていることを知ったからだ。
アメリカの現代文学はすべてマーク・トウェインの「ハックルベリー・フィン」という一冊の本から出発している・・・それ以前にはなにもなかった。それ以後にもこれに匹敵するものはなにもない。
初めて、ハックルベリィ・フィンの冒険を読んでみて、これはすごい小説だな、と思った。のちに影響を受けた作家が多いのも納得できる。初版が1885年なので、日本では明治18年。夏目漱石の吾輩は猫であるが、1905年だそうなので、その文学としての完成度の高さには驚かされる。
いつの時代もそうかもしれないが、目まぐるしく様相が変化する現代において、とくに閉塞感でいっぱいの日本で、ハック的生き方というものを捉えなおしてみることも面白いのかもしれない。
スタバで有田焼
今日の佐賀新聞に、東京銀座マロニエ通り店のスターバックスでは、有田焼のコーヒーカップ、ケーキ皿で楽しめる企画が始まったとある。(2月14日まで)
面白い企画だなあ。有田焼はいくつも企画を打ち出しているが、ターゲットと場所を絞り込んだところに企画の良さを感じる。それから、スターバックスの方が、有田の地域活性化協議会の取り組みに賛同したという点も見逃せない。
最近思うのは、なんだかんだいって、商売は<理念>への共感が必要だということ。やりたいことに共感してくれる人がいれば、物事は動き出す。
スターバックスWebサイト ↓ここに情報があります。
http://www.starbucks.co.jp/concept/mrn/index.html?cid=pc_wh_mrn_arita
<ありたさんぽ>もどうぞ ↓有田情報サイト
http://www.arita.jp/
悪人
今日から仕事始め。
昨年七月から毎週1日か2日は大阪に勤務していて、今年も引き続き大阪行脚を続けることにしている。
いろいろと動いてみると実に面白いもので、多くの新しい出会いがあり、刺激を受けた一年だった。
しかしながら、じゃあ、うまくいっているの?と問われると、決してうまくいっているわけではない。そこがミソ。
うまくいくわけないじゃーん。と開き直っている。(笑)
うまくいく、うまくいかない、なんて今の段階では結論はでまへん。まだまだでっせ。これからでっせ。
ということで、今週木曜日、金曜日も大阪勤務してきます。大阪のみなさん今年もよろしくお願いします。
さて久しぶりのブログ、何を書こうか・・・
あ、そうそう。佐賀で映画のロケがあっている『悪人』
もう一昨年になるが、個人主催の読書会で課題図書として読んだ。結構面白い。
吉田修一という小説家は長崎県出身の小説家で、福岡、佐賀、長崎に土地勘があるので、地理的なリアリティーを感じさせる舞台設計になっている。※朝日新聞の連載小説だったことを考えれば、北部九州以外の読者にどのように伝わるのかは聞いてみないとわからないが。
各章のタイトルの打ち方が、『冷血』に似た感じを受けた。※そのあとすぐに改めて冷血を読むことになった。
ということで、映画が公開される前に、『悪人』の読書会のイベントをしてみても面白そうだ。
それから映画ついでに、シエマで開催されていた『神代監督特集』のある作品を見に行った。
『アフリカの光』(原作丸山健二)
小説は何回も読んでいる。映画の主演は萩原健一と田中邦衛。原作よりもチャラっとしてるところが、受け入れられるかどうかだが、ぼくはあれはあれで良いと思った。原作は丸山健二らしくストイックな感じだ。
内容は、アフリカ大陸へ移住したい若者二人が、北海道のイカ釣り漁船で働き、町のチンピラどもにいじわるをされながらも、旅立ちを夢みている、というもの。なんてことのない、話の筋だ。
小説は、同じく若者二人が旅をするというストーリーでは、有名なところでスタインベックのハツカネズミと人間という小説があるが、ぼくはアフリカの光の方が好きだ。
とりとめのないブログになったけど、さがファンブロガーのみなさん、今年もよろしくお願いいたします。
昨年七月から毎週1日か2日は大阪に勤務していて、今年も引き続き大阪行脚を続けることにしている。
いろいろと動いてみると実に面白いもので、多くの新しい出会いがあり、刺激を受けた一年だった。
しかしながら、じゃあ、うまくいっているの?と問われると、決してうまくいっているわけではない。そこがミソ。
うまくいくわけないじゃーん。と開き直っている。(笑)
うまくいく、うまくいかない、なんて今の段階では結論はでまへん。まだまだでっせ。これからでっせ。
ということで、今週木曜日、金曜日も大阪勤務してきます。大阪のみなさん今年もよろしくお願いします。
さて久しぶりのブログ、何を書こうか・・・
あ、そうそう。佐賀で映画のロケがあっている『悪人』
もう一昨年になるが、個人主催の読書会で課題図書として読んだ。結構面白い。
吉田修一という小説家は長崎県出身の小説家で、福岡、佐賀、長崎に土地勘があるので、地理的なリアリティーを感じさせる舞台設計になっている。※朝日新聞の連載小説だったことを考えれば、北部九州以外の読者にどのように伝わるのかは聞いてみないとわからないが。
各章のタイトルの打ち方が、『冷血』に似た感じを受けた。※そのあとすぐに改めて冷血を読むことになった。
ということで、映画が公開される前に、『悪人』の読書会のイベントをしてみても面白そうだ。
それから映画ついでに、シエマで開催されていた『神代監督特集』のある作品を見に行った。
『アフリカの光』(原作丸山健二)
小説は何回も読んでいる。映画の主演は萩原健一と田中邦衛。原作よりもチャラっとしてるところが、受け入れられるかどうかだが、ぼくはあれはあれで良いと思った。原作は丸山健二らしくストイックな感じだ。
内容は、アフリカ大陸へ移住したい若者二人が、北海道のイカ釣り漁船で働き、町のチンピラどもにいじわるをされながらも、旅立ちを夢みている、というもの。なんてことのない、話の筋だ。
小説は、同じく若者二人が旅をするというストーリーでは、有名なところでスタインベックのハツカネズミと人間という小説があるが、ぼくはアフリカの光の方が好きだ。
とりとめのないブログになったけど、さがファンブロガーのみなさん、今年もよろしくお願いいたします。
10月27日(月)は読書会
さがファンサークルで読書部を創設しています。
第1回目、10月27日(月)の読書会の課題本は、『老人と海』(ヘミングウェイ)に決まりました。
開催概要は、
■課題本:『老人と海』(ヘミングウェイ)
■10月27日(月)
■19時~21時(2時間)
■場所未定:後日参加者にご連絡
■参加費:喫茶店で開催する場合も想定して、飲み物代をご用意ください。あと駐車場料金も。
■参加資格:20歳以上の男女。課題本を当日までに必ず読んでおくこと。
です。
さがファン読書部では部員を募集しています。
読書初心者大歓迎。
■さがファン読書部参加希望の方はここをクリック
興味のある方はぜひご参加ください。
毎月1回開催する、リアル読書会は、基本的に佐賀市内で開催します。
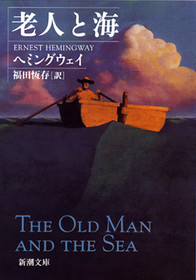
第1回目、10月27日(月)の読書会の課題本は、『老人と海』(ヘミングウェイ)に決まりました。
開催概要は、
■課題本:『老人と海』(ヘミングウェイ)
■10月27日(月)
■19時~21時(2時間)
■場所未定:後日参加者にご連絡
■参加費:喫茶店で開催する場合も想定して、飲み物代をご用意ください。あと駐車場料金も。
■参加資格:20歳以上の男女。課題本を当日までに必ず読んでおくこと。
です。
さがファン読書部では部員を募集しています。
読書初心者大歓迎。
■さがファン読書部参加希望の方はここをクリック
興味のある方はぜひご参加ください。
毎月1回開催する、リアル読書会は、基本的に佐賀市内で開催します。
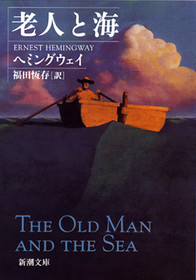
書店苦境
2008年9月10日(水)佐賀新聞朝刊9頁より
地域の書店が苦境だという。
いまに始まった話ではなく、十年前くらいから言われている話だろう。
しかしこの数年というかこの1年でも、書店の状況は厳しさを増しているようだ。
出版不況と書店の苦境はときを同じくして進行していて、このところの自費出版ブームも、自費出版社自体の破綻などもあり、イメージダウンもあるだろう、出版全体が厳しいようだ。
さて、書店に目を向けると、ネット通販が伸びていてそういう観点から見るといち早くネット販売に置き換えることができた出版社、書店は少なからず成果はでているのではないかと思われる。ただし、新刊本を扱うところは販社の関係もあり、ネット販売に自らの考えだけでは移行できなかった。古書店は思い切ってリアル店舗を閉鎖してネットだけに絞り込んだ店もある。佐賀市内でもある。
七、八年前だが、地場大手の某書店に、ネット通販とか、会員カード活用の提案をしたことがあったが、そのときは見向きもされなかった。ほどなく、大手販社の子会社になったので、先行投資の自由は無くなってしまったようだが、いま、その書店では会員カードが作られ、ポイントが貯まるようになっている。
書店では、ポイントはつけられない、と言っていたのに、他社がやりだしたことを背景に、入れずにはいられなくなったということだろう。しかし、判断は五年遅いと思う。
ネットの流れは止めることはできない。早くネットを使ってどうするか、を考えないとならないと思う。
ネットや携帯電話で注文して宅配なんてのは、ぼーっとしていると、あっという間に商売のひとつのあり方として広まると思う。
セブンイレブンで宅配がはじまっているけど、だれもつかわないだろう、がいつのまにか、自分も使うようになっているかもしれない。
そう考えると、業種によっては、
早く取り組まないとならないと思うが。
※すでにやっているところも多いが、ケーキ屋さんの、たんじょうびのケーキなどは、PCや携帯によるネット注文が一般的になると思うがどうだろうか?
(まだ実現してなくて、そういう注文を取りたい店は、ぜひさがファン使ってくださいね!相談乗ります)
地域の書店が苦境だという。
いまに始まった話ではなく、十年前くらいから言われている話だろう。
しかしこの数年というかこの1年でも、書店の状況は厳しさを増しているようだ。
出版不況と書店の苦境はときを同じくして進行していて、このところの自費出版ブームも、自費出版社自体の破綻などもあり、イメージダウンもあるだろう、出版全体が厳しいようだ。
さて、書店に目を向けると、ネット通販が伸びていてそういう観点から見るといち早くネット販売に置き換えることができた出版社、書店は少なからず成果はでているのではないかと思われる。ただし、新刊本を扱うところは販社の関係もあり、ネット販売に自らの考えだけでは移行できなかった。古書店は思い切ってリアル店舗を閉鎖してネットだけに絞り込んだ店もある。佐賀市内でもある。
七、八年前だが、地場大手の某書店に、ネット通販とか、会員カード活用の提案をしたことがあったが、そのときは見向きもされなかった。ほどなく、大手販社の子会社になったので、先行投資の自由は無くなってしまったようだが、いま、その書店では会員カードが作られ、ポイントが貯まるようになっている。
書店では、ポイントはつけられない、と言っていたのに、他社がやりだしたことを背景に、入れずにはいられなくなったということだろう。しかし、判断は五年遅いと思う。
ネットの流れは止めることはできない。早くネットを使ってどうするか、を考えないとならないと思う。
ネットや携帯電話で注文して宅配なんてのは、ぼーっとしていると、あっという間に商売のひとつのあり方として広まると思う。
セブンイレブンで宅配がはじまっているけど、だれもつかわないだろう、がいつのまにか、自分も使うようになっているかもしれない。
そう考えると、業種によっては、
早く取り組まないとならないと思うが。
※すでにやっているところも多いが、ケーキ屋さんの、たんじょうびのケーキなどは、PCや携帯によるネット注文が一般的になると思うがどうだろうか?
(まだ実現してなくて、そういう注文を取りたい店は、ぜひさがファン使ってくださいね!相談乗ります)
読書部開設!部員募集!さがファンサークル
このたび、さがファン読書部を開設しました!
さがファンブログトップページ上部の、<サークル>というタブをクリックして、サークルトップページから入部希望の方は入部申請ができます。(承認制にしていますので、承認後入部が許可されます。とくに入部制限はありませんのでお気軽に(笑))
↓↓ここからおすすみください↓↓
■さがファンブログサークルトップ
みんなで月1回、同じ小説を読んで、あーだこーだ感想を述べ合い、議論を深めるというのが読書部の活動になります。
※リアル読書会が中心です。場所は、基本佐賀市を考えていますが、入部メンバーが広域だったら持ち回りでもいいです。
男女年齢もちろん問いませんので、ぜひお気軽にご参加ください。
(ただし、ブロガーに高校生は少ないと思いますが、高校生以下はひょっとすると難しく感じることもあるかもです)
年に1回は、読書部で読書の旅も計画してみたいとも思っています。
遠藤周作文学館とか、松本清張記念館とか、佐世保の図書館に村上龍の著書を読みにいくとか、諫早の図書館に野呂邦暢
の著書を訪ねるとか。
といった具合です。入部希望者はぜひ。(5名以上にならないと廃部します。。)
さがファンブログトップページ上部の、<サークル>というタブをクリックして、サークルトップページから入部希望の方は入部申請ができます。(承認制にしていますので、承認後入部が許可されます。とくに入部制限はありませんのでお気軽に(笑))
↓↓ここからおすすみください↓↓
■さがファンブログサークルトップ
みんなで月1回、同じ小説を読んで、あーだこーだ感想を述べ合い、議論を深めるというのが読書部の活動になります。
※リアル読書会が中心です。場所は、基本佐賀市を考えていますが、入部メンバーが広域だったら持ち回りでもいいです。
男女年齢もちろん問いませんので、ぜひお気軽にご参加ください。
(ただし、ブロガーに高校生は少ないと思いますが、高校生以下はひょっとすると難しく感じることもあるかもです)
年に1回は、読書部で読書の旅も計画してみたいとも思っています。
遠藤周作文学館とか、松本清張記念館とか、佐世保の図書館に村上龍の著書を読みにいくとか、諫早の図書館に野呂邦暢
の著書を訪ねるとか。
といった具合です。入部希望者はぜひ。(5名以上にならないと廃部します。。)
佐嘉神社でチャリティーライブ!!
いよいよ今日。佐嘉神社特設ステージへ!!


■チャリティーライブ2008 HOME
■8月2日(土)
■12時スタート 18時30まで
■佐嘉神社内特設ステージ
■入場無料


■チャリティーライブ2008 HOME
■8月2日(土)
■12時スタート 18時30まで
■佐嘉神社内特設ステージ
■入場無料
読書塾
有田焼万年筆
2008年7月11日(金)佐賀新聞朝刊17頁より
有田焼万年筆が、洞爺湖サミット記念品として使用されたとある。
数ある候補品の中から選ばれたということで、有田焼の凄さと、有田焼万年筆を開発に従事した、佐賀ダンボール紹介、香蘭社、源右衛門窯、セーラー万年筆、丸善、の熱意に感服する。
有田焼といえば、有田焼カレーが全国放送のテレビで紹介されたこともあり、注目を少し浴びているようだが、有田焼が珍しいのか、駅弁で焼きカレーが珍しいのか、どちらも珍しいので注目を浴びたのか、ポイントが実のところよくわからない。
有田焼プリンも売れるのかといえば、それはわからないし、有田焼ひつまぶしとか、有田焼うどんとか、有田焼うどんすき、とかもいけるのかどうなのか。
もちろん味が伴っていないとならないし。
有田鍋焼きうどん、とか、有田焼うどんすき、なんかは良いと思うんだけど、いまから夏なので、冬にならないとねえ・・
有田焼万年筆が、洞爺湖サミット記念品として使用されたとある。
数ある候補品の中から選ばれたということで、有田焼の凄さと、有田焼万年筆を開発に従事した、佐賀ダンボール紹介、香蘭社、源右衛門窯、セーラー万年筆、丸善、の熱意に感服する。
有田焼といえば、有田焼カレーが全国放送のテレビで紹介されたこともあり、注目を少し浴びているようだが、有田焼が珍しいのか、駅弁で焼きカレーが珍しいのか、どちらも珍しいので注目を浴びたのか、ポイントが実のところよくわからない。
有田焼プリンも売れるのかといえば、それはわからないし、有田焼ひつまぶしとか、有田焼うどんとか、有田焼うどんすき、とかもいけるのかどうなのか。
もちろん味が伴っていないとならないし。
有田鍋焼きうどん、とか、有田焼うどんすき、なんかは良いと思うんだけど、いまから夏なので、冬にならないとねえ・・
松浦潟
2008年7月10日(木)佐賀新聞朝刊11頁より
6月29日に行われた、第31回佐賀新聞読者文芸大会の様子が掲載されている。
講演会は、唐津市の洋々閣女将、大河内氏によるもので、
うたがよみがえる時
―白秋と「松浦潟」
という題で話された。
講演内容については、ぜひ記事を読んでもらいたい。
記事中には、松浦潟と呼ばれる、それまで聞いたことのなかった民謡を宿泊客から聞いた女将が、その後、その出所を調べていくうちに、北原白秋の作であること、白秋が呼子の松浦漬という会社の社長宅に滞在したときに書いたといわれていること、歌詞は、当時の唐津をPRする観光本が下敷きになっていること、などが明らかにされていく。
なかでも、松浦潟の民謡を覚えている方に会って、テープレコーダーに録音したことや、その後、日本民謡協会から復曲したテープが発行された、というところが、出所をめぐる話のターニングポイントになっている。
松浦潟
という言葉に惹かれるようにして探された、民謡「松浦潟」
言葉の力、言霊で、
歌がよみがえる
と締めくくってある。
なるほどぉ。
※個人的な連絡でございます。Yさまありがとうございました。
6月29日に行われた、第31回佐賀新聞読者文芸大会の様子が掲載されている。
講演会は、唐津市の洋々閣女将、大河内氏によるもので、
うたがよみがえる時
―白秋と「松浦潟」
という題で話された。
講演内容については、ぜひ記事を読んでもらいたい。
記事中には、松浦潟と呼ばれる、それまで聞いたことのなかった民謡を宿泊客から聞いた女将が、その後、その出所を調べていくうちに、北原白秋の作であること、白秋が呼子の松浦漬という会社の社長宅に滞在したときに書いたといわれていること、歌詞は、当時の唐津をPRする観光本が下敷きになっていること、などが明らかにされていく。
なかでも、松浦潟の民謡を覚えている方に会って、テープレコーダーに録音したことや、その後、日本民謡協会から復曲したテープが発行された、というところが、出所をめぐる話のターニングポイントになっている。
松浦潟
という言葉に惹かれるようにして探された、民謡「松浦潟」
言葉の力、言霊で、
歌がよみがえる
と締めくくってある。
なるほどぉ。
※個人的な連絡でございます。Yさまありがとうございました。