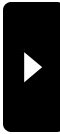スポンサーサイト
鯛女房物語(唐津民話の舞台)
2007年2月24日(土)佐賀新聞朝刊19頁より
鯛女房物語
なにかというと、明日、25日(日)に唐津市文化体育館で公演される、市民劇の演題だ。
唐津に伝わる民話を題材にした芝居で、30年ぶりに市民で復活させるというもの。
新聞記事によると、話の内容は、
唐津の浜で小料理屋を営む男が釣ったタイを逃がすという粗筋だそうだ。
「鶴の恩返しの唐津版」とある。
芝居は、約七十人の市民が登場するもので、保育園の園児なども登場するとな。坂井市長も。
ということで、興味のある人は、
唐津市文化体育館へ
■公演時間 1回目 13時~ 2回目 18時~
■入場料 2000円(当日) 1500円(前売り)←唐津市アルピノなどでも販売
中学生以下無料
■問い合わせ
NPO法人 日本の伝統文化を守る会 TEL 0955-73-0336
詳しくは、唐津市のサイトで
■唐津市ポータルサイトでの紹介ページ
鯛女房物語
なにかというと、明日、25日(日)に唐津市文化体育館で公演される、市民劇の演題だ。
唐津に伝わる民話を題材にした芝居で、30年ぶりに市民で復活させるというもの。
新聞記事によると、話の内容は、
唐津の浜で小料理屋を営む男が釣ったタイを逃がすという粗筋だそうだ。
「鶴の恩返しの唐津版」とある。
芝居は、約七十人の市民が登場するもので、保育園の園児なども登場するとな。坂井市長も。
ということで、興味のある人は、
唐津市文化体育館へ
■公演時間 1回目 13時~ 2回目 18時~
■入場料 2000円(当日) 1500円(前売り)←唐津市アルピノなどでも販売
中学生以下無料
■問い合わせ
NPO法人 日本の伝統文化を守る会 TEL 0955-73-0336
詳しくは、唐津市のサイトで
■唐津市ポータルサイトでの紹介ページ
幸福の黄色いハンカチは米国の物語だった・・
2007年2月14日(水)佐賀新聞朝刊25頁より
いやあ、まったく知らなかったのだが、
山田洋次監督の映画「幸福の黄色いハンカチ」。
この映画の原作は、米国の作家ピートハミルさんのコラムだったという話。
知らない人多いんじゃないかなあ。
その「幸福の黄色いハンカチ」が、米国でリメークされるという記事が載っている。(全国配信記事)
ということで山田洋次監督も、もともと米国の物語だから、米国で映画化されるのは感無量という談話も。
武田鉄也が転んだときに何べんも言う、「あいたーっす(痛い)」というせりふや、高倉健が、たこ八郎ふんするチンピラを見事に退治する場面、それを見て驚く桃井かおり、の顔とせりふ。
そんな場面のひとつひとつが、どのような形で受け継がれるのか楽しみだ。(そんな細かい場面は受け継がれないか・・(笑))
幸福の黄色いハンカチは、ああいうお涙頂戴のヒューマンドラマは嫌いな人は嫌いで、賛否両論あると思うが、私は結構好きだ。(小説で読むとなれば突込みどころ満載かもしれないけど)
あと、佐賀新聞の経済面を見ていたら、
福博印刷、6月にも創刊
横浜「ぱど」と合弁会社
なる文字が。
えーっ・・・。知らなかったというわけはないのだが、2月5日に社内説明会があり、私もそのとき初めて知った次第。
「ぱど」は、九州ではなじみがないが、関東、関西圏を中心に発行されているフリーペーパーで、発行部数ももの凄く多く、佐賀新聞記事によると1260万部。
そのフリーペーパーが、九州地区にはなかったということで、福博印刷が本体の「ぱど」と組んで福岡で発行するというもの。
全国でも有数のフリーペーパー激戦地といわれる福岡で、多くの人に親しまれる冊子になることを期待する。
いやあ、まったく知らなかったのだが、
山田洋次監督の映画「幸福の黄色いハンカチ」。
この映画の原作は、米国の作家ピートハミルさんのコラムだったという話。
知らない人多いんじゃないかなあ。
その「幸福の黄色いハンカチ」が、米国でリメークされるという記事が載っている。(全国配信記事)
ということで山田洋次監督も、もともと米国の物語だから、米国で映画化されるのは感無量という談話も。
武田鉄也が転んだときに何べんも言う、「あいたーっす(痛い)」というせりふや、高倉健が、たこ八郎ふんするチンピラを見事に退治する場面、それを見て驚く桃井かおり、の顔とせりふ。
そんな場面のひとつひとつが、どのような形で受け継がれるのか楽しみだ。(そんな細かい場面は受け継がれないか・・(笑))
幸福の黄色いハンカチは、ああいうお涙頂戴のヒューマンドラマは嫌いな人は嫌いで、賛否両論あると思うが、私は結構好きだ。(小説で読むとなれば突込みどころ満載かもしれないけど)
あと、佐賀新聞の経済面を見ていたら、
福博印刷、6月にも創刊
横浜「ぱど」と合弁会社
なる文字が。
えーっ・・・。知らなかったというわけはないのだが、2月5日に社内説明会があり、私もそのとき初めて知った次第。
「ぱど」は、九州ではなじみがないが、関東、関西圏を中心に発行されているフリーペーパーで、発行部数ももの凄く多く、佐賀新聞記事によると1260万部。
そのフリーペーパーが、九州地区にはなかったということで、福博印刷が本体の「ぱど」と組んで福岡で発行するというもの。
全国でも有数のフリーペーパー激戦地といわれる福岡で、多くの人に親しまれる冊子になることを期待する。
唐津の小説家白石氏が小説「月あかり」を出版
2007年1月10日(水)佐賀新聞朝刊13頁より
すっかり、なみログをさぼってしまっていた。。
今日からできるだけさぼらずに書こう。
さて、今朝の佐賀新聞の13面には、唐津在住の白石すみほ氏が、自身の小説「月あかり」を出版したとある。
白石氏は、現在佐賀県文学賞の小説部門の審査員を務める小説家で、これまでもいくつも作品を発表している。
今回の小説「月あかり」は、唐津新聞紙面に2005年から2006年6月まで連載されたものということで、氏いわく、「新聞連載は、毎日次につながるような”ヤマ場”を設けないければならず大変だったが、結果的にはメリハリがついた。読者の感想も今後書き続ける活力につながった」と感想を寄せている。
私も佐賀文学という同人誌に属しているので、県内の文学関係者ということで面識があり、会えばいろいろと話を聞かせていただいている。
県内にはほかにもよい作品を書く小説家が何人かいる。全国発行の商業誌に載るような作家ではないが、地域の歴史や風土、生活、人間模様を巧みに描き、その地域の人間がどのような生活をし、なにを考え、どのように現在を切り開いてきたかを、小説を通して知ることもできる。
私自身は、そのように地域に密着した小説はまだ書いたことがないが、そのような小説は、地域の人間でしか書けないのだと思うと、とても貴重なことだと思う。
すっかり、なみログをさぼってしまっていた。。
今日からできるだけさぼらずに書こう。
さて、今朝の佐賀新聞の13面には、唐津在住の白石すみほ氏が、自身の小説「月あかり」を出版したとある。
白石氏は、現在佐賀県文学賞の小説部門の審査員を務める小説家で、これまでもいくつも作品を発表している。
今回の小説「月あかり」は、唐津新聞紙面に2005年から2006年6月まで連載されたものということで、氏いわく、「新聞連載は、毎日次につながるような”ヤマ場”を設けないければならず大変だったが、結果的にはメリハリがついた。読者の感想も今後書き続ける活力につながった」と感想を寄せている。
私も佐賀文学という同人誌に属しているので、県内の文学関係者ということで面識があり、会えばいろいろと話を聞かせていただいている。
県内にはほかにもよい作品を書く小説家が何人かいる。全国発行の商業誌に載るような作家ではないが、地域の歴史や風土、生活、人間模様を巧みに描き、その地域の人間がどのような生活をし、なにを考え、どのように現在を切り開いてきたかを、小説を通して知ることもできる。
私自身は、そのように地域に密着した小説はまだ書いたことがないが、そのような小説は、地域の人間でしか書けないのだと思うと、とても貴重なことだと思う。
硫黄島~戦場の郵便配達~と市丸利之助伝
今日12月9日(土)フジテレビ系列で放映される、ドキュメンタリードラマ
硫黄島~戦場の郵便配達。
私が働く福博印刷の出門堂という出版事業部で、その登場人物である市丸利之助について書かれた本、「米国大統領への手紙 市丸利之助伝」が発刊されている。
この本は、佐賀の偉人などを顕彰すべく創設された、肥前佐賀文庫というシリーズの第1回目配本分だ。
ドラマをご覧になった方でさらに詳しく市丸利之助について知りたい方は、さがファンブックスでご購入いただけます。
■さがファンブックスで、「米国大統領への手紙 市丸利之助伝」を買う

硫黄島~戦場の郵便配達。
私が働く福博印刷の出門堂という出版事業部で、その登場人物である市丸利之助について書かれた本、「米国大統領への手紙 市丸利之助伝」が発刊されている。
この本は、佐賀の偉人などを顕彰すべく創設された、肥前佐賀文庫というシリーズの第1回目配本分だ。
ドラマをご覧になった方でさらに詳しく市丸利之助について知りたい方は、さがファンブックスでご購入いただけます。
■さがファンブックスで、「米国大統領への手紙 市丸利之助伝」を買う

さがんひすとりい・・
2006年11月29日(水)佐賀新聞朝刊13頁より
県内文化を論評する「文化時評2006」。
演劇・イベントのコーナーは、ティーンズミュージカルSAGA代表の栗原氏がペンをとっている。
今日の内容は、県演劇フェステバル「佐賀演劇王争奪戦!!」に関する内容で、氏が2つの劇団の公演を見た感想が述べられている。氏によると、佐賀で活躍している役者のレベルがかなり上がってきていて、しっかしした舞台を楽しめるようになったということ。
それと比較するように、後半は「2007年青春・佐賀総体 250日前進大会」で見た、高校生による「さがんひすとりい」というミュージカル仕立てのアトラクションについて言及してあり、内容に唖然としたとある。(言葉が濁してあり、演技のレベルなのか、舞台美術や音楽が寒かったのか、書かれていない・・)
ふ~ん。
具体的な内容が書かれていないので、なんともいえないが、なんとかしたほうがいいのだろう。
ところでそのような文章を読んで、先日こういう話を聞いた。
中学校の文化祭で、クラスで演劇をやることになっているのだが、芝居の脚本は先生が書きそれを演じるというもの。
大体どうなのだろうか?
私が中学生のときは、脚本を書き下ろす必要なない、といわれたが、本を下敷きに脚本は何人かで起したのだけど。あーだこーだいいながら。
(小学校6年のときの、おたのしみ会の出し物は、脚本を書き下ろしてドタバタの芝居をした)
今思えば、スポーツは体育があったり、自分も野球をしていたりと、なんだかんだとスポーツに触れる機会は多かったが、本を読むこと、文章を書くこと、芝居をすること、絵を書くことなどの芸術面は、ほとんどやる機会がなく、文化祭の前に慌ててその場しのぎでやるような感じだった。
それじゃあ、いい芝居なんてできっこないなー、という感じがする。
まあ全員参加なので、芝居の質というより、参加するのに意義があるというレベルだろうから、それはそれでいいかも知れないが。
たまたま私は、その後、小説を読むようになり、自分で創作もするようになったので、振り返ると小学校の頃、芝居の脚本も書いたなーとそれが少しは引き金になっていると強引にもっていくこともできるが、小学校、中学校の芝居の経験を通じて、大人になっていまだに表現活動を続けているという、同級生はどれくらいいるだろうか、と思う。
福岡は全国的にも演劇が盛んな都市ということで、先日、日経新聞だったか、日経流通新聞だったかに取り上げられていた。福岡で活躍する人の中には佐賀県出身者も多くいるはずだ。推測だが。
佐賀新聞を三年くらいまじめに読んでいるけど、佐賀の劇団に関する記事が増えてきているのを実感するので、今後ますます期待したい。
なんかまとまってしまった。。
県内文化を論評する「文化時評2006」。
演劇・イベントのコーナーは、ティーンズミュージカルSAGA代表の栗原氏がペンをとっている。
今日の内容は、県演劇フェステバル「佐賀演劇王争奪戦!!」に関する内容で、氏が2つの劇団の公演を見た感想が述べられている。氏によると、佐賀で活躍している役者のレベルがかなり上がってきていて、しっかしした舞台を楽しめるようになったということ。
それと比較するように、後半は「2007年青春・佐賀総体 250日前進大会」で見た、高校生による「さがんひすとりい」というミュージカル仕立てのアトラクションについて言及してあり、内容に唖然としたとある。(言葉が濁してあり、演技のレベルなのか、舞台美術や音楽が寒かったのか、書かれていない・・)
ふ~ん。
具体的な内容が書かれていないので、なんともいえないが、なんとかしたほうがいいのだろう。
ところでそのような文章を読んで、先日こういう話を聞いた。
中学校の文化祭で、クラスで演劇をやることになっているのだが、芝居の脚本は先生が書きそれを演じるというもの。
大体どうなのだろうか?
私が中学生のときは、脚本を書き下ろす必要なない、といわれたが、本を下敷きに脚本は何人かで起したのだけど。あーだこーだいいながら。
(小学校6年のときの、おたのしみ会の出し物は、脚本を書き下ろしてドタバタの芝居をした)
今思えば、スポーツは体育があったり、自分も野球をしていたりと、なんだかんだとスポーツに触れる機会は多かったが、本を読むこと、文章を書くこと、芝居をすること、絵を書くことなどの芸術面は、ほとんどやる機会がなく、文化祭の前に慌ててその場しのぎでやるような感じだった。
それじゃあ、いい芝居なんてできっこないなー、という感じがする。
まあ全員参加なので、芝居の質というより、参加するのに意義があるというレベルだろうから、それはそれでいいかも知れないが。
たまたま私は、その後、小説を読むようになり、自分で創作もするようになったので、振り返ると小学校の頃、芝居の脚本も書いたなーとそれが少しは引き金になっていると強引にもっていくこともできるが、小学校、中学校の芝居の経験を通じて、大人になっていまだに表現活動を続けているという、同級生はどれくらいいるだろうか、と思う。
福岡は全国的にも演劇が盛んな都市ということで、先日、日経新聞だったか、日経流通新聞だったかに取り上げられていた。福岡で活躍する人の中には佐賀県出身者も多くいるはずだ。推測だが。
佐賀新聞を三年くらいまじめに読んでいるけど、佐賀の劇団に関する記事が増えてきているのを実感するので、今後ますます期待したい。
なんかまとまってしまった。。
アジアのハリウッド構想。ディレクター育成講座が開始。
2006年11月27日(月)佐賀新聞朝刊19頁より
佐賀県が進める、アジアのハリウッド構想。
今月まで行なわれていた、プロデューサー講座に引き続き、ディレクター講座が始まった。
その第1回研修が昨日、佐嘉神社記念館で行なわれ、映画プロデューサーの奥山和由氏が講演を行なったとある。
ここにきて、佐賀県のアジアのハリウッド構想は、具体的な取り組みが目に見える形で動き出したなあという感じだ。
映画といえば、本を読むようになってから映画はあまり観なくなった。もちろん映画は映画の良さがあるのだが、2時間か3時間で話が終ってしまうストーリー展開に、どうしても端折ったような感じがして、ここ2、3年で観た映画はどれもそんな感じがしてならなかった。とくに、ハリウッド映画はその傾向を強く抱く。まあ、何でもかんでも詰め込めばいいという問題でもないが。。
とそんなことを書いていると、二、三日前の佐賀新聞に、映画評論家西村雄一郎氏のコラムがあり、その中で、
何を描くかよりも、何を描かないか、
というのも大事である、というようなことが書いてあった。
含蓄のある言葉だと思った。
ワールドトレードセンターという映画に関するコラムだった。ワールドトレードセンターの映画には、テロのことはほとんど描かれていないということを捉えての解説だった。
話は少し脱線するが、
何かの番組で、北野武氏が、例えば殺人事件を映画で描写していくとき、一人目の殺人の描写に拳銃をつかったとすると、二人目か、三人目までは拳銃そのものを出してもいいが、四人目は、もう、拳銃そのものは出す必要はない。
ということを言っていた。
佐賀県が進める、アジアのハリウッド構想。
今月まで行なわれていた、プロデューサー講座に引き続き、ディレクター講座が始まった。
その第1回研修が昨日、佐嘉神社記念館で行なわれ、映画プロデューサーの奥山和由氏が講演を行なったとある。
ここにきて、佐賀県のアジアのハリウッド構想は、具体的な取り組みが目に見える形で動き出したなあという感じだ。
映画といえば、本を読むようになってから映画はあまり観なくなった。もちろん映画は映画の良さがあるのだが、2時間か3時間で話が終ってしまうストーリー展開に、どうしても端折ったような感じがして、ここ2、3年で観た映画はどれもそんな感じがしてならなかった。とくに、ハリウッド映画はその傾向を強く抱く。まあ、何でもかんでも詰め込めばいいという問題でもないが。。
とそんなことを書いていると、二、三日前の佐賀新聞に、映画評論家西村雄一郎氏のコラムがあり、その中で、
何を描くかよりも、何を描かないか、
というのも大事である、というようなことが書いてあった。
含蓄のある言葉だと思った。
ワールドトレードセンターという映画に関するコラムだった。ワールドトレードセンターの映画には、テロのことはほとんど描かれていないということを捉えての解説だった。
話は少し脱線するが、
何かの番組で、北野武氏が、例えば殺人事件を映画で描写していくとき、一人目の殺人の描写に拳銃をつかったとすると、二人目か、三人目までは拳銃そのものを出してもいいが、四人目は、もう、拳銃そのものは出す必要はない。
ということを言っていた。
浅葉克巳氏と古湯温泉とつがに
2006年11月11日(土)佐賀新聞朝刊24頁より
11月13日(月)、伊万里・有田地域の再生に取り組む「有田ルネッサンス委員会」では、有田焼の新しいデザインを探るシンポジウムを開催するとある。
新聞記事によると、著名なデザイナーら7人がパネリストになり、窯業界が目指すデザインの方向性を展望するというもの。
パネリストのひとりは、グラフィックデザイナーの第一人者である浅葉克巳氏。
シンポジウムは入場無料で、場所は県の窯業技術センターである。
と記事をネタにブログを書きつつ、昨日、縁があり浅葉克巳氏をもてなす会合に末席ながら参加したのを振り返る。
正直いって浅葉氏のことは、よく知らなかった。私が働く会社で出版事業をしていて、出版事業第一弾の、八賢伝とうい本の装丁を浅葉氏に依頼したということで初めて知った。
インパクトのある装丁だったこともあり、八賢伝の本は、佐賀県出版社の発行分としては、異例のロングセラーになっていて、内容もさることながら、装丁に対する反響も多い。
そんな浅葉氏が座る会合の末席だったわけだが、古湯温泉の旅館の料理がたまらなく美味しかった。写真をよく撮らないので、ブログで伝えることができずに残念なのだが、鯉のあらい、鮎の塩焼き、佐賀牛の石焼ステーキに、つがにのボイル。天ぷらに、かにご飯。すべてが大満足。
古湯温泉は、嬉野温泉、武雄温泉に比べてすこし知名度が低いようだが、なんのなんの、先々週だったか、熊の川温泉の旅館にもいったけど、古湯、熊の川温泉は、佐賀市から車で30分圏だし、福岡からも近い。知名度的にはまだまだという感じかもしれないが、情緒のある小旅館が立ち並ぶのもまた魅力。
一度、さがファンでも、特集を組みたい温泉場だ。
11月13日(月)、伊万里・有田地域の再生に取り組む「有田ルネッサンス委員会」では、有田焼の新しいデザインを探るシンポジウムを開催するとある。
新聞記事によると、著名なデザイナーら7人がパネリストになり、窯業界が目指すデザインの方向性を展望するというもの。
パネリストのひとりは、グラフィックデザイナーの第一人者である浅葉克巳氏。
シンポジウムは入場無料で、場所は県の窯業技術センターである。
と記事をネタにブログを書きつつ、昨日、縁があり浅葉克巳氏をもてなす会合に末席ながら参加したのを振り返る。
正直いって浅葉氏のことは、よく知らなかった。私が働く会社で出版事業をしていて、出版事業第一弾の、八賢伝とうい本の装丁を浅葉氏に依頼したということで初めて知った。
インパクトのある装丁だったこともあり、八賢伝の本は、佐賀県出版社の発行分としては、異例のロングセラーになっていて、内容もさることながら、装丁に対する反響も多い。
そんな浅葉氏が座る会合の末席だったわけだが、古湯温泉の旅館の料理がたまらなく美味しかった。写真をよく撮らないので、ブログで伝えることができずに残念なのだが、鯉のあらい、鮎の塩焼き、佐賀牛の石焼ステーキに、つがにのボイル。天ぷらに、かにご飯。すべてが大満足。
古湯温泉は、嬉野温泉、武雄温泉に比べてすこし知名度が低いようだが、なんのなんの、先々週だったか、熊の川温泉の旅館にもいったけど、古湯、熊の川温泉は、佐賀市から車で30分圏だし、福岡からも近い。知名度的にはまだまだという感じかもしれないが、情緒のある小旅館が立ち並ぶのもまた魅力。
一度、さがファンでも、特集を組みたい温泉場だ。
演劇王争奪戦!
2006年11月1日(水)佐賀新聞朝刊13頁より
先日10月28日(土)に企画した、井上光晴文学館(じつは井上光晴文学室だった・・)を訪問するツアーは、当日2名の欠席者が出たが、8名の参加者で行った。
天気も快晴で、崎戸島の先っぽにある、ホテル咲き都から展望する東シナ海も素晴らしく、絶対に行って損はない文学ツアーだった。佐賀の文学界の生き字引の一人である、城と九州文学の同人である畑島氏の参加もあり、文学佐賀の乱の話や、県内各同人誌の話も聞け、大変面白かった。
もちろん畑島氏は、生の井上氏を見た人なので、井上光晴についての話もばっちり聞けた。
あとで道中の模様や、写真も掲載したいと思う。
さて、今日の新聞をみると、「演劇王争奪戦 3日スタート」とある、
何のことかというと、佐賀県内で活躍するアマチュア劇団が、観客も審査員に加わりつつ、演劇王を決定するというもの。
佐賀市愛敬町の、STAGEMARO という舞台で、11月3日から、日曜と祝日毎に、午後2時から芝居を行う。
県内8劇団がエントリーをしていて、見事演劇王に輝いた劇団には賞金20万円が贈られるという、素晴らしい企画だ!
(某県内有名文学賞なんて図書券だけ)
お問い合わせは、STAGEMAROへ電話してほしい。
↑Webサイトがあったので、リンクしておきます。
いやあ、演劇は元気があっていいなあ縲懊懊怐B
先日10月28日(土)に企画した、井上光晴文学館(じつは井上光晴文学室だった・・)を訪問するツアーは、当日2名の欠席者が出たが、8名の参加者で行った。
天気も快晴で、崎戸島の先っぽにある、ホテル咲き都から展望する東シナ海も素晴らしく、絶対に行って損はない文学ツアーだった。佐賀の文学界の生き字引の一人である、城と九州文学の同人である畑島氏の参加もあり、文学佐賀の乱の話や、県内各同人誌の話も聞け、大変面白かった。
もちろん畑島氏は、生の井上氏を見た人なので、井上光晴についての話もばっちり聞けた。
あとで道中の模様や、写真も掲載したいと思う。
さて、今日の新聞をみると、「演劇王争奪戦 3日スタート」とある、
何のことかというと、佐賀県内で活躍するアマチュア劇団が、観客も審査員に加わりつつ、演劇王を決定するというもの。
佐賀市愛敬町の、STAGEMARO という舞台で、11月3日から、日曜と祝日毎に、午後2時から芝居を行う。
県内8劇団がエントリーをしていて、見事演劇王に輝いた劇団には賞金20万円が贈られるという、素晴らしい企画だ!
(某県内有名文学賞なんて図書券だけ)
お問い合わせは、STAGEMAROへ電話してほしい。
↑Webサイトがあったので、リンクしておきます。
いやあ、演劇は元気があっていいなあ縲懊懊怐B
唐津市民劇「末廬の風神」あす上演
なみログで以前紹介した、唐津市民劇が、明日10月21日(土)に上演される。
場所は唐津市民会館。時間は午後1時と午後6時からの2回。
詳しくは、唐津市民会館へ
■唐津市民会館の案内(唐津市役所ウェブサイト)
場所は唐津市民会館。時間は午後1時と午後6時からの2回。
詳しくは、唐津市民会館へ
■唐津市民会館の案内(唐津市役所ウェブサイト)
福岡を本の街に。
2006年10月6日(金)佐賀新聞朝刊18頁より
おっとっとっと。
オリンピックの次は、逆ブレして、本かよ縲怐B
しかし本のイベントに気付くとは、さすが福岡。うらやましい。
時代がまともな芸術を望んでいるんだと思いますよ。
趣味がら多くの本好きの人を知っていますが、ここ数年で、こと本の中でも小説に対する期待はひしひしと感じる。
いい小説ってなかなか無いものねー。
ちなみにわが読書会で、関心の高かったのは、深沢七郎の楢山節考。それから丸山健二のアフリカの光。古いけど、野呂邦暢もよかった。遠藤周作もずいぶんと議論が沸騰したなあ。
それから、夏目漱石のこころ、も盛り上がった。
話は記事に戻るが、福岡を本の街にということで、10月16日より、『ブックオカ』というのがスタートする。アジアマンスとかあれやこれやとよくやるよなーと思うが。すばらしい。
詳しいことは、
■ブックオカの公式Webサイトへ
おっとっとっと。
オリンピックの次は、逆ブレして、本かよ縲怐B
しかし本のイベントに気付くとは、さすが福岡。うらやましい。
時代がまともな芸術を望んでいるんだと思いますよ。
趣味がら多くの本好きの人を知っていますが、ここ数年で、こと本の中でも小説に対する期待はひしひしと感じる。
いい小説ってなかなか無いものねー。
ちなみにわが読書会で、関心の高かったのは、深沢七郎の楢山節考。それから丸山健二のアフリカの光。古いけど、野呂邦暢もよかった。遠藤周作もずいぶんと議論が沸騰したなあ。
それから、夏目漱石のこころ、も盛り上がった。
話は記事に戻るが、福岡を本の街にということで、10月16日より、『ブックオカ』というのがスタートする。アジアマンスとかあれやこれやとよくやるよなーと思うが。すばらしい。
詳しいことは、
■ブックオカの公式Webサイトへ
紀伊國屋が佐賀初出店!!
2006年9月15日(金)佐賀新聞朝刊9頁より
紀伊國屋書店が、佐賀に初出店する!!
出店場所は、佐賀市兵庫のゆめタウン佐賀内。(現在12月上旬のオープンに向けて着々と準備されている)
県内にはこれまで本格的な書店がなかったため(エスプラッツに喜久屋書店が入ったが撤退・・)、専門書はどこで買えばいいか困り果てていた人も多い。
中には、新聞の広告などを見て、電話で取寄せたり、インターネットでネット通販したりしていたと思うが、それでも、本屋のその地域における存在意義はとてつもなく大きい。
本との出会いは人生のターニングポイントであることもありうる。
とくに若い人には、いろんな本のタイトルを目にしてもらい、その中からワクワクしたり、恐る恐るだったりして、本を手に取る。そんな体験をしてもらいたい。
私自信のエピソードを書くと、佐賀県文学賞という県内の文芸コンテストに、24歳のときに始めて小説を応募した。それがたまたま選は洩れたが、審査委員の人にいい評価をいただいた、「よし。もう少し小説を書いてみよう」と、若かったので単純にそう思った。
そして、佐賀駅の積文館書店に行って、そこの端っこにあった県内出版物コーナーに足を運んだ。その以前からその一角に文芸同人誌があるのは知っていたが、どのような同人雑誌があるのかは具体的には知らなかった。
城、佐賀文学、九州文学などが並んでいた。
そして私は、佐賀文学を手に取り、買って帰った。14号か15号だったと思う。
家に帰って佐賀文学に掲載の小説を読み、そして私はあるひとつの行動に出た。
佐賀文学同人で多久市の人がいたので、その人に思い切って連絡を取ってみようと思い、ハガキを1枚書いて送ったのだ。
早速、佐賀文学のその人から連絡があり、ほどなく私は佐賀文学に所属することになった。
積文館書店での佐賀文学との出会いが、私の拙い文学歴の始まりなのだ。
ほかにも、坂口安吾との出会いも本屋で、坂口安吾は私が初めて古本まで買いあさった作家だ。大学生の頃だったので、「堕落論」というタイトルに惹かれたという単純なものなのだけど。。(苦笑)
紀伊國屋書店が、佐賀に初出店する!!
出店場所は、佐賀市兵庫のゆめタウン佐賀内。(現在12月上旬のオープンに向けて着々と準備されている)
県内にはこれまで本格的な書店がなかったため(エスプラッツに喜久屋書店が入ったが撤退・・)、専門書はどこで買えばいいか困り果てていた人も多い。
中には、新聞の広告などを見て、電話で取寄せたり、インターネットでネット通販したりしていたと思うが、それでも、本屋のその地域における存在意義はとてつもなく大きい。
本との出会いは人生のターニングポイントであることもありうる。
とくに若い人には、いろんな本のタイトルを目にしてもらい、その中からワクワクしたり、恐る恐るだったりして、本を手に取る。そんな体験をしてもらいたい。
私自信のエピソードを書くと、佐賀県文学賞という県内の文芸コンテストに、24歳のときに始めて小説を応募した。それがたまたま選は洩れたが、審査委員の人にいい評価をいただいた、「よし。もう少し小説を書いてみよう」と、若かったので単純にそう思った。
そして、佐賀駅の積文館書店に行って、そこの端っこにあった県内出版物コーナーに足を運んだ。その以前からその一角に文芸同人誌があるのは知っていたが、どのような同人雑誌があるのかは具体的には知らなかった。
城、佐賀文学、九州文学などが並んでいた。
そして私は、佐賀文学を手に取り、買って帰った。14号か15号だったと思う。
家に帰って佐賀文学に掲載の小説を読み、そして私はあるひとつの行動に出た。
佐賀文学同人で多久市の人がいたので、その人に思い切って連絡を取ってみようと思い、ハガキを1枚書いて送ったのだ。
早速、佐賀文学のその人から連絡があり、ほどなく私は佐賀文学に所属することになった。
積文館書店での佐賀文学との出会いが、私の拙い文学歴の始まりなのだ。
ほかにも、坂口安吾との出会いも本屋で、坂口安吾は私が初めて古本まで買いあさった作家だ。大学生の頃だったので、「堕落論」というタイトルに惹かれたという単純なものなのだけど。。(苦笑)
冨田才治 虹の松原一揆を扱った芝居
2006年9月6日(水)佐賀新聞朝刊22頁より
まちから村からという、市民記者?が寄せた記事に、
冨田才治という人を扱った芝居が公演されるという記事がある。
■10月21日 唐津市民会館
タイトル「末盧の風神」
午後1時からと午後6時からの2回公演
唐津の人であれば、知っている人も多いのであろうが、冨田才治というひとは、なんでも虹の松原一揆と呼ばれる百姓一揆を成功させた人物であるという。
ちょっとグーグルで検索してみたら、下のようなサイトが出てきたので紹介する。
ちょいと詳しく読んでみないとわからないので、興味のある人は、リンク先を読んでみてください。
■虹の松原一揆について書かれたサイト
■劇団穴の会(今回なみログで取り上げた劇をやる劇団のようだ)
私自身、少しは佐賀のあれこれを表に出す(もっと知ってもらう)ための活動をしているつもりだが、ほんとうにいろいろあるんだなーという感じがする。
地域の歴史、風土、生活習慣、人物、なにを考え、なにを思い、どんな行動をしたのか、そういうのを後世に伝えるのが、文学であったり芝居であったり、歌であったりするんだろうと思う。
いまは、テレビ全盛時代(そろそろ落ち目?)なので、文化情報の消費も一方的であることを否めないが、ちょうど我々の世代あたりから下は、地域の地に足のついた情報に飢えていると思うのだが、どうだろうか。
上のような情報を知るにつれ、地域のことを知ることは面白いなあと思うのだけれど。
まちから村からという、市民記者?が寄せた記事に、
冨田才治という人を扱った芝居が公演されるという記事がある。
■10月21日 唐津市民会館
タイトル「末盧の風神」
午後1時からと午後6時からの2回公演
唐津の人であれば、知っている人も多いのであろうが、冨田才治というひとは、なんでも虹の松原一揆と呼ばれる百姓一揆を成功させた人物であるという。
ちょっとグーグルで検索してみたら、下のようなサイトが出てきたので紹介する。
ちょいと詳しく読んでみないとわからないので、興味のある人は、リンク先を読んでみてください。
■虹の松原一揆について書かれたサイト
■劇団穴の会(今回なみログで取り上げた劇をやる劇団のようだ)
私自身、少しは佐賀のあれこれを表に出す(もっと知ってもらう)ための活動をしているつもりだが、ほんとうにいろいろあるんだなーという感じがする。
地域の歴史、風土、生活習慣、人物、なにを考え、なにを思い、どんな行動をしたのか、そういうのを後世に伝えるのが、文学であったり芝居であったり、歌であったりするんだろうと思う。
いまは、テレビ全盛時代(そろそろ落ち目?)なので、文化情報の消費も一方的であることを否めないが、ちょうど我々の世代あたりから下は、地域の地に足のついた情報に飢えていると思うのだが、どうだろうか。
上のような情報を知るにつれ、地域のことを知ることは面白いなあと思うのだけれど。
がばいばあちゃんエキストラ募集
2006年8月30日(水)佐賀新聞朝刊19頁より
武雄市の「佐賀のがばいばあちゃん実行委員会」では、来年1月に全国放送される、テレビドラマのエキストラやスタッフを募集しているという記事が載っている。
オーディションは、9月3日(日)で、武雄市文化会館で行なわれる。
詳しくは、武雄市役所Webサイトを。
しかし、武雄はスピードが速いというか、盛り上がってますなー。
佐賀のがばいばあちゃんって、佐賀市の話じゃなかったけ??
佐賀市は何をしとるのかしらん。と思っている佐賀市民も多いのではないか?
まあ、佐賀県が盛り上がればいいのでそういう心配は余計なことだが。
それから、その記事の左ななめ下にも、また武雄市の話題が。
なんでも毎月第四土曜日に、武雄温泉新館を舞台に見立てた「湯のまえステージ」というのがあり、その出演者を募集しているとある。
出演者には、ステージを三十分から一時間を無料で貸し出し、歌や歌以外のパフォーマンスもいいそうだ。
まあ、そんなのがあっているとは知らなかった。
関心がある方は、ぜひ佐賀新聞をご覧あれ。←たまには佐賀新聞の宣伝もちゃんとしないとね!じんわりとはしているつもりだが。
武雄市の「佐賀のがばいばあちゃん実行委員会」では、来年1月に全国放送される、テレビドラマのエキストラやスタッフを募集しているという記事が載っている。
オーディションは、9月3日(日)で、武雄市文化会館で行なわれる。
詳しくは、武雄市役所Webサイトを。
しかし、武雄はスピードが速いというか、盛り上がってますなー。
佐賀のがばいばあちゃんって、佐賀市の話じゃなかったけ??
佐賀市は何をしとるのかしらん。と思っている佐賀市民も多いのではないか?
まあ、佐賀県が盛り上がればいいのでそういう心配は余計なことだが。
それから、その記事の左ななめ下にも、また武雄市の話題が。
なんでも毎月第四土曜日に、武雄温泉新館を舞台に見立てた「湯のまえステージ」というのがあり、その出演者を募集しているとある。
出演者には、ステージを三十分から一時間を無料で貸し出し、歌や歌以外のパフォーマンスもいいそうだ。
まあ、そんなのがあっているとは知らなかった。
関心がある方は、ぜひ佐賀新聞をご覧あれ。←たまには佐賀新聞の宣伝もちゃんとしないとね!じんわりとはしているつもりだが。
多久市在住のファッションデザイナー
2006年8月28日(月)佐賀新聞朝刊22頁より
多久市在住のファッションデザイナー、田代氏のことが載っている。
何でも、9月4日から開かれる、東京コレクション(東コレ)に、自身のブランドを初出品するということ。
ファッションのことはまったく知らないが、地方から出品するのは、とても凄いことだ。
記事によると、田代氏は現在福岡市に、事務所を立ち上げているということなので、多久から福岡まで通っているということか。
高速道路を使えば1時間ちょっとで行くので、多久=福岡は、思ったより早い。
多久市在住といえば、直木賞候補作家の小説家、故滝口康彦氏がいたことを思い出した。
私も多久出身だし頑張ろう。
多久市在住のファッションデザイナー、田代氏のことが載っている。
何でも、9月4日から開かれる、東京コレクション(東コレ)に、自身のブランドを初出品するということ。
ファッションのことはまったく知らないが、地方から出品するのは、とても凄いことだ。
記事によると、田代氏は現在福岡市に、事務所を立ち上げているということなので、多久から福岡まで通っているということか。
高速道路を使えば1時間ちょっとで行くので、多久=福岡は、思ったより早い。
多久市在住といえば、直木賞候補作家の小説家、故滝口康彦氏がいたことを思い出した。
私も多久出身だし頑張ろう。
井上靖の長男が8/5(土)来佐
2006年7月22日(土)佐賀新聞朝刊21頁より
佐賀大文化教育学部同窓会が主催して、
小説家井上靖氏の長男修一氏と、フォトジャーナリスト大塚清吾氏による、文化講演会が開催される。
日時は、8月5日(土)午後2時から。
場所は、佐賀大学講義室。
講演の演題は、それぞれ
井上修一氏が、
「作家井上靖の教育観」
大塚清吾氏が、
「敦煌・シルクロードの開拓者 井上靖先生のこと」
だ。
※本件については、新聞には問い合わせ先電話番号が載っているが、
ここでは載せない。問い合わせは、コメントに書き込むか、メールください。
返信します。
敦煌は、小説は読んでいないが、映画は観た。それも映画館で。
(試写会の券があたってたしか見に行ったような・・)
佐賀大学でもいくつか面白いと思える講演があっているんだなーと思った。
三年くらいまえになるが、長崎在住の芥川賞作家、青来有一氏を呼んで、文学シンポジウムが開かれたときは、思わず見に行った。
蛇足だが、子供の読書離れも歯止めがかかったという記事も載っていた。
佐賀大文化教育学部同窓会が主催して、
小説家井上靖氏の長男修一氏と、フォトジャーナリスト大塚清吾氏による、文化講演会が開催される。
日時は、8月5日(土)午後2時から。
場所は、佐賀大学講義室。
講演の演題は、それぞれ
井上修一氏が、
「作家井上靖の教育観」
大塚清吾氏が、
「敦煌・シルクロードの開拓者 井上靖先生のこと」
だ。
※本件については、新聞には問い合わせ先電話番号が載っているが、
ここでは載せない。問い合わせは、コメントに書き込むか、メールください。
返信します。
敦煌は、小説は読んでいないが、映画は観た。それも映画館で。
(試写会の券があたってたしか見に行ったような・・)
佐賀大学でもいくつか面白いと思える講演があっているんだなーと思った。
三年くらいまえになるが、長崎在住の芥川賞作家、青来有一氏を呼んで、文学シンポジウムが開かれたときは、思わず見に行った。
蛇足だが、子供の読書離れも歯止めがかかったという記事も載っていた。
佐賀県立図書館が不要本を求めてる
2006年7月20日(木)佐賀新聞朝刊25頁より
佐賀新聞の25面の下の方に、佐賀県立図書館が、不要になった本の提供を求める記事が載っている。
なんでも、8月25日から8月27日までの3日間にわたり、提供された本を県立図書館で展示し、ひとり十冊を上限に譲るというもの。
本の提供期間は、8月4日から11日まで。本の分野は問わないが、雑誌、マンガ本、参考書はダメ。
受け付けない。
果たして昨年は何冊集まったかというと、約9000冊も集まった!
本好きの者にとっては、十冊選ぶのも楽しみがあるし、要らない本の処分に困っている人にとっては、これまた捨てるわけにもいかないと思うので、ありがたい企画だ。
いやいや、こんな企画が昨年もあったのかあ。知らなかった。
個人的に本はよく買うほうだが、本屋に並んでいるのは、佐賀県内であれば、まずどの本屋を巡っても似たりよったりの品揃え。面白くない。
だからといって、福岡まで行くこともそうそうないし、ネットでは、ぶらぶら探しができない。(本屋の魅力はこれといってお目当ての本が無くてもぶらぶらと探せるところだ)
いやいや、楽しみだ。忘れずに、8月25日は県立図書館に行こう。昼休みとかに。
さて、本関係の話題では、先日の日曜日は月1回開催している読書会だった。
取り上げた本は、車谷長吉氏の「赤目四十八瀧心中未遂」。久しぶりに読み応え、議論応えのある本だった。
結局わからなかった疑問点で、主人公の生島は、なぜ転落の人生を歩むようになったのか。
彼が持っていた、暗殺の計画書や、匕首は、いったいだれを殺そうとしていたのか。
が、残ったままだ。(正子という三角関係の女性は、別れたあと、自殺したのかどうかというのも疑問に上がった)
ググッてみたけど、目に付くサイトにはこの件については言及されていないような・・・
「赤目・・」についてのコメント歓迎!!
佐賀新聞の25面の下の方に、佐賀県立図書館が、不要になった本の提供を求める記事が載っている。
なんでも、8月25日から8月27日までの3日間にわたり、提供された本を県立図書館で展示し、ひとり十冊を上限に譲るというもの。
本の提供期間は、8月4日から11日まで。本の分野は問わないが、雑誌、マンガ本、参考書はダメ。
受け付けない。
果たして昨年は何冊集まったかというと、約9000冊も集まった!
本好きの者にとっては、十冊選ぶのも楽しみがあるし、要らない本の処分に困っている人にとっては、これまた捨てるわけにもいかないと思うので、ありがたい企画だ。
いやいや、こんな企画が昨年もあったのかあ。知らなかった。
個人的に本はよく買うほうだが、本屋に並んでいるのは、佐賀県内であれば、まずどの本屋を巡っても似たりよったりの品揃え。面白くない。
だからといって、福岡まで行くこともそうそうないし、ネットでは、ぶらぶら探しができない。(本屋の魅力はこれといってお目当ての本が無くてもぶらぶらと探せるところだ)
いやいや、楽しみだ。忘れずに、8月25日は県立図書館に行こう。昼休みとかに。
さて、本関係の話題では、先日の日曜日は月1回開催している読書会だった。
取り上げた本は、車谷長吉氏の「赤目四十八瀧心中未遂」。久しぶりに読み応え、議論応えのある本だった。
結局わからなかった疑問点で、主人公の生島は、なぜ転落の人生を歩むようになったのか。
彼が持っていた、暗殺の計画書や、匕首は、いったいだれを殺そうとしていたのか。
が、残ったままだ。(正子という三角関係の女性は、別れたあと、自殺したのかどうかというのも疑問に上がった)
ググッてみたけど、目に付くサイトにはこの件については言及されていないような・・・
「赤目・・」についてのコメント歓迎!!
角(かっ)くんちゃん演劇に
2006年5月27日(土)佐賀新聞朝刊18頁より
今朝の佐賀新聞の18面、
カックンチャン、劇に
という見出しを見て、「へえ、ほんとうにやるんだぁ」という感慨を持った。
彫刻を手がける光山氏が、小城市で開かれる「天山アートフェスタ」のイベントで、かっくんちゃんを題材にした芝居をやるという。
ではかっくんちゃん、とは誰か。新聞記事によれば、昭和の伝説の門付と肩書きが書いてある。かっくんちゃんという人は、もうずいぶん年配の人でないと知らないと思われるが、家々の軒先を回り、1本三味線を弾き歩いていた人。(たしか?)
いろいろと伝説を持っている人で、有名な三味線奏者と腕比べをして勝ったとか、そういうのがあったと思う。
そのかっくんちゃん、を劇に。
やるなー、光山氏。
光山氏とは、3、4年前に何回か面識がある、天山アートフェスタにも深く関わっている、ハーベスト21という芸術集団の一人で(いまもだと思うが)、記事にも書いてあるとおり、旧有明町から依頼されて、かっくんちゃんの彫像を作ったことがある人だ。
そういえば、飲んでいる席でも、かっくんちゃんの話をしていたのを思い出す。小説に書くようなことをいっていたと記憶しているが、芝居にする話だったか。。
今日、天山アートフェスタで初公演とある。どんな芝居か楽しみだ。
ちなみに天山アートフェスタは、小城市の小柳酒造高砂本蔵で開かれている。天気がパッとしないが、出かけてみてはどうか。
今朝の佐賀新聞の18面、
カックンチャン、劇に
という見出しを見て、「へえ、ほんとうにやるんだぁ」という感慨を持った。
彫刻を手がける光山氏が、小城市で開かれる「天山アートフェスタ」のイベントで、かっくんちゃんを題材にした芝居をやるという。
ではかっくんちゃん、とは誰か。新聞記事によれば、昭和の伝説の門付と肩書きが書いてある。かっくんちゃんという人は、もうずいぶん年配の人でないと知らないと思われるが、家々の軒先を回り、1本三味線を弾き歩いていた人。(たしか?)
いろいろと伝説を持っている人で、有名な三味線奏者と腕比べをして勝ったとか、そういうのがあったと思う。
そのかっくんちゃん、を劇に。
やるなー、光山氏。
光山氏とは、3、4年前に何回か面識がある、天山アートフェスタにも深く関わっている、ハーベスト21という芸術集団の一人で(いまもだと思うが)、記事にも書いてあるとおり、旧有明町から依頼されて、かっくんちゃんの彫像を作ったことがある人だ。
そういえば、飲んでいる席でも、かっくんちゃんの話をしていたのを思い出す。小説に書くようなことをいっていたと記憶しているが、芝居にする話だったか。。
今日、天山アートフェスタで初公演とある。どんな芝居か楽しみだ。
ちなみに天山アートフェスタは、小城市の小柳酒造高砂本蔵で開かれている。天気がパッとしないが、出かけてみてはどうか。
佐賀市で演劇大作戦
2006年5月26日(土)佐賀新聞朝刊26頁より
佐賀県内で活躍する若手アマチュア劇団の10団体が一同に集まり公演を行なう、
「レッツSAGA演劇大作戦-MISHMASH(ミシュマシュ)」
が5月27日、28日の両日、佐賀市中心市街地のエスプラッツホールで開かれる。
出演団体は、10団体ということで、
佐賀県内のアマチュア劇団の数も結構あるもんだなーという率直な感想だ。
ちなみに、劇団名も紹介しておくと、
芝居屋Rose、ANGEL WING、自主製作映像集団DANGO茶屋、team eighteen、劇団Ziシアター、(以上27日)
劇団ヤマト、劇団PETER PAN、斜陽、劇団COLORS、万能グローブパタゴスダイナモス、(以上28日)
開演は両日ともに午後2時から。料金は1日1000円。(当日券は1000円高)
問い合わせは、Ziシアターまで。
※なみログもまあまあアクセスしてもらっているので、来場者数アップに貢献できればいいが・・
佐賀県内で活躍する若手アマチュア劇団の10団体が一同に集まり公演を行なう、
「レッツSAGA演劇大作戦-MISHMASH(ミシュマシュ)」
が5月27日、28日の両日、佐賀市中心市街地のエスプラッツホールで開かれる。
出演団体は、10団体ということで、
佐賀県内のアマチュア劇団の数も結構あるもんだなーという率直な感想だ。
ちなみに、劇団名も紹介しておくと、
芝居屋Rose、ANGEL WING、自主製作映像集団DANGO茶屋、team eighteen、劇団Ziシアター、(以上27日)
劇団ヤマト、劇団PETER PAN、斜陽、劇団COLORS、万能グローブパタゴスダイナモス、(以上28日)
開演は両日ともに午後2時から。料金は1日1000円。(当日券は1000円高)
問い合わせは、Ziシアターまで。
※なみログもまあまあアクセスしてもらっているので、来場者数アップに貢献できればいいが・・
がばいばあちゃん世界へ
2006年5月18日(木)佐賀新聞朝刊1頁より
全国公開された映画、「佐賀のがばいばあちゃん」が人気を呼んでいる。
先日佐賀ローカル局のテレビニュースで、ゴールデンウィークの佐賀県内の映画館の様子がレポートされていたが、昨年の来場者数を大きく上回り、なかでも、中高年齢層の来場が目立ったとあった。
数年ぶりに映画を見に来たという人も多く、目当ては、佐賀のがばいばあちゃん。孫に見せたいと、孫といっしょに来たという人も多かったようだ。
そんながばいばあちゃんが、台湾で今秋公開されるという記事が佐賀新聞の1面に載っている。
台湾公開に先立ち、6月17日からはじまる上海映画祭にも上映されるとあり、佐賀から世界へと公開されるようだ。
島田洋七氏オフィシャルサイト
全国公開された映画、「佐賀のがばいばあちゃん」が人気を呼んでいる。
先日佐賀ローカル局のテレビニュースで、ゴールデンウィークの佐賀県内の映画館の様子がレポートされていたが、昨年の来場者数を大きく上回り、なかでも、中高年齢層の来場が目立ったとあった。
数年ぶりに映画を見に来たという人も多く、目当ては、佐賀のがばいばあちゃん。孫に見せたいと、孫といっしょに来たという人も多かったようだ。
そんながばいばあちゃんが、台湾で今秋公開されるという記事が佐賀新聞の1面に載っている。
台湾公開に先立ち、6月17日からはじまる上海映画祭にも上映されるとあり、佐賀から世界へと公開されるようだ。
島田洋七氏オフィシャルサイト
九州さが大衆文学賞大賞は井上さんに
2006年3月20日(月)佐賀新聞朝刊1頁より
今日の佐賀新聞1面に、
九州さが大衆文学賞の選考結果が発表されている。
大賞は川崎市在住の井上氏が受賞した。
受賞作は、『華吉屋縁起』というタイトルで、徳川吉宗時代の長崎を舞台にした内容で、隠れキリシタンの話なども織り交ぜられているとある。
16面のあらすじを読むと、将軍吉宗に献上されるために長崎港へ陸揚げされた象の話を縦糸にかかれているようだ。
さて、先日なみログで書いた、文学仲間の受賞は一体???
というか、県内の優秀作品には奨励賞というのが与えられるようになっていて、最終選考に残った6編の中では、佐賀県在住の作品はひとつしかなく、おのずと大賞と佳作でなければ、奨励賞ということだったようだ。
ということで、佐賀市在住の西村氏が見事奨励賞だった。
パチパチパチ。
大賞だったら一番よかったと思うのだが、奨励賞でも十分凄い。
受賞作は、『海峡に陽は昇る』で朝鮮通信史のことが書かれており、恋愛物語だそうだ。ほほう。
いつか読む機会があると思うのでたのしみにしておこう。
九州さが大衆文学賞は、あまり身近に感じていなかった賞だが、いざ知り合いが奨励賞であれ、受賞となると急に親近感を覚えてしまった。間違っても私が応募することは無いが、西村氏の知り合いのなかには、来年は自分も、と急に鼻息を荒げて書き始めた人もいるかも知れない。
そうやって、段々と佐賀県在住の小説家のレベルがあがれば、いいと思う。
今日の佐賀新聞1面に、
九州さが大衆文学賞の選考結果が発表されている。
大賞は川崎市在住の井上氏が受賞した。
受賞作は、『華吉屋縁起』というタイトルで、徳川吉宗時代の長崎を舞台にした内容で、隠れキリシタンの話なども織り交ぜられているとある。
16面のあらすじを読むと、将軍吉宗に献上されるために長崎港へ陸揚げされた象の話を縦糸にかかれているようだ。
さて、先日なみログで書いた、文学仲間の受賞は一体???
というか、県内の優秀作品には奨励賞というのが与えられるようになっていて、最終選考に残った6編の中では、佐賀県在住の作品はひとつしかなく、おのずと大賞と佳作でなければ、奨励賞ということだったようだ。
ということで、佐賀市在住の西村氏が見事奨励賞だった。
パチパチパチ。
大賞だったら一番よかったと思うのだが、奨励賞でも十分凄い。
受賞作は、『海峡に陽は昇る』で朝鮮通信史のことが書かれており、恋愛物語だそうだ。ほほう。
いつか読む機会があると思うのでたのしみにしておこう。
九州さが大衆文学賞は、あまり身近に感じていなかった賞だが、いざ知り合いが奨励賞であれ、受賞となると急に親近感を覚えてしまった。間違っても私が応募することは無いが、西村氏の知り合いのなかには、来年は自分も、と急に鼻息を荒げて書き始めた人もいるかも知れない。
そうやって、段々と佐賀県在住の小説家のレベルがあがれば、いいと思う。