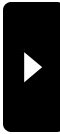スポンサーサイト
SOHO-SAGA
2006年5月23日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
日本SOHO協会理事の飯盛氏(佐賀市)が、SOHO事業者の育成などを目指す、「SOHO-SAGA」を設立したとある。
「SOHO-SAGA」Webサイト
SOHOについては、これまでなみログでも何度か話題にしてきた。
SOHOスピリッツ
なかでもSOHOというのが、単なるITを使った事業形態であるというだけではなく、SOHOというライフスタイルや志を大切にすることが大事ではないかということを考えていた。
SOHO-SAGAの活動の中心は、アウトソーシングをしたい企業とSOHOの仲介役ということで、データ入力やウェブサイトの制作などが中心になるということだ。
それから、SOHO同士の連携強化も目的のひとつだそうだ。
Webに関していえば、県内企業のWebサイトも過去に作られたものはいたしかたないサイトもあるが、ここ1年あまりで開設またはリニューアルされたサイトは、段々とレベルが上がってきた。
ようやくWebサイトが、単なる看板ではなくて、機能しなければならないという認識の元で作られはじめてきたと思う。
これまでは、Webサイトはだれでも簡単に作れるという話があまりにも先行しすぎて、実際に作れるのは作れるから、それで作って満足というところで終っていることが多い。
いまさら私が口に出してまでいうことではないが、だれが見るのか、何の目的で作るのか、目的は達成されたか、という検証をすると、まだまだ意図されていないサイトもあるようだ。
SOHOの方もSOHOではない制作会社のスタッフも、Webに関わるすべての作業は、目的を明確にすることと、すべての作業は目的を達成するための作業の集合でなければならないということを、忘れることなく、佐賀のWebサービスの発展のためにいろいろと取り組んでいきたいものだ。
日本SOHO協会理事の飯盛氏(佐賀市)が、SOHO事業者の育成などを目指す、「SOHO-SAGA」を設立したとある。
「SOHO-SAGA」Webサイト
SOHOについては、これまでなみログでも何度か話題にしてきた。
SOHOスピリッツ
なかでもSOHOというのが、単なるITを使った事業形態であるというだけではなく、SOHOというライフスタイルや志を大切にすることが大事ではないかということを考えていた。
SOHO-SAGAの活動の中心は、アウトソーシングをしたい企業とSOHOの仲介役ということで、データ入力やウェブサイトの制作などが中心になるということだ。
それから、SOHO同士の連携強化も目的のひとつだそうだ。
Webに関していえば、県内企業のWebサイトも過去に作られたものはいたしかたないサイトもあるが、ここ1年あまりで開設またはリニューアルされたサイトは、段々とレベルが上がってきた。
ようやくWebサイトが、単なる看板ではなくて、機能しなければならないという認識の元で作られはじめてきたと思う。
これまでは、Webサイトはだれでも簡単に作れるという話があまりにも先行しすぎて、実際に作れるのは作れるから、それで作って満足というところで終っていることが多い。
いまさら私が口に出してまでいうことではないが、だれが見るのか、何の目的で作るのか、目的は達成されたか、という検証をすると、まだまだ意図されていないサイトもあるようだ。
SOHOの方もSOHOではない制作会社のスタッフも、Webに関わるすべての作業は、目的を明確にすることと、すべての作業は目的を達成するための作業の集合でなければならないということを、忘れることなく、佐賀のWebサービスの発展のためにいろいろと取り組んでいきたいものだ。
自転車県 佐賀
2006年5月19日(金)佐賀新聞朝刊15頁より
昨日?おととい?から風まじりの雨。
梅雨への一歩手前といった天気で、湿度も高いのか、じめじめとしている。
朝から、営業車に乗り込み、福岡県篠栗町へ。
まあ、仕事のことは置いておいて。。
佐賀新聞のふくおかスポットというコーナーの天神通信というコラム。
加速する一極集中
という見出しで書かれている。
ここ数日間でおきた、九州地方銀行の営業提携のニュースを受けて、今後の九州金融界の動きが活発化するのではという主旨から、福岡一極集中がますます強まる中、佐賀はどう向き合うべきか、という課題をあげてある。
ますます一極集中は進むとは思うが、その反面、通勤圏の広がりから佐賀駅から博多駅へ通うビジネスマンの数も増えている。
そういう私も5年ほどまえは、一年間、多久の実家から博多駅まで通勤していた一人だ。
多久から自家用車で佐賀駅まで、佐賀駅から特急に乗って博多駅まで。土曜日以外の平日は毎日。
前にも書いたかも知れないが、佐賀に住んでいたある人が、子供を育てるのには佐賀は良かったといっていた。どんなところがよかったかというと、その人の子供は音楽をやっていたようで、音楽の発表会などが、新聞に取り上げられたりすることも多かったといわれた。そのことが子供の自信につながったようで、それが良かったといっていた。
競争が無いので、すぐに目立つということをいっているのではなく、地域がこじんまりとしているので、子供ひとりひとりにスポットがあたることも多い。
そうはいえ、影響力のあるメディアは数が限られていて、もっと才能のある若者にもスポットをあててほしいというような意見はよく耳にするので、それはメディアへの期待として書いておこう。
さて、読者投稿欄の、「わたし 新・田舎主義」という見出しの中に、佐賀県は自転車県さがへ回帰してはどうだろうか、という意見があった。
佐賀市内も自転車は多い。自転車屋も多い。佐賀は自転車の利用者が多いというのはみんなが抱いている感想ではないだろうか。
しかしそれでも少しは減ってきているのかな??
中途半端に自転車県としてアピールしようとするのではなく、思い切って、世界一の自転車先進県というくらいのビジョンを持って取り組めば、案外面白いのではないかと思う。
けれど、自転車も危ない乗り方をしている人もいるので、安全対策も必要にはなるが。。
昨日?おととい?から風まじりの雨。
梅雨への一歩手前といった天気で、湿度も高いのか、じめじめとしている。
朝から、営業車に乗り込み、福岡県篠栗町へ。
まあ、仕事のことは置いておいて。。
佐賀新聞のふくおかスポットというコーナーの天神通信というコラム。
加速する一極集中
という見出しで書かれている。
ここ数日間でおきた、九州地方銀行の営業提携のニュースを受けて、今後の九州金融界の動きが活発化するのではという主旨から、福岡一極集中がますます強まる中、佐賀はどう向き合うべきか、という課題をあげてある。
ますます一極集中は進むとは思うが、その反面、通勤圏の広がりから佐賀駅から博多駅へ通うビジネスマンの数も増えている。
そういう私も5年ほどまえは、一年間、多久の実家から博多駅まで通勤していた一人だ。
多久から自家用車で佐賀駅まで、佐賀駅から特急に乗って博多駅まで。土曜日以外の平日は毎日。
前にも書いたかも知れないが、佐賀に住んでいたある人が、子供を育てるのには佐賀は良かったといっていた。どんなところがよかったかというと、その人の子供は音楽をやっていたようで、音楽の発表会などが、新聞に取り上げられたりすることも多かったといわれた。そのことが子供の自信につながったようで、それが良かったといっていた。
競争が無いので、すぐに目立つということをいっているのではなく、地域がこじんまりとしているので、子供ひとりひとりにスポットがあたることも多い。
そうはいえ、影響力のあるメディアは数が限られていて、もっと才能のある若者にもスポットをあててほしいというような意見はよく耳にするので、それはメディアへの期待として書いておこう。
さて、読者投稿欄の、「わたし 新・田舎主義」という見出しの中に、佐賀県は自転車県さがへ回帰してはどうだろうか、という意見があった。
佐賀市内も自転車は多い。自転車屋も多い。佐賀は自転車の利用者が多いというのはみんなが抱いている感想ではないだろうか。
しかしそれでも少しは減ってきているのかな??
中途半端に自転車県としてアピールしようとするのではなく、思い切って、世界一の自転車先進県というくらいのビジョンを持って取り組めば、案外面白いのではないかと思う。
けれど、自転車も危ない乗り方をしている人もいるので、安全対策も必要にはなるが。。
がばい佐賀 佐賀弁CD全国発売へ
2006年4月23日(日)佐賀新聞朝刊26頁より
佐賀 ×○ (さが ばってん、まる)さんのブログで書いてあった、佐賀弁CD「がばい佐賀」。
昨日アパートで佐賀市のケーブルテレビ、ぶんぶんテレビにチャンネルを合わせたら、「がばい佐賀」の歌を歌っているヒーマン氏(佐賀で活躍するタレント)が出演して、「がばい佐賀」全国発売のPRをしていた。
さらに、日曜日、今朝の新聞を見ていたら、またまた笑顔のヒーマン氏の写真。
記事によると、全国発売は、東京の大手レコード会社徳間ジャパンコミュニケーションズが、佐賀で自主制作されたCDを全国発売するということになったということ。曲の完成度が高いというのと、方言ブームが追い風にあるというのも、全国発売を決めた理由のようだ。
CDについで、佐賀産和牛、佐賀の野菜などを使った「がばい佐賀弁」なる弁当も作って、佐賀駅とか、佐賀空港や、羽田空港で売るのはどうか。←もうあるのかなあ。
大ヒットすることが楽しみだ。
佐賀 ×○ (さが ばってん、まる)さんのブログで書いてあった、佐賀弁CD「がばい佐賀」。
昨日アパートで佐賀市のケーブルテレビ、ぶんぶんテレビにチャンネルを合わせたら、「がばい佐賀」の歌を歌っているヒーマン氏(佐賀で活躍するタレント)が出演して、「がばい佐賀」全国発売のPRをしていた。
さらに、日曜日、今朝の新聞を見ていたら、またまた笑顔のヒーマン氏の写真。
記事によると、全国発売は、東京の大手レコード会社徳間ジャパンコミュニケーションズが、佐賀で自主制作されたCDを全国発売するということになったということ。曲の完成度が高いというのと、方言ブームが追い風にあるというのも、全国発売を決めた理由のようだ。
CDについで、佐賀産和牛、佐賀の野菜などを使った「がばい佐賀弁」なる弁当も作って、佐賀駅とか、佐賀空港や、羽田空港で売るのはどうか。←もうあるのかなあ。
大ヒットすることが楽しみだ。
ぶらぶらと疲れない町づくり
2006年4月19日(水)佐賀新聞朝刊26頁より
「バタぐる」った年度末から年度始めもようやく落ち着いてきた。
のでなみログも少し頻度を上げて書かなくてはと。
今朝の新聞26面には、新田舎主義という年次企画に、福岡の地域振興研究所代表取締役の須川氏の論評が掲載してある。
要約すると、町づくりは一過性のイベントで終らないようにして、住民参加型で取り組むのが基本とあり、ただその町づくりの担い手である人材育成の仕掛けも持ち合わせていなければならないと説明する。
佐賀市中心商店街で三年前から行なわれている、まち音という音楽イベントを良い取り組みと取り上げ、能書きより行動していることを評価してある。
記事を読んでいて思ったのは、そこにも書かれているし、以前もそういうことを言及していた人がいたが、町づくり=イベント一辺倒、だけでは疲れはしないか、ということだ。
市民活動ブームは少し落ち着いてきたようだが、市民活動そのものが、軽い躁状態の連続ではないかと心配したくなるような、イベント連続型も多い。
イベントで盛り上げ続けなくてはならないというほとんど脅迫観念に近いものではないか、と自称文学系マーケッターとしては思ったりしていたのだが、まさにそのことを指摘する声が聞かれてきたので、少し冷静になれてよかったと思ったりしていた。
個人的にイベントが疲れるからそう感じるのかも知れないが、みんな元気だなあ、と思うときがある。
元気にしていないと、町づくりが達成しないという町も、なんだかなと思うので、
少しは冷静に、落ち着いて町づくりを考えるのもいいのでは、と思う。まあ、疲れるイベントについていけない人はそもそも静観していると思うので、心配することもないだろうが。
ところで、最近ぶらぶらと町を歩く人が減ったと感じるのは私だけではないだろう。この議論も数十年されているかもしれないが、改めて問い直すと、イベントがあってもなくても、人が町を安心してぶらぶらできる町づくりが理想ではないだろうか。
単にぶらぶらだけだと、危ないので、『「安心して」ぶらぶら』いうのがキーワードにはなる。
「バタぐる」った年度末から年度始めもようやく落ち着いてきた。
のでなみログも少し頻度を上げて書かなくてはと。
今朝の新聞26面には、新田舎主義という年次企画に、福岡の地域振興研究所代表取締役の須川氏の論評が掲載してある。
要約すると、町づくりは一過性のイベントで終らないようにして、住民参加型で取り組むのが基本とあり、ただその町づくりの担い手である人材育成の仕掛けも持ち合わせていなければならないと説明する。
佐賀市中心商店街で三年前から行なわれている、まち音という音楽イベントを良い取り組みと取り上げ、能書きより行動していることを評価してある。
記事を読んでいて思ったのは、そこにも書かれているし、以前もそういうことを言及していた人がいたが、町づくり=イベント一辺倒、だけでは疲れはしないか、ということだ。
市民活動ブームは少し落ち着いてきたようだが、市民活動そのものが、軽い躁状態の連続ではないかと心配したくなるような、イベント連続型も多い。
イベントで盛り上げ続けなくてはならないというほとんど脅迫観念に近いものではないか、と自称文学系マーケッターとしては思ったりしていたのだが、まさにそのことを指摘する声が聞かれてきたので、少し冷静になれてよかったと思ったりしていた。
個人的にイベントが疲れるからそう感じるのかも知れないが、みんな元気だなあ、と思うときがある。
元気にしていないと、町づくりが達成しないという町も、なんだかなと思うので、
少しは冷静に、落ち着いて町づくりを考えるのもいいのでは、と思う。まあ、疲れるイベントについていけない人はそもそも静観していると思うので、心配することもないだろうが。
ところで、最近ぶらぶらと町を歩く人が減ったと感じるのは私だけではないだろう。この議論も数十年されているかもしれないが、改めて問い直すと、イベントがあってもなくても、人が町を安心してぶらぶらできる町づくりが理想ではないだろうか。
単にぶらぶらだけだと、危ないので、『「安心して」ぶらぶら』いうのがキーワードにはなる。
イノシシ猟特区
2006年3月30日(木)佐賀新聞朝刊30頁より
3月も明日で終り。年度末でバタバタ。今月は特に忙しかった。
ありがたい話で、県内を中心にWebの仕事をしているのだが、バタグるった。
(↑バタグるは方言か?バタバタすると狂うがひとつになり省略されて、バタグる?)
佐賀県が国に申請していた「イノシシわな猟免許特区」が3月31日付けで認定されることが決まったようだ。
これまでは、網・わな猟として免許取得がセットだったが、わな猟だけでも免許が取得できるようにするということで、わな猟取得者を増やし、イノシシ対策を行なうことが目的。今夏からの試験で適用するとある。
新聞によると、県内には、イノシシ猟の免許を網・わな猟の免許取得者が870人いるということだが、半数は60歳以上ということで高齢化している。
それをなんとか若い人にも、という目的もあるようだ。
網・わな猟の免許取得者って、870人もいるんだ。
今回の特区は、すでに長崎、大分など5県が認定されていて、佐賀、宮崎、鹿児島が認定されるとある。
イノシシの被害金額が県内だけでも3億円(2004年)あるというから、深刻な状況だ。
山陰中央新報の関連記事をみる
3月も明日で終り。年度末でバタバタ。今月は特に忙しかった。
ありがたい話で、県内を中心にWebの仕事をしているのだが、バタグるった。
(↑バタグるは方言か?バタバタすると狂うがひとつになり省略されて、バタグる?)
佐賀県が国に申請していた「イノシシわな猟免許特区」が3月31日付けで認定されることが決まったようだ。
これまでは、網・わな猟として免許取得がセットだったが、わな猟だけでも免許が取得できるようにするということで、わな猟取得者を増やし、イノシシ対策を行なうことが目的。今夏からの試験で適用するとある。
新聞によると、県内には、イノシシ猟の免許を網・わな猟の免許取得者が870人いるということだが、半数は60歳以上ということで高齢化している。
それをなんとか若い人にも、という目的もあるようだ。
網・わな猟の免許取得者って、870人もいるんだ。
今回の特区は、すでに長崎、大分など5県が認定されていて、佐賀、宮崎、鹿児島が認定されるとある。
イノシシの被害金額が県内だけでも3億円(2004年)あるというから、深刻な状況だ。
山陰中央新報の関連記事をみる
まちづくりは教育から。
2006年3月26日(日)佐賀新聞朝刊1頁より
以前から議論になっている佐賀県立病院好生館の移転問題。
今日の佐賀新聞一面に、佐賀市嘉瀬地区へ移転するということで、知事が方針を固めたとある。
この問題では、佐賀駅西の「どんどんどんの森」が選定されていたが、佐賀市の市有地譲渡拒否があり、一時候補地選定が頓挫していた。
とりあえずこれでひと段落といったところだろうか。
それから、2面、3面には、「まちづくりシンポin多久」の模様が掲載されている。
先日実家に帰ったときに最近の多久の小学生のことを聞いたら、論語を学んでいるという話があった。
へえ縲怐Aと思っていたのだが、シンポジウムの発言のなかにも、多久の小学生が論語を100くらいは覚えているという発言がでていて、本当の話だったんだ、と感心した。
私も多久出身だが、論語を覚えることなんてなかったので、ずいぶんと変わったものだな縲怩ニ思う。細かくいうと、聖廟のある地区は多久町というところで、私は北多久町の北部小学校だったので、聖廟との係わり合いも、小学生のころはほとんど理解していなかったといっていい。
聖廟のことや孔子のことを先生も教えてくれたと思うのだが、ほとんど覚えていない。ほかの同級生もだいたいそんな感じではないだろうか。
別に論語を暗誦できたからといってすぐに何かの役に立つわけではないだろうが、学ぶこと、勉強するこへの抵抗がなくなるだろう。
学ぶこと、勉強への抵抗をなくすというのは非常に大事なことだと思う。
野口悠紀雄氏の「超」勉強法という本だったか、パソコンアレルギーは、文字を早く打てるようにすることで克服できるとあったが、これは私がパソコンを始めた頃に実践した手法で、いまではWebプロデューサーになっているのだから、成功した方法だ。
いまでこそたまにはパソコンの使い方を教える側になるときもあるのだが、8年前、会社に入る前まではワープロのキーボードをちょっと触ったことがあるくらいで、パソコンはまったく知らなかった。
会社に入って何をしたかというと、定時が終わるととにかく文字打ちだけを徹底してやった。ちょうど手書きの小説の原稿があったので、これ幸いとばかりに練習のために、手書き原稿をデータ化していった。最初はぽつぽつと、キーボードを叩いていたが、不思議なもので打ち方が早くなり、そのうちブラインドタッチもできるようになった。1ヶ月もかかっただろうか。おかげで文字打ちの仕事から順次するようになり、HTML組んだり、イラストレーターというソフトやフォトショップというソフトも少しは扱えるようになった。
なんでも基礎なんだなあ、というのは経験値としてある。
で、まちづくりのことに強引に結びつけると、まちづくりは結局人がやることなので、人づくりということで、人づくりとはとどのつまり、教育ではないかと思うのだ。
というかみんもそう思っているだろうから、あらためて言うまでもないことだろう。
イギリスのブレアではないが、大事なのは、教育、教育、教育だ。
以前から議論になっている佐賀県立病院好生館の移転問題。
今日の佐賀新聞一面に、佐賀市嘉瀬地区へ移転するということで、知事が方針を固めたとある。
この問題では、佐賀駅西の「どんどんどんの森」が選定されていたが、佐賀市の市有地譲渡拒否があり、一時候補地選定が頓挫していた。
とりあえずこれでひと段落といったところだろうか。
それから、2面、3面には、「まちづくりシンポin多久」の模様が掲載されている。
先日実家に帰ったときに最近の多久の小学生のことを聞いたら、論語を学んでいるという話があった。
へえ縲怐Aと思っていたのだが、シンポジウムの発言のなかにも、多久の小学生が論語を100くらいは覚えているという発言がでていて、本当の話だったんだ、と感心した。
私も多久出身だが、論語を覚えることなんてなかったので、ずいぶんと変わったものだな縲怩ニ思う。細かくいうと、聖廟のある地区は多久町というところで、私は北多久町の北部小学校だったので、聖廟との係わり合いも、小学生のころはほとんど理解していなかったといっていい。
聖廟のことや孔子のことを先生も教えてくれたと思うのだが、ほとんど覚えていない。ほかの同級生もだいたいそんな感じではないだろうか。
別に論語を暗誦できたからといってすぐに何かの役に立つわけではないだろうが、学ぶこと、勉強するこへの抵抗がなくなるだろう。
学ぶこと、勉強への抵抗をなくすというのは非常に大事なことだと思う。
野口悠紀雄氏の「超」勉強法という本だったか、パソコンアレルギーは、文字を早く打てるようにすることで克服できるとあったが、これは私がパソコンを始めた頃に実践した手法で、いまではWebプロデューサーになっているのだから、成功した方法だ。
いまでこそたまにはパソコンの使い方を教える側になるときもあるのだが、8年前、会社に入る前まではワープロのキーボードをちょっと触ったことがあるくらいで、パソコンはまったく知らなかった。
会社に入って何をしたかというと、定時が終わるととにかく文字打ちだけを徹底してやった。ちょうど手書きの小説の原稿があったので、これ幸いとばかりに練習のために、手書き原稿をデータ化していった。最初はぽつぽつと、キーボードを叩いていたが、不思議なもので打ち方が早くなり、そのうちブラインドタッチもできるようになった。1ヶ月もかかっただろうか。おかげで文字打ちの仕事から順次するようになり、HTML組んだり、イラストレーターというソフトやフォトショップというソフトも少しは扱えるようになった。
なんでも基礎なんだなあ、というのは経験値としてある。
で、まちづくりのことに強引に結びつけると、まちづくりは結局人がやることなので、人づくりということで、人づくりとはとどのつまり、教育ではないかと思うのだ。
というかみんもそう思っているだろうから、あらためて言うまでもないことだろう。
イギリスのブレアではないが、大事なのは、教育、教育、教育だ。
佐賀県から村が消える
2006年3月14日(火)佐賀新聞朝刊27頁より
佐賀県神埼郡脊振村。
3月20日をもって、神埼市となり、県内の自治体としての村がこれでなくなるという。
そうかあ。
多久市生まれなので村が無くなることに感傷を抱いても仕方がないかもしれないが、無くなったものを元に戻すのは難しいことを考えると、なにかうら寂しいものが残る。地区名としては、村が残るんだろうけど。。
話は突然ずれるが、
先日からなみログでも少しずつ文学について書いたりしているが、三年位前に、同人雑誌の行方というテーマで、座談会を開いたことを思い出す。
同人雑誌に与えられた使命とか、期待とかいう青臭いような、まっすぐな論議は抜きにしても、同人誌の役割として、特に地方の同人誌がやったほうがいい取り組みに、
その地域に生きた人たちの生活やら風土やらを小説という形にして残す
ということがあるように思う。
とくにこうもあれやこれやの時勢が速いと、無くなっていくものをどれだけ捕まえることができるのだろうか、などと思ってしまうのだ。
いらぬ心配かも知れないが。
と思ったりしていたら、昭和三十年代の佐賀を面白く描き残した、佐賀のがばいばあちゃんの映画が完成したという記事があった。
13日に島田洋七氏原作の映画佐賀のがばいばあちゃんの完成試写会が佐賀市文化会館であり、いよいよ来月22日から、九州では先行上映が始まるようだ。
佐賀県神埼郡脊振村。
3月20日をもって、神埼市となり、県内の自治体としての村がこれでなくなるという。
そうかあ。
多久市生まれなので村が無くなることに感傷を抱いても仕方がないかもしれないが、無くなったものを元に戻すのは難しいことを考えると、なにかうら寂しいものが残る。地区名としては、村が残るんだろうけど。。
話は突然ずれるが、
先日からなみログでも少しずつ文学について書いたりしているが、三年位前に、同人雑誌の行方というテーマで、座談会を開いたことを思い出す。
同人雑誌に与えられた使命とか、期待とかいう青臭いような、まっすぐな論議は抜きにしても、同人誌の役割として、特に地方の同人誌がやったほうがいい取り組みに、
その地域に生きた人たちの生活やら風土やらを小説という形にして残す
ということがあるように思う。
とくにこうもあれやこれやの時勢が速いと、無くなっていくものをどれだけ捕まえることができるのだろうか、などと思ってしまうのだ。
いらぬ心配かも知れないが。
と思ったりしていたら、昭和三十年代の佐賀を面白く描き残した、佐賀のがばいばあちゃんの映画が完成したという記事があった。
13日に島田洋七氏原作の映画佐賀のがばいばあちゃんの完成試写会が佐賀市文化会館であり、いよいよ来月22日から、九州では先行上映が始まるようだ。
北山少年自然の家
2006年3月8日(水)佐賀新聞朝刊23頁より
昨日は佐賀県貿易協会のセミナーに講師に呼ばれ、Webサイトの活用についていろいろと話をさせてもらった。
セミナーでは、時間の半分をログ解析とブログの話にあて、いかに運営が大切かということと、ブログを活用することのメリットを話した。
そういう自分のブログがなかなか更新されていないというのは、医者の不養生そのものなのだが・・(苦笑)
一昨日の3月6日(月)は、「福岡・佐賀経済フォーラム」と題して開催された経済交流会に参加した。基調講演として、佐賀市富士町のNPOである「こだまの富士倶楽部」の山口代表の話があった。
福岡市民の方は知っている人も多いと思うが、三瀬峠を挟んで佐賀県側の富士町や七山、大和町などは、土曜日や休日ともなれば、福岡ナンバーの車が多く、産直販売所や温泉、蕎麦屋などの駐車場がいっぱいになる。
ここ5年くらいでぐんと車の量も増えたように思え、ますます福岡市民の癒しの場所として、存在感を増しつつあるという感じだ。
こだまの富士倶楽部では、現在、グリーンツーズムの一環で農家への民泊事業を展開しているということで、家族連れや若い人に泊まってもらっているということだった。
福岡と佐賀はとても近い。佐賀からは天神などに買い物に行く若者も多く、身近に感じているのだが、福岡の人は佐賀に来たことが無いというひともまだまだ多い。呼子や唐津を佐賀だと思っていない人もいたりするが・・←極端な例!
(からつバーガーって佐賀だったの! という人がいたな・・)
さて、今日の佐賀新聞には、北山少年自然の家が、お年寄りに人気、という見出しの記事がある。
読んでみると、少子化で子供の利用が減る中、名物の山菜料理や佐賀にわか公演、などの企画事業に人気があり、高齢者の利用が増えているとある。
少年自然の家ならぬ、長寿自然の家といったところか。
大体にして、少年たちの団体行動への適応能力はどんどん低下しているだろう。それに反して、中年以上の方の団体活動に対する適応能力はおしなべて高く、それがどういった背景なのかは具体的には説明できないが、兄弟親戚が多かったり、地域の寄り合いがあったり、学校生活や会社生活も団体で行なうことになれているという背景があるだろう。
お笑いブームで面白いのは若者だけだと思っている人はいないと思うが、中年以上の人たちの寄り合いに参加すると、その面白さには圧倒される。必ず芸達者な人がなかに何人もいて、歌をうたったり、踊りをおどったり、場を賑わせる芸には事足りない。
カラオケしか歌う手段をしらない私たちの世代以下よりは、圧倒的に芸達者なのだ。
そういうお年寄りが北山少年自然の家に集まって、夜通しで交流を深めるということだから、それは賑わうだろう。その満足感が、またみんなで行きたかねえ、となってリピーターとして定着するのではないだろうか。
昨日は佐賀県貿易協会のセミナーに講師に呼ばれ、Webサイトの活用についていろいろと話をさせてもらった。
セミナーでは、時間の半分をログ解析とブログの話にあて、いかに運営が大切かということと、ブログを活用することのメリットを話した。
そういう自分のブログがなかなか更新されていないというのは、医者の不養生そのものなのだが・・(苦笑)
一昨日の3月6日(月)は、「福岡・佐賀経済フォーラム」と題して開催された経済交流会に参加した。基調講演として、佐賀市富士町のNPOである「こだまの富士倶楽部」の山口代表の話があった。
福岡市民の方は知っている人も多いと思うが、三瀬峠を挟んで佐賀県側の富士町や七山、大和町などは、土曜日や休日ともなれば、福岡ナンバーの車が多く、産直販売所や温泉、蕎麦屋などの駐車場がいっぱいになる。
ここ5年くらいでぐんと車の量も増えたように思え、ますます福岡市民の癒しの場所として、存在感を増しつつあるという感じだ。
こだまの富士倶楽部では、現在、グリーンツーズムの一環で農家への民泊事業を展開しているということで、家族連れや若い人に泊まってもらっているということだった。
福岡と佐賀はとても近い。佐賀からは天神などに買い物に行く若者も多く、身近に感じているのだが、福岡の人は佐賀に来たことが無いというひともまだまだ多い。呼子や唐津を佐賀だと思っていない人もいたりするが・・←極端な例!
(からつバーガーって佐賀だったの! という人がいたな・・)
さて、今日の佐賀新聞には、北山少年自然の家が、お年寄りに人気、という見出しの記事がある。
読んでみると、少子化で子供の利用が減る中、名物の山菜料理や佐賀にわか公演、などの企画事業に人気があり、高齢者の利用が増えているとある。
少年自然の家ならぬ、長寿自然の家といったところか。
大体にして、少年たちの団体行動への適応能力はどんどん低下しているだろう。それに反して、中年以上の方の団体活動に対する適応能力はおしなべて高く、それがどういった背景なのかは具体的には説明できないが、兄弟親戚が多かったり、地域の寄り合いがあったり、学校生活や会社生活も団体で行なうことになれているという背景があるだろう。
お笑いブームで面白いのは若者だけだと思っている人はいないと思うが、中年以上の人たちの寄り合いに参加すると、その面白さには圧倒される。必ず芸達者な人がなかに何人もいて、歌をうたったり、踊りをおどったり、場を賑わせる芸には事足りない。
カラオケしか歌う手段をしらない私たちの世代以下よりは、圧倒的に芸達者なのだ。
そういうお年寄りが北山少年自然の家に集まって、夜通しで交流を深めるということだから、それは賑わうだろう。その満足感が、またみんなで行きたかねえ、となってリピーターとして定着するのではないだろうか。
ホテル龍登園の農業体験プラン
2006年2月22日(水)佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀市大和町川上峡にある、ホテル龍登園。
子供の頃は、多久の子供クラブの夏休みのイベントで、龍登園のプールに行くのがステータスだった。といえば、多久近辺の子供クラブのことだけだったのだろうか??
といいながら、私は龍登園に行くというときに、なぜか行けない用事ができて、小学生のときは行ったことがなかった。
初めて龍登園に行ったのは、小城高校に入学した1年のときの勉強合宿。そのときは、なにか子供の頃行きたくてもいけなかった思いが達成されたような感じをもったことをうっすらと述懐する。
そのホテル龍登園が、農業体験で顧客を獲得しようと、「田舎クラブ」なるものを立ち上げ、退職後の世代をターゲットに農業のあれこれを教える企画を実施するとある。
農業体験は、会員になってもらい、ホテル近くの農地を使って、田んぼで稲の栽培や、畑で野菜の栽培などをしてもらうというもの。
会員には、宿泊料の割引特典があり、農作業に訪れやすくするという。
昨日書いた、ファミリーツーリズムの、何のために?佐賀に訪れるのか?の問いに、きちんと答えることができる、素晴らしい企画だと思う。
農業をしに、佐賀へ。そして泊まる。シンプルだ。
詳しくは、龍登園のWebサイトを見てもらいたい。
それから、今日は、さがファンオンラインショッピングモールの、出店者説明会を佐賀市で行なった。8名の参加者があり、熱心にさがファンのコンセプトや事業内容を聞いたもらった。
それともう一つ。
福博印刷株式会社Webビジネスカンパニーでは、人材を急募している。
未経験者でもやる気があれば応募待っていますので、Webビジネスやりて縲怐Aいまも十分にいけてる佐賀をさらにWebを使って盛り上げたい!と思っている方。
ぜひ、門を叩いてください。待っています。
佐賀市大和町川上峡にある、ホテル龍登園。
子供の頃は、多久の子供クラブの夏休みのイベントで、龍登園のプールに行くのがステータスだった。といえば、多久近辺の子供クラブのことだけだったのだろうか??
といいながら、私は龍登園に行くというときに、なぜか行けない用事ができて、小学生のときは行ったことがなかった。
初めて龍登園に行ったのは、小城高校に入学した1年のときの勉強合宿。そのときは、なにか子供の頃行きたくてもいけなかった思いが達成されたような感じをもったことをうっすらと述懐する。
そのホテル龍登園が、農業体験で顧客を獲得しようと、「田舎クラブ」なるものを立ち上げ、退職後の世代をターゲットに農業のあれこれを教える企画を実施するとある。
農業体験は、会員になってもらい、ホテル近くの農地を使って、田んぼで稲の栽培や、畑で野菜の栽培などをしてもらうというもの。
会員には、宿泊料の割引特典があり、農作業に訪れやすくするという。
昨日書いた、ファミリーツーリズムの、何のために?佐賀に訪れるのか?の問いに、きちんと答えることができる、素晴らしい企画だと思う。
農業をしに、佐賀へ。そして泊まる。シンプルだ。
詳しくは、龍登園のWebサイトを見てもらいたい。
それから、今日は、さがファンオンラインショッピングモールの、出店者説明会を佐賀市で行なった。8名の参加者があり、熱心にさがファンのコンセプトや事業内容を聞いたもらった。
それともう一つ。
福博印刷株式会社Webビジネスカンパニーでは、人材を急募している。
未経験者でもやる気があれば応募待っていますので、Webビジネスやりて縲怐Aいまも十分にいけてる佐賀をさらにWebを使って盛り上げたい!と思っている方。
ぜひ、門を叩いてください。待っています。
ファミリーツーリズム雑感
2006年2月21日(火)佐賀新聞朝刊26頁より
佐賀新聞26面に、
古川流総仕上げへ 点検2006年県予算
ということで、連載記事が掲載されていて、今日の佐賀新聞は観光戦略がテーマとして上げられている。
県の観光戦略は「ファミリーツーリズム」というテーマで、親、子、孫の三世代家族旅行を推進する取り組みを行なっている。
記事によると、ファミリーツーリズムの第一弾の企画である、唐津市の旅館業界が行なったキャンペーンが思ったような成果を得ることができず、苦戦したことがあげられ、ファミリーツーリズムという着想をどう具体化していくか、方向性が見えにくいという指摘もある。
ファミリーツーリズムというテーマはもちろん悪くないし、新聞に書いてあるとおり、語感も良く、PRしやすいと思う。
国内の旅行といっても佐賀の認知度は下から数えた方が早いと思われるので、ファミリーツーリズムという切り口だけでは総花的であることは否めず、これっといった魅力が浮かばないのが理由のひとつではないだろうか。
家族で佐賀へ
何しに?何のために?←この問いに答えてもらうような企画が必要なのではないだろうか?
しかし、唐津で苦戦ということだったら、県内どこも苦戦するような気がするなあ。。
観光立県、IT立県、図書館日本一、いくつか県のプロジェクトはあるが、どれも全国的には下から数えた方が早いという認識に立って、選択と集中で、スピードあげて取り組む必要があるだろう。
ちなみに、なみログでは、佐賀県は「勉強立県」としてPRすることを提案している。最近読者になった関係者の方はぜひご一考を。
勉強県佐賀! 勉強するなら佐賀に来い!
佐賀は勉強立県だ、を参照
佐賀新聞26面に、
古川流総仕上げへ 点検2006年県予算
ということで、連載記事が掲載されていて、今日の佐賀新聞は観光戦略がテーマとして上げられている。
県の観光戦略は「ファミリーツーリズム」というテーマで、親、子、孫の三世代家族旅行を推進する取り組みを行なっている。
記事によると、ファミリーツーリズムの第一弾の企画である、唐津市の旅館業界が行なったキャンペーンが思ったような成果を得ることができず、苦戦したことがあげられ、ファミリーツーリズムという着想をどう具体化していくか、方向性が見えにくいという指摘もある。
ファミリーツーリズムというテーマはもちろん悪くないし、新聞に書いてあるとおり、語感も良く、PRしやすいと思う。
国内の旅行といっても佐賀の認知度は下から数えた方が早いと思われるので、ファミリーツーリズムという切り口だけでは総花的であることは否めず、これっといった魅力が浮かばないのが理由のひとつではないだろうか。
家族で佐賀へ
何しに?何のために?←この問いに答えてもらうような企画が必要なのではないだろうか?
しかし、唐津で苦戦ということだったら、県内どこも苦戦するような気がするなあ。。
観光立県、IT立県、図書館日本一、いくつか県のプロジェクトはあるが、どれも全国的には下から数えた方が早いという認識に立って、選択と集中で、スピードあげて取り組む必要があるだろう。
ちなみに、なみログでは、佐賀県は「勉強立県」としてPRすることを提案している。最近読者になった関係者の方はぜひご一考を。
勉強県佐賀! 勉強するなら佐賀に来い!
佐賀は勉強立県だ、を参照
唐津市民手作りドラマ
2006年2月18日(土)佐賀新聞朝刊28頁より
唐津市民の小、中、高校生など30人のスタッフで、唐津市をPRするドラマが完成したとある。
映像づくりをとおして子供たちの社会参画を促し、唐津の魅力を発信しようと、唐津市教委が企画した。
ドラマは1時間で、小、中、高校生編に分かれた三話構成。クライマックスは唐津くんちというストーリーだ。
佐賀県は、古湯映画祭や、伊万里市に黒澤明記念館(現在はサテライト館)ができ、黒澤明映画祭が開かれるなど、映画、映像に取り組む活動が盛んになってきている。
映像への憧れはとくに子供たちにとっては、強いものがあるだろう。しかしそれが、ほとんどの場合、作り手としての魅力より、見る側としての魅力のままで興味がとまってしまう場合が多い。とくにゲームにはその傾向が強いだろう。
簡単なゲームや遊びであれば、ルールを自分たちだけで勝手に脚色して遊んだりできるが、複雑なゲームになれば、作られたプログラムであるから手は出せないし、完成度も高く、見ていること楽しむことに興味を奪われ、それだけに時間を費やす。一見というより、完璧に完成されたものであるから、自分だったらこう作るのになあとか、なにか違和感があるとか思うことも少なければ、だからといって自分なりの表現もできない。
そういった意味で、子供のころに、演劇や映像製作や文章創作に取り組むことは、大きな可能性を秘めていると思う。
いつまでも情報や芸術を鑑賞する側に甘んじるだけではなく、たまには創作する側に回ってみるということだ。
唐津市民の小、中、高校生など30人のスタッフで、唐津市をPRするドラマが完成したとある。
映像づくりをとおして子供たちの社会参画を促し、唐津の魅力を発信しようと、唐津市教委が企画した。
ドラマは1時間で、小、中、高校生編に分かれた三話構成。クライマックスは唐津くんちというストーリーだ。
佐賀県は、古湯映画祭や、伊万里市に黒澤明記念館(現在はサテライト館)ができ、黒澤明映画祭が開かれるなど、映画、映像に取り組む活動が盛んになってきている。
映像への憧れはとくに子供たちにとっては、強いものがあるだろう。しかしそれが、ほとんどの場合、作り手としての魅力より、見る側としての魅力のままで興味がとまってしまう場合が多い。とくにゲームにはその傾向が強いだろう。
簡単なゲームや遊びであれば、ルールを自分たちだけで勝手に脚色して遊んだりできるが、複雑なゲームになれば、作られたプログラムであるから手は出せないし、完成度も高く、見ていること楽しむことに興味を奪われ、それだけに時間を費やす。一見というより、完璧に完成されたものであるから、自分だったらこう作るのになあとか、なにか違和感があるとか思うことも少なければ、だからといって自分なりの表現もできない。
そういった意味で、子供のころに、演劇や映像製作や文章創作に取り組むことは、大きな可能性を秘めていると思う。
いつまでも情報や芸術を鑑賞する側に甘んじるだけではなく、たまには創作する側に回ってみるということだ。
呼子の捕鯨文化
2006年2月12日(日)佐賀新聞朝刊30頁より
唐津市呼子が捕鯨基地として栄えたところだというのは、感覚的には理解できるが、実際のところはなにも知らない。多くの県民がそんなところではないだろうか。
そんな捕鯨に関する歴史、文化を掘り起こそうと、呼子町の住民グループが、「鯨組」というのを作り、捕鯨に関する資料の調査を始めている。その取り組みのひとつが、去年なみログでも紹介した、イベント、鯨セミナーであったようだ。
以前に、民俗学者の宮本常一氏に少しだけ触れたが、氏の著作に、「日本の村・海をひらいた人々」(ちくま文庫)という本があり、海をひらいた人々の章を読むと、捕鯨によって海を人が移動し、文化が伝えられてきたことが判りやすく書かれている。
例えば、長崎県五島の捕鯨技術の向上に、和歌山などの鯨組の存在があったとか、捕鯨に来た人々が、自分の故郷に帰らなくなって、その土地に住むようになって村ができたとか、そういう話が書かれている。
いまは、高速道路や、鉄道が日本全国を張り巡らしているし、飛行機で二点間移動をするような社会だが、交通網が陸地に発達していなかった頃は、多くの移動手段が船だった。船で移動するというのは、単純に二点間移動ではなくて、何箇所も港や漁村を経由しながら、移動する。
そこに交易が生まれたり文化の交流がある。
捕鯨文化の掘り起こしは、単なる鯨だけの問題ではなくて、そこに住む人々の歴史とそこに関わった、海を隔てていまも残る、別の土地との関わりあいまでもが明らかにされていくだろう。
唐津市呼子が捕鯨基地として栄えたところだというのは、感覚的には理解できるが、実際のところはなにも知らない。多くの県民がそんなところではないだろうか。
そんな捕鯨に関する歴史、文化を掘り起こそうと、呼子町の住民グループが、「鯨組」というのを作り、捕鯨に関する資料の調査を始めている。その取り組みのひとつが、去年なみログでも紹介した、イベント、鯨セミナーであったようだ。
以前に、民俗学者の宮本常一氏に少しだけ触れたが、氏の著作に、「日本の村・海をひらいた人々」(ちくま文庫)という本があり、海をひらいた人々の章を読むと、捕鯨によって海を人が移動し、文化が伝えられてきたことが判りやすく書かれている。
例えば、長崎県五島の捕鯨技術の向上に、和歌山などの鯨組の存在があったとか、捕鯨に来た人々が、自分の故郷に帰らなくなって、その土地に住むようになって村ができたとか、そういう話が書かれている。
いまは、高速道路や、鉄道が日本全国を張り巡らしているし、飛行機で二点間移動をするような社会だが、交通網が陸地に発達していなかった頃は、多くの移動手段が船だった。船で移動するというのは、単純に二点間移動ではなくて、何箇所も港や漁村を経由しながら、移動する。
そこに交易が生まれたり文化の交流がある。
捕鯨文化の掘り起こしは、単なる鯨だけの問題ではなくて、そこに住む人々の歴史とそこに関わった、海を隔てていまも残る、別の土地との関わりあいまでもが明らかにされていくだろう。
八福人??
2006年2月2日(木)佐賀新聞朝刊17頁より
七福神は聞いたことがあるが、八福人これいかに?
八福人とは、七福神に貧乏神も加えた言い方で(ちょっと強引すぎる展開だが)、佐賀市の県庁通商店連盟が、八福人による節分祭を開こうと企画したということ。
商売人にとっては、敵となる貧乏神さえも見方につけようということらしい。
(私が勤める会社が出版した八賢伝という本のタイトルが、もともと七賢人といわれた偉人に一人加えたような発想とは根本が違う・・)
八福人の発想の元は、商店街にある竜造寺八幡宮からあやかってつけたということで、適当に付けたわけではないとうこと。
発想としては面白い。あとは続けれることと、貧乏神のキャラクターというか、インパクトというか、だからどうなるの。というところの詰めは必要だろう。七福人だってそれぞれキャラが立っているわけだから。
※話は仕事のことになる。Webサイトの企画立案をしているが、考えれば考えるほど、Webサイトをどう構築するかというよりも、いかにWebサイトを機能させるか、そういう企画にならざるを得ない。
七福神は聞いたことがあるが、八福人これいかに?
八福人とは、七福神に貧乏神も加えた言い方で(ちょっと強引すぎる展開だが)、佐賀市の県庁通商店連盟が、八福人による節分祭を開こうと企画したということ。
商売人にとっては、敵となる貧乏神さえも見方につけようということらしい。
(私が勤める会社が出版した八賢伝という本のタイトルが、もともと七賢人といわれた偉人に一人加えたような発想とは根本が違う・・)
八福人の発想の元は、商店街にある竜造寺八幡宮からあやかってつけたということで、適当に付けたわけではないとうこと。
発想としては面白い。あとは続けれることと、貧乏神のキャラクターというか、インパクトというか、だからどうなるの。というところの詰めは必要だろう。七福人だってそれぞれキャラが立っているわけだから。
※話は仕事のことになる。Webサイトの企画立案をしているが、考えれば考えるほど、Webサイトをどう構築するかというよりも、いかにWebサイトを機能させるか、そういう企画にならざるを得ない。
中心市街地と大型店
2006年1月19日(木)佐賀新聞朝刊2頁より
佐賀市の兵庫地区にできる大型ショッピングセンター。ゆめタウン。
着々と地ならしもすすみ、最近では鉄筋構造物も建ち始めた。
いよいよ佐賀市の流通戦争も最終局面。大和ジャスコ、モラージュ佐賀、ゆめタウン。全国的にも注目される地区だ。
そういう中、佐賀市の中心市街地といえば、エスプラッツビルを中心とした計画が頓挫し、いまもなお、その後の疲弊した状況をどうすることもできないままだ。
今日の2面の論説に、大型店立地規制について、「まちづくり三法」を見直す、都市計画法改正の件が書かれている。
改正後は、大型店の出店については、最終的に都道府県の判断で立地を認めないこともありうることや、述べ床面積が一万平方メートルを超える大型店の郊外立地を原則的に禁止するとある。
そういう取り組みが中心市街地の活性化に果たして直結するのかどうか。
いまさらなにを、という感じがしないでもないし、中心市街地の問題はたしかに大型店の郊外進出による影響もあるが、ほかにも細かな要因があるだろう。一概にいえない。
なぜ、佐賀市の中心市街地、アーケード街はあんなににぎやかだったのだろうか?
なぜ?
あたりまえのことを今一度整理してみることも面白い。
もし当時、大型ショッピングモールが郊外にあったなら、やっぱり多くの人がそっちに行くのかどうか。
中心商店街近辺の人口集積度、車の利用率、他の交通網の状況。当時の家族構成の分布。広域からの集客力・・・
小学生のころ(昭和55年縲怐jの思い出は、佐賀市のアーケード街にいくと人がいっぱい歩いていた印象がある。多久から佐賀玉屋に家族で買い物に行くのも、なにかステータスみたいなものがあって、玉屋に買い物に行った次の日は友達に自慢したりしていた。
個人的な見解としては、具体的な便利さが、いまの中心商店街には乏しいような気がする。必然性も少ないし。
妙案があれば出したいところなのだが。。
※エスプラッツ全館をつかった老人大学のアイデアは、なみログで書いたかな?九州初の本格的な老人大学は面白いと思うのだが。近くの宿泊施設なども抱き込んで、滞在型の講座や研修をしたり。マイクロバスでエスプラッツに横付けすれば、遠くから来る高齢者の交通の不便さは解消される。
講座内容は、歴史だったり、人物だったり、芸術だったり、地域に根ざしたものが面白そうだ。
佐賀市の兵庫地区にできる大型ショッピングセンター。ゆめタウン。
着々と地ならしもすすみ、最近では鉄筋構造物も建ち始めた。
いよいよ佐賀市の流通戦争も最終局面。大和ジャスコ、モラージュ佐賀、ゆめタウン。全国的にも注目される地区だ。
そういう中、佐賀市の中心市街地といえば、エスプラッツビルを中心とした計画が頓挫し、いまもなお、その後の疲弊した状況をどうすることもできないままだ。
今日の2面の論説に、大型店立地規制について、「まちづくり三法」を見直す、都市計画法改正の件が書かれている。
改正後は、大型店の出店については、最終的に都道府県の判断で立地を認めないこともありうることや、述べ床面積が一万平方メートルを超える大型店の郊外立地を原則的に禁止するとある。
そういう取り組みが中心市街地の活性化に果たして直結するのかどうか。
いまさらなにを、という感じがしないでもないし、中心市街地の問題はたしかに大型店の郊外進出による影響もあるが、ほかにも細かな要因があるだろう。一概にいえない。
なぜ、佐賀市の中心市街地、アーケード街はあんなににぎやかだったのだろうか?
なぜ?
あたりまえのことを今一度整理してみることも面白い。
もし当時、大型ショッピングモールが郊外にあったなら、やっぱり多くの人がそっちに行くのかどうか。
中心商店街近辺の人口集積度、車の利用率、他の交通網の状況。当時の家族構成の分布。広域からの集客力・・・
小学生のころ(昭和55年縲怐jの思い出は、佐賀市のアーケード街にいくと人がいっぱい歩いていた印象がある。多久から佐賀玉屋に家族で買い物に行くのも、なにかステータスみたいなものがあって、玉屋に買い物に行った次の日は友達に自慢したりしていた。
個人的な見解としては、具体的な便利さが、いまの中心商店街には乏しいような気がする。必然性も少ないし。
妙案があれば出したいところなのだが。。
※エスプラッツ全館をつかった老人大学のアイデアは、なみログで書いたかな?九州初の本格的な老人大学は面白いと思うのだが。近くの宿泊施設なども抱き込んで、滞在型の講座や研修をしたり。マイクロバスでエスプラッツに横付けすれば、遠くから来る高齢者の交通の不便さは解消される。
講座内容は、歴史だったり、人物だったり、芸術だったり、地域に根ざしたものが面白そうだ。
才能は持ち上げて育つもの
2006年1月10日(火)佐賀新聞朝刊18頁より
なみログや、さがファンの他のブログで、新田舎主義についてのエントリーが続いた。
佐賀新聞に掲載された同じ記事に関心を持ち、それぞれが同時に似通ったり、違ったりした意見を持つ。それをブログに書き、それを見る人がいる。
そうやってブログは機能するから面白い。
今日の佐賀新聞には「さがルネッサンス構想」という見出しのコラムがあった。
内容は、山口亮一記念館を拠点に、さがルネッサンス構想が現在進行中で、今年春にもNPO法人化されるというもの。NPO組織は、佐賀での文化的活動に理解ある人々で記念館開館に協力いただいた人を中心に組織されるようだ。
具体的に何をするかというと、(傍線部分はコラムを引用)
世界レベルで活躍できる質の高い創作活動や、文化活動をされている人たちがこの佐賀に住んでいるのに、佐賀の人は知らないことが多い
ので、
佐賀では、あまり取り上げられないそんな人たちや活動を支援し、スポットライトを当てるため
とある。
面白そうだ。
ひとつ提案だが、すでに才能のある人の支援やスポットライトを当てるのに加えて、発展途上の人もぜひ支援し、スポットライトを当ててもらいたいものだ。
才能は持ち上げられて育つもの。
とくに若いときには。
そういう私ももう10年前になるが、初めて本格的に書いた小説が、佐賀県文学賞で評価され、そのときの嬉しい思いがきっかけで、そのとき小説を書いていこうと心に決めた。
就職してからは、小説も書かなくなったので、持ち上げられることは一切なくなってしまったが・・・残念。
才能というのは、いきなり高いレベルの人はいないわけだから、それぞれの段階で持ち上げられる機会があれば、モチベーションも一気にあがって、飛躍的に才能が開花するかもしれない。
才能があって出て来る奴はどんな環境でも出て来るが、予備軍を育てることも片方では大事なことではないだろうか。
いまのような経済情勢や社会環境であれば、佐賀から芸術家が育つのは難しいと思うからだ。
なあ縲怩ト。
なみログや、さがファンの他のブログで、新田舎主義についてのエントリーが続いた。
佐賀新聞に掲載された同じ記事に関心を持ち、それぞれが同時に似通ったり、違ったりした意見を持つ。それをブログに書き、それを見る人がいる。
そうやってブログは機能するから面白い。
今日の佐賀新聞には「さがルネッサンス構想」という見出しのコラムがあった。
内容は、山口亮一記念館を拠点に、さがルネッサンス構想が現在進行中で、今年春にもNPO法人化されるというもの。NPO組織は、佐賀での文化的活動に理解ある人々で記念館開館に協力いただいた人を中心に組織されるようだ。
具体的に何をするかというと、(傍線部分はコラムを引用)
世界レベルで活躍できる質の高い創作活動や、文化活動をされている人たちがこの佐賀に住んでいるのに、佐賀の人は知らないことが多い
ので、
佐賀では、あまり取り上げられないそんな人たちや活動を支援し、スポットライトを当てるため
とある。
面白そうだ。
ひとつ提案だが、すでに才能のある人の支援やスポットライトを当てるのに加えて、発展途上の人もぜひ支援し、スポットライトを当ててもらいたいものだ。
才能は持ち上げられて育つもの。
とくに若いときには。
そういう私ももう10年前になるが、初めて本格的に書いた小説が、佐賀県文学賞で評価され、そのときの嬉しい思いがきっかけで、そのとき小説を書いていこうと心に決めた。
就職してからは、小説も書かなくなったので、持ち上げられることは一切なくなってしまったが・・・残念。
才能というのは、いきなり高いレベルの人はいないわけだから、それぞれの段階で持ち上げられる機会があれば、モチベーションも一気にあがって、飛躍的に才能が開花するかもしれない。
才能があって出て来る奴はどんな環境でも出て来るが、予備軍を育てることも片方では大事なことではないだろうか。
いまのような経済情勢や社会環境であれば、佐賀から芸術家が育つのは難しいと思うからだ。
なあ縲怩ト。
家業の価値
2006年1月6日(金)佐賀新聞朝刊1頁より
新田舎主義、さが未来探しの5回目。
清酒「東長」で知られる蔵元、瀬頭酒造(嬉野市塩田町)代表取締役の瀬頭氏のインタビュー記事が掲載されている。
前回のなみログで、新田舎主義の価値についてわずかに言及したが、インタビュー記事の中で興味深いことが語られている。(記事は3面)
佐賀新聞をそのまま引用させてもらうと
酒屋を続けていくのは、バトンタッチしていくことだろうと思う。
今まで二百年続いてきて、あと五十年なのか、百年なのか知れないが、自分でつくったものではないわけで、父からバトンタッチされて、息子にバトンタッチしていく。
地方の酒屋が、本当に地域に根付いた伝統産業であるならば、家業としての瀬頭酒造であり、「東長」でないと続いていかない。
そのあとに家業と企業との違いを説明し、
酒だけをまじめに造っていくと考えると、家業じゃないとやっていけない。
と家業である必要性と価値が語ってある。
企業ではやっていけなくて、家業だからやっていける。
「家業」
どちらかというと古い組織体のように思えたり、企業と比較してなんとなくだが弱い組織体のイメージをもっていたが、上の言葉を読むと、家業という言葉にこれまで意識していなかった大きな価値を感じる。
バトンタッチという言葉も判りやすくて、字面がやわらかくていい。字面以上に精神性の高いものを感じるのは私だけではないだろう。
バトンタッチという言葉を見て、真っ先に思い出したのが、埴谷雄高が晩年言っていた、精神のリレーという言葉だ。
新田舎主義、さが未来探しの5回目。
清酒「東長」で知られる蔵元、瀬頭酒造(嬉野市塩田町)代表取締役の瀬頭氏のインタビュー記事が掲載されている。
前回のなみログで、新田舎主義の価値についてわずかに言及したが、インタビュー記事の中で興味深いことが語られている。(記事は3面)
佐賀新聞をそのまま引用させてもらうと
酒屋を続けていくのは、バトンタッチしていくことだろうと思う。
今まで二百年続いてきて、あと五十年なのか、百年なのか知れないが、自分でつくったものではないわけで、父からバトンタッチされて、息子にバトンタッチしていく。
地方の酒屋が、本当に地域に根付いた伝統産業であるならば、家業としての瀬頭酒造であり、「東長」でないと続いていかない。
そのあとに家業と企業との違いを説明し、
酒だけをまじめに造っていくと考えると、家業じゃないとやっていけない。
と家業である必要性と価値が語ってある。
企業ではやっていけなくて、家業だからやっていける。
「家業」
どちらかというと古い組織体のように思えたり、企業と比較してなんとなくだが弱い組織体のイメージをもっていたが、上の言葉を読むと、家業という言葉にこれまで意識していなかった大きな価値を感じる。
バトンタッチという言葉も判りやすくて、字面がやわらかくていい。字面以上に精神性の高いものを感じるのは私だけではないだろう。
バトンタッチという言葉を見て、真っ先に思い出したのが、埴谷雄高が晩年言っていた、精神のリレーという言葉だ。
新田舎主義
2006年1月4日(水)佐賀新聞朝刊1頁より
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
元日と昨日3日には、予定通り多久聖廟と祐徳稲荷神社に初詣に行った。
多久聖廟では、りんご飴を食べることを目的のひとつにしていたので、300円の小さいりんご飴を買った。
さてて、・・・ペロン。
べっこう飴なんだろうな。この飴は。美味しくない。。
なぜりんご飴かというと、りんご飴のりんごは『酸っぱい』という仮説を長年立てていて、まあ、過去の記憶なのだが、その『酸っぱさ』がいったいどれくらい『酸っぱい』か、というのを身をもって体験してみたかったからなのだ。
ペロペロ舐めていても埒があかないので、思い切って齧り付く。
しかし、なかなか齧れない。
こうなったら1点突破主義だ、とばかりに、歯を立てて一箇所を攻める。
おおお、ほどなく、りんごの身にたどり着いた。さてて、りんごの酸っぱさはと。。
・・・案外酸っぱくない。
結論:りんご飴のりんごは案外酸っぱくない。
とつまらん話はさておき、佐賀新聞は元日から、新田舎主義というテーマで特集を組んでいて、
今日の1面には、浜玉町のみのり農場を営む麻生さんのインタビュー記事が掲載されている。
みのり農場は、昨年佐賀新聞紙面でも取り上げられ、なみログでも書いたことのある、養鶏農場で、2004年度の食アメニティ・コンテストで農水大臣賞を受賞した農場だ。
みのり農場のホームページ
麻生さんの言葉に、
これからの農業は、農畜産物の生産や加工販売だけでなく、もっと観光や教育、癒しや健康、環境問題ともリンクしていく夢のあるもの。都会では決して実現不可能です。
とある。農業を中心としたライフスタイル、サービススタイルの充実と広がりにはますます期待したい。
新田舎主義ということで、田舎の魅力をもっと掘り下げたり、情報発信したりしていく試みにスポットがあたることは非常にいい。さらにプラスして大事なのが、新田舎主義というライフスタイル、サービススタイルに、客観的に評価される価値を与えることだろう。
言い方が難しいが、そういう価値を認める人々が多く増えなければならないし、そこに価値があるということを教えていく必要もあるだろう。
価値のあいまいなままで、新田舎主義とだけ掛け声をあげても、なかなか長続きはしないものだ。
例えばであるが、いまの佐賀ではこういうことを言う人がいてもおかしくない。
俺の代までは農業で本物の食を提供していくことだけを考えて一生懸命やってきたが、子供には都会に出て違う仕事に就いてもらいたい。
新田舎主義という言葉の裏に、新田舎主義の価値とは何か、その価値を知らしめたり、理解していく取り組みも必要だと思う。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
元日と昨日3日には、予定通り多久聖廟と祐徳稲荷神社に初詣に行った。
多久聖廟では、りんご飴を食べることを目的のひとつにしていたので、300円の小さいりんご飴を買った。
さてて、・・・ペロン。
べっこう飴なんだろうな。この飴は。美味しくない。。
なぜりんご飴かというと、りんご飴のりんごは『酸っぱい』という仮説を長年立てていて、まあ、過去の記憶なのだが、その『酸っぱさ』がいったいどれくらい『酸っぱい』か、というのを身をもって体験してみたかったからなのだ。
ペロペロ舐めていても埒があかないので、思い切って齧り付く。
しかし、なかなか齧れない。
こうなったら1点突破主義だ、とばかりに、歯を立てて一箇所を攻める。
おおお、ほどなく、りんごの身にたどり着いた。さてて、りんごの酸っぱさはと。。
・・・案外酸っぱくない。
結論:りんご飴のりんごは案外酸っぱくない。
とつまらん話はさておき、佐賀新聞は元日から、新田舎主義というテーマで特集を組んでいて、
今日の1面には、浜玉町のみのり農場を営む麻生さんのインタビュー記事が掲載されている。
みのり農場は、昨年佐賀新聞紙面でも取り上げられ、なみログでも書いたことのある、養鶏農場で、2004年度の食アメニティ・コンテストで農水大臣賞を受賞した農場だ。
みのり農場のホームページ
麻生さんの言葉に、
これからの農業は、農畜産物の生産や加工販売だけでなく、もっと観光や教育、癒しや健康、環境問題ともリンクしていく夢のあるもの。都会では決して実現不可能です。
とある。農業を中心としたライフスタイル、サービススタイルの充実と広がりにはますます期待したい。
新田舎主義ということで、田舎の魅力をもっと掘り下げたり、情報発信したりしていく試みにスポットがあたることは非常にいい。さらにプラスして大事なのが、新田舎主義というライフスタイル、サービススタイルに、客観的に評価される価値を与えることだろう。
言い方が難しいが、そういう価値を認める人々が多く増えなければならないし、そこに価値があるということを教えていく必要もあるだろう。
価値のあいまいなままで、新田舎主義とだけ掛け声をあげても、なかなか長続きはしないものだ。
例えばであるが、いまの佐賀ではこういうことを言う人がいてもおかしくない。
俺の代までは農業で本物の食を提供していくことだけを考えて一生懸命やってきたが、子供には都会に出て違う仕事に就いてもらいたい。
新田舎主義という言葉の裏に、新田舎主義の価値とは何か、その価値を知らしめたり、理解していく取り組みも必要だと思う。
長崎街道ミニツアー
2005年12月19日(月)佐賀新聞朝刊19頁より
18日(日)に長崎街道を軸にした観光ルート作りを進めるNPOが主催する、イベントが行なわれた。
長崎街道ミニツアーがそれだ。
約60人が参加したというのだから、盛況なイベントになった。
佐賀市から嬉野町のシーボルトの湯まで宿場跡を巡ったとある。
昨日も寒かったと思うが、寒い中だからこそ、団結力も生まれて賑わったイベントになったことだろう。
巡った場所は、牛津宿の赤レンガ館、北方宿の本陣、浜宿の酒造通りなど。
先日なみログでも書いた、歩き旅ブームにつながる面白いイベントだ。主催したNPO「活気会」は、今後もマップ作りやウォークラリーも予定しているという。
さて、前回ブログに書いた、宮本常一氏。昨日夜遅く本屋に行って、宮本常一氏の本を二冊買った。宮本常一氏は民俗学者で、民俗学というと柳田国男が有名すぎるほど有名だが、宮本常一は柳田国男と渋沢敬二氏に師事した有名な民俗学者だ。
宮本常一氏は自らの足で、日本全国の津々浦々を歩きまわっている。津々浦々を歩きまわって、村の成り立ちや、家の造り、道具の発達、農業、漁業の発達など、自分の目で見て、資料をあさったり、土地の人に話を聞いたりしながら、日本の地域がどのように成り立ったのかを調べている。
そして、それを私たち後世のものに伝えるべく本にして残している。
昨日はパラパラと、日本の村、海をひらいた人々、を読んだ。まだ途中だが、文章も平易で読みやすい。と思ったら、どうやら小学生向けに書かれた本のようだ。。
まあ、子供向けの本でも宮本常一はいい。読んだことのない人はぜひどうぞ。
18日(日)に長崎街道を軸にした観光ルート作りを進めるNPOが主催する、イベントが行なわれた。
長崎街道ミニツアーがそれだ。
約60人が参加したというのだから、盛況なイベントになった。
佐賀市から嬉野町のシーボルトの湯まで宿場跡を巡ったとある。
昨日も寒かったと思うが、寒い中だからこそ、団結力も生まれて賑わったイベントになったことだろう。
巡った場所は、牛津宿の赤レンガ館、北方宿の本陣、浜宿の酒造通りなど。
先日なみログでも書いた、歩き旅ブームにつながる面白いイベントだ。主催したNPO「活気会」は、今後もマップ作りやウォークラリーも予定しているという。
さて、前回ブログに書いた、宮本常一氏。昨日夜遅く本屋に行って、宮本常一氏の本を二冊買った。宮本常一氏は民俗学者で、民俗学というと柳田国男が有名すぎるほど有名だが、宮本常一は柳田国男と渋沢敬二氏に師事した有名な民俗学者だ。
宮本常一氏は自らの足で、日本全国の津々浦々を歩きまわっている。津々浦々を歩きまわって、村の成り立ちや、家の造り、道具の発達、農業、漁業の発達など、自分の目で見て、資料をあさったり、土地の人に話を聞いたりしながら、日本の地域がどのように成り立ったのかを調べている。
そして、それを私たち後世のものに伝えるべく本にして残している。
昨日はパラパラと、日本の村、海をひらいた人々、を読んだ。まだ途中だが、文章も平易で読みやすい。と思ったら、どうやら小学生向けに書かれた本のようだ。。
まあ、子供向けの本でも宮本常一はいい。読んだことのない人はぜひどうぞ。
地方の9割経済縮小
2005年12月3日(土)佐賀新聞朝刊1頁より
今日の佐賀新聞のまえに・・
さがファンブログの各ブログにも書かれている、パールマッシュさんのキングパールシャンピニオン。さがファンショップのピザとマッシュルーム屋さんのサイトにもアクセスが集中して、注文が殺到した。ありがたい。
キングパールシャンピニオンは、あの大きさであれだけ身の詰まったものは本当に貴重で、パールマッシュさんだけしか生産できない逸品。
たまたまさがファンに出店してもらったのがきっかけで、自社サイトのデザインリニューアルも手がけさせてもらったが、いや、逆だ、自社サイトのリニューアルを手がけていたら、さがファンの事業化が進んだので、出店してもらったのだ。
キングパールシャンピニオンが特選素材に使われることになったのは、ホームページを見られたことがきっかけだったということで、ホームページのリニューアルをした甲斐があった。
誰が見るか分からないので、ホームページは丁寧にメンテナンスを怠らないようにしておきたいものだ。
さて、今日の佐賀新聞。
1面に「地方の9割 経済縮小」という見出しで、2030年には、人口減に伴い地方の9割で、経済規模が縮小するという。
経済産業省の資料
佐賀市で経済縮小率がマイナス3.7%、唐津市がマイナス9.8%と予測してある。
また、5面に少し詳しい記事が載せてあり、その記事を読むと、国土審議会で、
「国土の均衡ある発展」は人口減時代には非効率との議論がされたり、山間地の集落は強制消滅もやむを得ないとの厳しい意見が出たということも。。
予測を見ると、佐賀県の市ではプラスのところがなかった。2030年まであと25年あるが、じわりじわりと経済規模が縮小していくのだろうか。そうならないように何か具体的な策を講じていかないとなるまい。
今日の佐賀新聞のまえに・・
さがファンブログの各ブログにも書かれている、パールマッシュさんのキングパールシャンピニオン。さがファンショップのピザとマッシュルーム屋さんのサイトにもアクセスが集中して、注文が殺到した。ありがたい。
キングパールシャンピニオンは、あの大きさであれだけ身の詰まったものは本当に貴重で、パールマッシュさんだけしか生産できない逸品。
たまたまさがファンに出店してもらったのがきっかけで、自社サイトのデザインリニューアルも手がけさせてもらったが、いや、逆だ、自社サイトのリニューアルを手がけていたら、さがファンの事業化が進んだので、出店してもらったのだ。
キングパールシャンピニオンが特選素材に使われることになったのは、ホームページを見られたことがきっかけだったということで、ホームページのリニューアルをした甲斐があった。
誰が見るか分からないので、ホームページは丁寧にメンテナンスを怠らないようにしておきたいものだ。
さて、今日の佐賀新聞。
1面に「地方の9割 経済縮小」という見出しで、2030年には、人口減に伴い地方の9割で、経済規模が縮小するという。
経済産業省の資料
佐賀市で経済縮小率がマイナス3.7%、唐津市がマイナス9.8%と予測してある。
また、5面に少し詳しい記事が載せてあり、その記事を読むと、国土審議会で、
「国土の均衡ある発展」は人口減時代には非効率との議論がされたり、山間地の集落は強制消滅もやむを得ないとの厳しい意見が出たということも。。
予測を見ると、佐賀県の市ではプラスのところがなかった。2030年まであと25年あるが、じわりじわりと経済規模が縮小していくのだろうか。そうならないように何か具体的な策を講じていかないとなるまい。
まちづくりのイロハ!講座
2005年12月1日(金)佐賀新聞朝刊19頁より
小城市は、NPOによる市民自らが行なう地域づくり、をキーワードに市民団体を養成する「まちづくりのイロハ!」講座を始めた。というニュース。
第1回目は既に終っていて、新聞に掲載されている写真は第2回目のもの。
「NPOさが」の石丸氏が講演し、芸術家グループの「ハーベスト99」を例に、NPOとまちづくりについて話したようだ。
ハーベスト99という団体は、とても興味深い活動をしている団体だ。
なみログでも取り上げたことがあるが、数年前から牛津町(現小城市)とジョイントで、子供向けの芸術に触れる機会を作る講座を引き受け、赤レンガ館などを拠点に地域の芸術活動を支援する取り組みをしている。
最近ではそのノウハウを活かして、小城を中心にアートとまちづくり、人づくりをキーワードに活動の場を広げている。
アートがらみでいえば、アートサポートふくおか、という団体が福岡にある。
http://www.as-fuk.com/
アートサポートふくおかも、福岡を拠点にさまざまなアートとまちづくりに関する活動を行なっている。
小城市は、NPOによる市民自らが行なう地域づくり、をキーワードに市民団体を養成する「まちづくりのイロハ!」講座を始めた。というニュース。
第1回目は既に終っていて、新聞に掲載されている写真は第2回目のもの。
「NPOさが」の石丸氏が講演し、芸術家グループの「ハーベスト99」を例に、NPOとまちづくりについて話したようだ。
ハーベスト99という団体は、とても興味深い活動をしている団体だ。
なみログでも取り上げたことがあるが、数年前から牛津町(現小城市)とジョイントで、子供向けの芸術に触れる機会を作る講座を引き受け、赤レンガ館などを拠点に地域の芸術活動を支援する取り組みをしている。
最近ではそのノウハウを活かして、小城を中心にアートとまちづくり、人づくりをキーワードに活動の場を広げている。
アートがらみでいえば、アートサポートふくおか、という団体が福岡にある。
http://www.as-fuk.com/
アートサポートふくおかも、福岡を拠点にさまざまなアートとまちづくりに関する活動を行なっている。