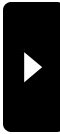スポンサーサイト
佐賀市中心商店街考
2007年4月3日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
大好きな小説、楢山節考、にちなんで、佐賀市中心商店街考。
今日の佐賀新聞の経済面は、ビジネス談話室という新しいコーナー?で、TMOタウンマネジャーの伊豆氏の談話が載っている。
伊豆氏は、佐賀商工会議所のまちづくり機構「TMO佐賀」のマネジャーに2006年4月に就任し、佐賀市中心商店街を活性化するべく、敏腕を振るってきた。
伊豆氏の談話のなかには、長崎街道について言及するところがあり、佐賀市中心部の人の中でも、知らない人が増えたとあり、佐賀市の中心部を歴史、文化の集積地にしたいとある。
↑これって相当な方向転換に感じるのだが・・・
つい昨年のエスプラッツの再開発案の中には、飲食ビル構想だったり、癒し構想だったりしたわけで。佐賀新聞文化センターが入ることによって色合いが、文化、歴史となったとは思うが、当初のビジョンにあったかなあ・・・
個人的には良い方向に向いたと思うので、良いが。
ちなみに、なみログでは、再三再四にわたり、老人大学校みたいなカルチャーセンターを作ったらどうか、と提案をしてきた。
通学は、佐賀駅から直行バスを使えばいいと思う。
それから、紙面の下には、スーパーモリナガが、二酸化炭素削減の取り組みを勉強する、エコ教室を開催するとある。8日(日)鹿島店で。ご近所の方はどうぞ。
大好きな小説、楢山節考、にちなんで、佐賀市中心商店街考。
今日の佐賀新聞の経済面は、ビジネス談話室という新しいコーナー?で、TMOタウンマネジャーの伊豆氏の談話が載っている。
伊豆氏は、佐賀商工会議所のまちづくり機構「TMO佐賀」のマネジャーに2006年4月に就任し、佐賀市中心商店街を活性化するべく、敏腕を振るってきた。
伊豆氏の談話のなかには、長崎街道について言及するところがあり、佐賀市中心部の人の中でも、知らない人が増えたとあり、佐賀市の中心部を歴史、文化の集積地にしたいとある。
↑これって相当な方向転換に感じるのだが・・・
つい昨年のエスプラッツの再開発案の中には、飲食ビル構想だったり、癒し構想だったりしたわけで。佐賀新聞文化センターが入ることによって色合いが、文化、歴史となったとは思うが、当初のビジョンにあったかなあ・・・
個人的には良い方向に向いたと思うので、良いが。
ちなみに、なみログでは、再三再四にわたり、老人大学校みたいなカルチャーセンターを作ったらどうか、と提案をしてきた。
通学は、佐賀駅から直行バスを使えばいいと思う。
それから、紙面の下には、スーパーモリナガが、二酸化炭素削減の取り組みを勉強する、エコ教室を開催するとある。8日(日)鹿島店で。ご近所の方はどうぞ。
山笠サミットが開催された
2007年2月19日(月)佐賀新聞朝刊22頁より
2月18日(日)に唐津市鏡にある古代の森会館で、山笠サミットなる会合が行われた。
唐津をはじめ、伊万里市や前原市などから関係者11名が参加。熱心に各地域で行っている山笠について情報交換したとある。
新聞記事によると、会合は7年ぶりに行われたとある。7年前は、参加者50人。今回は、高齢化やまつり自体の中止もあって、11名と少ない会合に。
こういう記事は、あとで読むだけだったら、もっとあちこちから関係しそうな人を呼んで、やればよかったのに、とかいえるけど、実際に会合を企画する側になったら人集めも大変なものだ。
実際に、私もボランティアとか会社のセミナーとかで、人集めには苦労をする。まあもちろんつきあいだけで動員をしてもしかたのないことなのだが、それでもある程度盛り上がりを欠かないくらいの人には参加してもらいたい。
それはそうと、情報交換の中身だが、どこの山笠も後継者不足で悩んでいるということのようだ。
見にくる人は、ネットでの情報収集や交通の便がよくなったおかげもあって、近年増加傾向にあるまつりが多いと思うのだが、やる側の人手不足や後継者不足は深刻な問題のようだ。
ウェブ2.0が流行っているが、「まつり2.0」でも考えたりしないとならないのだろうか。。(苦笑)
2月18日(日)に唐津市鏡にある古代の森会館で、山笠サミットなる会合が行われた。
唐津をはじめ、伊万里市や前原市などから関係者11名が参加。熱心に各地域で行っている山笠について情報交換したとある。
新聞記事によると、会合は7年ぶりに行われたとある。7年前は、参加者50人。今回は、高齢化やまつり自体の中止もあって、11名と少ない会合に。
こういう記事は、あとで読むだけだったら、もっとあちこちから関係しそうな人を呼んで、やればよかったのに、とかいえるけど、実際に会合を企画する側になったら人集めも大変なものだ。
実際に、私もボランティアとか会社のセミナーとかで、人集めには苦労をする。まあもちろんつきあいだけで動員をしてもしかたのないことなのだが、それでもある程度盛り上がりを欠かないくらいの人には参加してもらいたい。
それはそうと、情報交換の中身だが、どこの山笠も後継者不足で悩んでいるということのようだ。
見にくる人は、ネットでの情報収集や交通の便がよくなったおかげもあって、近年増加傾向にあるまつりが多いと思うのだが、やる側の人手不足や後継者不足は深刻な問題のようだ。
ウェブ2.0が流行っているが、「まつり2.0」でも考えたりしないとならないのだろうか。。(苦笑)
佐賀市中心市街地エスプラッツ問題
2007年2月15日(木)佐賀新聞朝刊24頁より
「エスプラッツ問題」
といってしまっては気の毒なのだが、問題になっている件で、1階部分の商業スペースに、福岡のスーパーが入居することが内定したとある。
福岡県内に6店舗を展開するスーパーが入るそうだ。んん・・・どこだろう??
エスプラッツは他に、カフェレストラン、レストラン、旅行業が内定している。ほかには、子育て支援センターや、ハローワーク関連施設、佐賀市の窓口業務の一部なども。
3階には、佐賀新聞文化センターの入居が決まっている。
いずれも、9月の開店を予定しているとある。
ようやく、エスプラッツ問題が、問題でなくなる日が近づいてきた、というところか。
「エスプラッツ問題」
といってしまっては気の毒なのだが、問題になっている件で、1階部分の商業スペースに、福岡のスーパーが入居することが内定したとある。
福岡県内に6店舗を展開するスーパーが入るそうだ。んん・・・どこだろう??
エスプラッツは他に、カフェレストラン、レストラン、旅行業が内定している。ほかには、子育て支援センターや、ハローワーク関連施設、佐賀市の窓口業務の一部なども。
3階には、佐賀新聞文化センターの入居が決まっている。
いずれも、9月の開店を予定しているとある。
ようやく、エスプラッツ問題が、問題でなくなる日が近づいてきた、というところか。
がばいばあちゃんロケ地ツアーが始まる。
2007年1月11日(木)佐賀新聞朝刊20頁より
1月4日のフジテレビのドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」
いまさらなみログでいうまでもなく、全国のお茶の間の感動をさらった。
テレビ欄を見たとき、テレビ朝日が、渡哲也主演の「マグロ」、日本テレビが「どっちの料理ショー」だったので、正直公表されている19パーセントもの視聴率がとれるのだろうかという疑いをもっていたが、なんのこと、その帯では1番の視聴率だったとな。
さて、そのドラマのロケ地としてドラマが撮影された武雄市では、早速ロケ地を見学するツアーがはじまり、佐賀市の老人クラブ連合会・勧興校区の会員約50人が現地を訪れたとある。
新聞紙面には、堀川の土手の上に立ち、ツアー客にハンドマイクで説明をする、武雄市の樋渡市長の姿が写真に写っている。
精力的に動いているなーと、感心。楽しく樋渡市長の話を聞いている様子が、写真から伝わる。
ということで、佐賀のがばいばあちゃん旋風は、まだまだ続く。
1月4日のフジテレビのドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」
いまさらなみログでいうまでもなく、全国のお茶の間の感動をさらった。
テレビ欄を見たとき、テレビ朝日が、渡哲也主演の「マグロ」、日本テレビが「どっちの料理ショー」だったので、正直公表されている19パーセントもの視聴率がとれるのだろうかという疑いをもっていたが、なんのこと、その帯では1番の視聴率だったとな。
さて、そのドラマのロケ地としてドラマが撮影された武雄市では、早速ロケ地を見学するツアーがはじまり、佐賀市の老人クラブ連合会・勧興校区の会員約50人が現地を訪れたとある。
新聞紙面には、堀川の土手の上に立ち、ツアー客にハンドマイクで説明をする、武雄市の樋渡市長の姿が写真に写っている。
精力的に動いているなーと、感心。楽しく樋渡市長の話を聞いている様子が、写真から伝わる。
ということで、佐賀のがばいばあちゃん旋風は、まだまだ続く。
「ラックワン」という会社の宅地開発
2006年12月12日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
12月9日(土)の、フジテレビ(佐賀ではサガテレビ)の土曜プレミアムドラマ、
戦場の郵便配達。
見た人も多いだろう。
さがファンブックスで、市丸利之助伝という本を取り扱っているので、土日はアクセスもかなり増えた。
まあ、それはそれとして、
藤竜也といえば、草刈正雄と二人で出ていたプロハンターという探偵ドラマをすぐに思い出す世代で(それでも見ていたのは、夕方だったので再放送だ)、歳をとっても、相変わらずかっこいいなーと思ったりした。
若いときにあれだけ若者の憧れみたいなかっこいい役ばかりしていると、歳をとると、潰しが利かない役者になったりする人も少なくないだろうが、藤竜也は、いつのまにか、プロハンターのイメージを払拭するのに成功したようだ。
さて、話は今日の佐賀新聞で、
ラックワンという佐賀市の玉屋横で楽庵というギャラリーを運営している会社が、先日、ドイツの見本市に出展したというブログを書いたが、今度は、佐賀市の新栄東に宅地開発をするという。
それも、コンセプトに、「人」
を掲げ、宅地内だけではなく、地域住民の方たちとの結びつきも重視するような宅地だという。
14区画の、説明会が、17日(日)の午後3時からギャラリー楽庵であるというので、興味のある人は事前に連絡をとのことだ。
楽庵Webサイト
※Webサイトはもう少し簡単に検索にかかるようにしてもらいたいですねえ。。
12月9日(土)の、フジテレビ(佐賀ではサガテレビ)の土曜プレミアムドラマ、
戦場の郵便配達。
見た人も多いだろう。
さがファンブックスで、市丸利之助伝という本を取り扱っているので、土日はアクセスもかなり増えた。
まあ、それはそれとして、
藤竜也といえば、草刈正雄と二人で出ていたプロハンターという探偵ドラマをすぐに思い出す世代で(それでも見ていたのは、夕方だったので再放送だ)、歳をとっても、相変わらずかっこいいなーと思ったりした。
若いときにあれだけ若者の憧れみたいなかっこいい役ばかりしていると、歳をとると、潰しが利かない役者になったりする人も少なくないだろうが、藤竜也は、いつのまにか、プロハンターのイメージを払拭するのに成功したようだ。
さて、話は今日の佐賀新聞で、
ラックワンという佐賀市の玉屋横で楽庵というギャラリーを運営している会社が、先日、ドイツの見本市に出展したというブログを書いたが、今度は、佐賀市の新栄東に宅地開発をするという。
それも、コンセプトに、「人」
を掲げ、宅地内だけではなく、地域住民の方たちとの結びつきも重視するような宅地だという。
14区画の、説明会が、17日(日)の午後3時からギャラリー楽庵であるというので、興味のある人は事前に連絡をとのことだ。
楽庵Webサイト
※Webサイトはもう少し簡単に検索にかかるようにしてもらいたいですねえ。。
協働化テストに全国から361件!!
2006年12月6日(水)佐賀新聞朝刊20頁より
12月定例県議会の一般質問の記事が出ている。
その中で、協働化テストに、全国から361件の応募があったとのこと。結構集まった。
協働化テストとは、記事を引用すると、県の業務を民間事業者に委託したり、NPOなどと連携して進める試み。
詳しくは協働化テストについての県のページを
これって面白い試みだなーと思う。
もちろんなんでもかんでも、委託事業にしたり、NPOと連携したりするだけでは、行政事業の丸投げということで問題もあるだろうが、民間企業や、NPOがやったほうが、効率化が図れたり、受益者便益があるようなものは、委託や連携をしたほうがいいだろう。
しかし、佐賀県内からだけではなく、全国からというのが驚きだ。確か先日、なにかの折に、海外からも問い合わせがあったと聞く。
佐賀県民がしたほうが良さそうなのは、できるだけ佐賀県民でできるようにしてもらいたいものだが、全国の人や団体や企業から、関心を持たれたという点では、面白い試みだということだろう。
12月定例県議会の一般質問の記事が出ている。
その中で、協働化テストに、全国から361件の応募があったとのこと。結構集まった。
協働化テストとは、記事を引用すると、県の業務を民間事業者に委託したり、NPOなどと連携して進める試み。
詳しくは協働化テストについての県のページを
これって面白い試みだなーと思う。
もちろんなんでもかんでも、委託事業にしたり、NPOと連携したりするだけでは、行政事業の丸投げということで問題もあるだろうが、民間企業や、NPOがやったほうが、効率化が図れたり、受益者便益があるようなものは、委託や連携をしたほうがいいだろう。
しかし、佐賀県内からだけではなく、全国からというのが驚きだ。確か先日、なにかの折に、海外からも問い合わせがあったと聞く。
佐賀県民がしたほうが良さそうなのは、できるだけ佐賀県民でできるようにしてもらいたいものだが、全国の人や団体や企業から、関心を持たれたという点では、面白い試みだということだろう。
がBuyさがん運動!!
2006年11月30日(木)佐賀新聞朝刊27頁より
がBuyさがん運動!!
ご当地キャッチフレーズの王道を行くようなネーミング。どうだ!という感じだ。
これくらい、思い切ると、それもまたいいのかも知れない。
佐賀商工会議所が、佐賀市内の小売販売額の増加につなげようと、「がBuyさがん運動!!」を展開する。来年3月まで。
この取り組みは、県が今年から進めている、Buyさがん2006県民運動を支援しようと独自に企画したもの。
500円毎にカードにスタンプを押してもらうもので、50個たまると協賛十社の中から賞品が抽選であたるとな。
参加予定店一覧は、佐賀商工会議所サイトで
その記事の下には、佐賀市中心商店街にあるエスプラッツに、佐賀新聞文化センターが入るという記事が。
なみログでも何回か取り上げている、文化交流ができる場所というのはいいと思う。
※なみログでは、高齢者大学を提案していた。
4月から202講座を開くというから、とても面白そうだ。
その他記事によると、子育て支援センターも入るとある。
ふーん。
ところで、エスプラッツとアイスクエアとほほえみ館は、どんな風に住み分けがあるのだろうか。
市民活動といえば、アイスクエアがなかったころは、ほほえみ館で何でもあっていて、アイスクエアができて、アイスクエアにも人が集まるようになった。
そしてエスプラッツ。
なんかもう少しまとまって建っていればいいのになーと思ったりするんだけど。
がBuyさがん運動!!
ご当地キャッチフレーズの王道を行くようなネーミング。どうだ!という感じだ。
これくらい、思い切ると、それもまたいいのかも知れない。
佐賀商工会議所が、佐賀市内の小売販売額の増加につなげようと、「がBuyさがん運動!!」を展開する。来年3月まで。
この取り組みは、県が今年から進めている、Buyさがん2006県民運動を支援しようと独自に企画したもの。
500円毎にカードにスタンプを押してもらうもので、50個たまると協賛十社の中から賞品が抽選であたるとな。
参加予定店一覧は、佐賀商工会議所サイトで
その記事の下には、佐賀市中心商店街にあるエスプラッツに、佐賀新聞文化センターが入るという記事が。
なみログでも何回か取り上げている、文化交流ができる場所というのはいいと思う。
※なみログでは、高齢者大学を提案していた。
4月から202講座を開くというから、とても面白そうだ。
その他記事によると、子育て支援センターも入るとある。
ふーん。
ところで、エスプラッツとアイスクエアとほほえみ館は、どんな風に住み分けがあるのだろうか。
市民活動といえば、アイスクエアがなかったころは、ほほえみ館で何でもあっていて、アイスクエアができて、アイスクエアにも人が集まるようになった。
そしてエスプラッツ。
なんかもう少しまとまって建っていればいいのになーと思ったりするんだけど。
神奈川県川崎市でからつくんち!
2006年10月25日(水)佐賀新聞朝刊16頁より
神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘にある、唐津市出身者の学生寮「久敬社」。
首都圏に通う大学生の宿舎だそうだが、その寮生が、からつくんちの曳き山「赤獅子」を曳いて寮のある地域を歩いたとある。
なんのことかというと、三十年前に現塾監の中山氏が塾生だったころ、塾生たちで、からつくんちの赤獅子を手作りして作り、それを曳いたのが始まりだそうで、毎年の地域の恒例行事になっているという。
新聞の写真にその赤獅子が写っているが、みたところかなり高精度な曳き山に仕上がっている。
二人の若者が山に乗っている姿も。
唐津市であるからつくんちは、11月2日の宵山から始まるということで、全国の唐津市出身者や、ゆかりのある人、からつくんちのファンは、いまが一番楽しみになときだろう。
神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘にある、唐津市出身者の学生寮「久敬社」。
首都圏に通う大学生の宿舎だそうだが、その寮生が、からつくんちの曳き山「赤獅子」を曳いて寮のある地域を歩いたとある。
なんのことかというと、三十年前に現塾監の中山氏が塾生だったころ、塾生たちで、からつくんちの赤獅子を手作りして作り、それを曳いたのが始まりだそうで、毎年の地域の恒例行事になっているという。
新聞の写真にその赤獅子が写っているが、みたところかなり高精度な曳き山に仕上がっている。
二人の若者が山に乗っている姿も。
唐津市であるからつくんちは、11月2日の宵山から始まるということで、全国の唐津市出身者や、ゆかりのある人、からつくんちのファンは、いまが一番楽しみになときだろう。
10年ぶりの沖縄の旅
2006年10月17日(火)佐賀新聞朝刊17頁より
佐賀新聞の17面に、佐賀大学のサテライトで、「むつごろう館」というのが鹿島市七浦にオープンしたとある。(施設は、七浦の、海浜スポーツ公園体育館を利用)
鹿島市と佐賀大学が、干潟環境教育のプログラム開発と、実践活動の拠点作りということで準備を進めてきたものとある。
有明海の干潟は、ガタリンピックなどでも知られるとおり、干潟で泥にまみれて遊んだりするのが面白い。新聞紙上でも、県外の修学旅行生に、干潟体験は人気があるという記事が何回も載っている。
私も小学生のとき、多久市の小学校なのだが、バス旅行のルートで干潟体験をするのがあった。小学校4年生だったか。いまではその感触がどのようなものだったのかは覚えていないが、体験したこと自体は忘れていない。
むつごろう館でも、干潟遊びを体験する講座などが組まれているようで、面白そうだ。
話は変わるが、10年ぶりに沖縄に旅に行った。
おなじみの観光ルートである琉球村にも行ったのだが、平日にも関わらず、修学旅行シーズンもあって、大勢の人で賑わっていた。
その中で感じたのは、体験型のプログラムが多く取り入れられていたことだった。
10年前に行ったときは、当時、琉球大学大学院の新城くんに案内してもらって、琉球村の中にある古民家に上がりこんで、サーターアンダーギーを買って食べたりしたが、今度は、三味線の講座や薬草の講座、織物の講座などもそれぞれの古民家であっていた。
10年前より、より身近な生活体験型になっていて、とても楽しめた。
そこで佐賀市の観光のことを考えたのだが、佐賀市って普段観光に来ても、なにもないなー、という感じがした。何もないなー、は「何もできないなー」かも知れない。
見るものは有るのはあるんだろうが、何もできないのだ。
何かをしてもらう、企画が必要だと感じた。
トムソーヤじゃないけど、壁のペンキ塗りも、体験型イベントにするような発想が必要だろう。
※沖縄については、旅の終わりに岡本太郎氏の「沖縄文化論」を買って読み、今度の旅がけっしてホンモノの旅ではなかったことを反省として付け加えておく。
佐賀新聞の17面に、佐賀大学のサテライトで、「むつごろう館」というのが鹿島市七浦にオープンしたとある。(施設は、七浦の、海浜スポーツ公園体育館を利用)
鹿島市と佐賀大学が、干潟環境教育のプログラム開発と、実践活動の拠点作りということで準備を進めてきたものとある。
有明海の干潟は、ガタリンピックなどでも知られるとおり、干潟で泥にまみれて遊んだりするのが面白い。新聞紙上でも、県外の修学旅行生に、干潟体験は人気があるという記事が何回も載っている。
私も小学生のとき、多久市の小学校なのだが、バス旅行のルートで干潟体験をするのがあった。小学校4年生だったか。いまではその感触がどのようなものだったのかは覚えていないが、体験したこと自体は忘れていない。
むつごろう館でも、干潟遊びを体験する講座などが組まれているようで、面白そうだ。
話は変わるが、10年ぶりに沖縄に旅に行った。
おなじみの観光ルートである琉球村にも行ったのだが、平日にも関わらず、修学旅行シーズンもあって、大勢の人で賑わっていた。
その中で感じたのは、体験型のプログラムが多く取り入れられていたことだった。
10年前に行ったときは、当時、琉球大学大学院の新城くんに案内してもらって、琉球村の中にある古民家に上がりこんで、サーターアンダーギーを買って食べたりしたが、今度は、三味線の講座や薬草の講座、織物の講座などもそれぞれの古民家であっていた。
10年前より、より身近な生活体験型になっていて、とても楽しめた。
そこで佐賀市の観光のことを考えたのだが、佐賀市って普段観光に来ても、なにもないなー、という感じがした。何もないなー、は「何もできないなー」かも知れない。
見るものは有るのはあるんだろうが、何もできないのだ。
何かをしてもらう、企画が必要だと感じた。
トムソーヤじゃないけど、壁のペンキ塗りも、体験型イベントにするような発想が必要だろう。
※沖縄については、旅の終わりに岡本太郎氏の「沖縄文化論」を買って読み、今度の旅がけっしてホンモノの旅ではなかったことを反省として付け加えておく。
シュガーロード協議会
2006年9月9日(土)佐賀新聞朝刊23頁より
9月8日、県内13の、NPO法人や、国交省佐賀国道事務所などの団体が集まって、
「シュガーロード協議会」を発足させたとある。
シュガーロードとは、旧長崎街道が、交易街道として知られる中、沿線には数々のお菓子文化が生れたことを指して、そういうようになった。
■シュガーロードに関するサイト(佐賀県観光連盟)
■シュガーロードについてさまざまな活動を行なっている、活気会サイト
協議会では、旧長崎街道のさまざまな通りに名前を付け、観光マップや案内板を作る事業を行なう予定で、国交省の「まちづくりナビプロジェクト」の実施地域として採択される事業だそうだ。
車社会が発展して、なかなかゆっくり歩く機会もなくなったが、いま一度歩き旅ブームなどがやってくれば、長崎街道も面白くなるんだろうなあと思ったりする。
あ、長崎街道をゆっくりじっくりと紹介する、DVDとかあればいいかな。面白いかも。
9月8日、県内13の、NPO法人や、国交省佐賀国道事務所などの団体が集まって、
「シュガーロード協議会」を発足させたとある。
シュガーロードとは、旧長崎街道が、交易街道として知られる中、沿線には数々のお菓子文化が生れたことを指して、そういうようになった。
■シュガーロードに関するサイト(佐賀県観光連盟)
■シュガーロードについてさまざまな活動を行なっている、活気会サイト
協議会では、旧長崎街道のさまざまな通りに名前を付け、観光マップや案内板を作る事業を行なう予定で、国交省の「まちづくりナビプロジェクト」の実施地域として採択される事業だそうだ。
車社会が発展して、なかなかゆっくり歩く機会もなくなったが、いま一度歩き旅ブームなどがやってくれば、長崎街道も面白くなるんだろうなあと思ったりする。
あ、長崎街道をゆっくりじっくりと紹介する、DVDとかあればいいかな。面白いかも。
全国51社の新聞サイト
2006年9月8日(金)佐賀新聞朝刊30頁より
全国の新聞社51社が参加して、国内外のニュースやグルメ、旅などの情報をネットで配信する新しいポータルサイトができるとある。
年内公開予定だそうだ。
記事の書き方には、ヤフーやグーグルといった名前が出てきて、IT企業が圧倒的に優位に立つ現状を脱却すべく、それらに対抗し、ニュース提供者としての役割を再構築するというのが目的のようだ。
ニュース提供者としての役割を再構築するというのは判るが、ヤフーとグーグルを簡単に引合いに出すと、要は情報産業として、金になるところを持っていかれているので、このままでは危ないので、連携を図り金儲けのしくみをつくりたい、というのが本音に聞こえる。
まあそれでもいいと思う。すでに新聞とはなんぞや、という本質を議論すること自体が軽んじられがちな中で、地方の新聞社がいくら旧態の新聞に固執したところで、世の趨勢には置いてけぼりになるだろうから。
いまあるWebサービスでそういった情報が少ないのかといえば、決してそうでもない。新聞社が連携して情報を出そうが出すまいが、必要な人はすでに検索するか、そういうコミュニティーに参加して情報を得ていると思ったりするのだが。
判りやすく佐賀の情報にアクセスされる道すじができればそれはとてもいいことなので、ぜひ佐賀の情報がもっと出るようになってもらい。
九州は全国比で7%とか9%の経済規模であるといわれたりする。それを県の数で割ると、福岡が半分くらい持っていくと思うので、佐賀は1%にも満たない経済規模だろう。
ネットで流れている情報量の県別比較をとったことはないが、佐賀県に関する情報は、1%は極端かもしれないが、ひょっとすると1%という数字に近いのかもしれないと思ったりする。
最近実感として思うのは、佐賀の認知度って、自分たちが思っているほど高くないどころか、相当低いということだ。高けりゃいいという問題ではないが、人口少なくてもうまくPRできているところもあるはず。
なんとか佐賀の認知が高まるような作戦を、Webで打っていけないかと日々考えている。
全国の新聞社51社が参加して、国内外のニュースやグルメ、旅などの情報をネットで配信する新しいポータルサイトができるとある。
年内公開予定だそうだ。
記事の書き方には、ヤフーやグーグルといった名前が出てきて、IT企業が圧倒的に優位に立つ現状を脱却すべく、それらに対抗し、ニュース提供者としての役割を再構築するというのが目的のようだ。
ニュース提供者としての役割を再構築するというのは判るが、ヤフーとグーグルを簡単に引合いに出すと、要は情報産業として、金になるところを持っていかれているので、このままでは危ないので、連携を図り金儲けのしくみをつくりたい、というのが本音に聞こえる。
まあそれでもいいと思う。すでに新聞とはなんぞや、という本質を議論すること自体が軽んじられがちな中で、地方の新聞社がいくら旧態の新聞に固執したところで、世の趨勢には置いてけぼりになるだろうから。
いまあるWebサービスでそういった情報が少ないのかといえば、決してそうでもない。新聞社が連携して情報を出そうが出すまいが、必要な人はすでに検索するか、そういうコミュニティーに参加して情報を得ていると思ったりするのだが。
判りやすく佐賀の情報にアクセスされる道すじができればそれはとてもいいことなので、ぜひ佐賀の情報がもっと出るようになってもらい。
九州は全国比で7%とか9%の経済規模であるといわれたりする。それを県の数で割ると、福岡が半分くらい持っていくと思うので、佐賀は1%にも満たない経済規模だろう。
ネットで流れている情報量の県別比較をとったことはないが、佐賀県に関する情報は、1%は極端かもしれないが、ひょっとすると1%という数字に近いのかもしれないと思ったりする。
最近実感として思うのは、佐賀の認知度って、自分たちが思っているほど高くないどころか、相当低いということだ。高けりゃいいという問題ではないが、人口少なくてもうまくPRできているところもあるはず。
なんとか佐賀の認知が高まるような作戦を、Webで打っていけないかと日々考えている。
佐賀のCSOブログ面白そう!
2006年8月23日(金)佐賀新聞朝刊23頁より
新聞を見てはじめて知ったが、佐賀の市民活動を応援するポータルサイトができていた。
■市民活動応援ポータルブログ
情報量も立ち上がったばかり?の割には多く、今後の発展に大いに期待がもてる。
最近の佐賀県の運営・企画するサイトはどれもレベルがあがって、オープンな情報交流を目指すものが増えた。とてもいいことだ。
つい数年前までは、私たちがオープンなサイトを企画しても、相手にされなかった現状からすれば、ずいぶんとよく変わった。
大体ブログ自体否定されていましたもんね。あるところでは。
県関係のサイトでブログをさきにいれたのは、佐賀県観光連盟のブログだと思っているが、いまでは、県流通課もブログをもっているし、ほかにも増えている。(と思う)
SNSを自治体が運営しようということもいわれはじめている中で、今度は、それをどう市民活動や、産業振興に具体的に活かすかが、課題になる。
ここまでは単に技術優先に場を作ることが目的で、これからが本当の課題解決のステージではないだろうか。
05年度の県民調査の結果が、26面に載っている。
暮らしの満足度に、
不満と答えた人が、全体の24%。なかでも不満の内訳で増えているのは、
産業と雇用だ。
新聞を見てはじめて知ったが、佐賀の市民活動を応援するポータルサイトができていた。
■市民活動応援ポータルブログ
情報量も立ち上がったばかり?の割には多く、今後の発展に大いに期待がもてる。
最近の佐賀県の運営・企画するサイトはどれもレベルがあがって、オープンな情報交流を目指すものが増えた。とてもいいことだ。
つい数年前までは、私たちがオープンなサイトを企画しても、相手にされなかった現状からすれば、ずいぶんとよく変わった。
大体ブログ自体否定されていましたもんね。あるところでは。
県関係のサイトでブログをさきにいれたのは、佐賀県観光連盟のブログだと思っているが、いまでは、県流通課もブログをもっているし、ほかにも増えている。(と思う)
SNSを自治体が運営しようということもいわれはじめている中で、今度は、それをどう市民活動や、産業振興に具体的に活かすかが、課題になる。
ここまでは単に技術優先に場を作ることが目的で、これからが本当の課題解決のステージではないだろうか。
05年度の県民調査の結果が、26面に載っている。
暮らしの満足度に、
不満と答えた人が、全体の24%。なかでも不満の内訳で増えているのは、
産業と雇用だ。
がばいばあちゃん課ができ、佐賀市中心市街地から映画館が消える
2006年8月22日(火)佐賀新聞朝刊23頁より
武雄市が、佐賀のがばいばあちゃんの特別ドラマのロケ地に決まり、武雄市役所は早速、がばいばあちゃん課なる組織を立ち上げた。武雄市はロケ地として、存分に武雄の魅力を伝えようという試みだ。なんという素早さ。
ドラマはフジテレビ系列で来年1月ゴールデンタイムで放映されるということで、佐賀のがばいばあちゃんが、本、映画、そしてテレビドラマと、どんどん全国の人に知られるようになっている。
いよいよ武雄ブームの到来か!?
嬉しいニュースの反面、佐賀市中心市街地にあった、佐賀セントラルという映画館が今月で閉鎖されるというニュースが掲載されている。
なんとも明暗をわけた形になっていて、こちらは残念だ。
小学校、中学校のころは、わざわざ多久市から列車で佐賀まで出て、映画を見ていた。
当時は友達同士で佐賀に映画を見にいくというのは、多久の私たちにとって少し大人びたイベントで、知らない土地の賑わいと、緊張感があって、とても新鮮だった。
アーケードの中に、どんどん亭というお好み焼き屋があり、そこでお好み焼きを食べるが流行った。多久から行くものはみんな行くものだから、偶然、どんどん亭で友達と出くわすことも。(笑)
もちろん、どんどん亭はとっくの昔に無い。
多久の私にとってもそれくらいの思い出がある映画館だったので、佐賀市民ならなおさら。
まあしょうがないなーという反面。中心市街地活性化と十数年来やっているが、どんどん状況は悪くなるばかりで、まったく好転しないのが残念だ。
武雄市が、佐賀のがばいばあちゃんの特別ドラマのロケ地に決まり、武雄市役所は早速、がばいばあちゃん課なる組織を立ち上げた。武雄市はロケ地として、存分に武雄の魅力を伝えようという試みだ。なんという素早さ。
ドラマはフジテレビ系列で来年1月ゴールデンタイムで放映されるということで、佐賀のがばいばあちゃんが、本、映画、そしてテレビドラマと、どんどん全国の人に知られるようになっている。
いよいよ武雄ブームの到来か!?
嬉しいニュースの反面、佐賀市中心市街地にあった、佐賀セントラルという映画館が今月で閉鎖されるというニュースが掲載されている。
なんとも明暗をわけた形になっていて、こちらは残念だ。
小学校、中学校のころは、わざわざ多久市から列車で佐賀まで出て、映画を見ていた。
当時は友達同士で佐賀に映画を見にいくというのは、多久の私たちにとって少し大人びたイベントで、知らない土地の賑わいと、緊張感があって、とても新鮮だった。
アーケードの中に、どんどん亭というお好み焼き屋があり、そこでお好み焼きを食べるが流行った。多久から行くものはみんな行くものだから、偶然、どんどん亭で友達と出くわすことも。(笑)
もちろん、どんどん亭はとっくの昔に無い。
多久の私にとってもそれくらいの思い出がある映画館だったので、佐賀市民ならなおさら。
まあしょうがないなーという反面。中心市街地活性化と十数年来やっているが、どんどん状況は悪くなるばかりで、まったく好転しないのが残念だ。
Uターン、Iターンの県職員が奮闘
2006年8月18日(金)佐賀新聞朝刊1面より
佐賀県庁は昨年から、県外からのUターン、Iターンの希望者を採用する枠を設けた。
それで採用された4名の奮闘のようすが、佐賀新聞の1面に掲載されている。
流通課の栗林さんは、以前は佐賀が嫌いだったと語り、しかしいまでは、佐賀にもいいものがたくさんあると、思えるとある。
佐賀ってまんざらじゃないよなーと思ったのは、個人的には、やはり幕末維新期の偉人たちの存在が大きい。蒼々たる人物群を知ると、佐賀って一体どんな国だったんだ!と驚いてしまう。
リアルに想像できないのが、やるせない思いがするが、日本一の技術力、日本一の海外通、日本一の軍事力。いや、ほんとうのところは知らんよ。でもそういう風に紹介されていたりするし、実際にそういう言説を知ると、そうだったかもと信じる。
ある人が、自分のルーツを知る事は、いまの自分の生き方に刺激を与えてくれる、という風なことをいった。
佐賀という風土、歴史、生活、人物、学問、教養、品格。
いいなーとつくづく思う。
という私も福岡大学の一年生のときは、佐賀出身というのが嫌だったのだけどね・・
あー、ダメのは商売っ気がないところ。もちろん他にもたくさんあるが
佐賀県庁は昨年から、県外からのUターン、Iターンの希望者を採用する枠を設けた。
それで採用された4名の奮闘のようすが、佐賀新聞の1面に掲載されている。
流通課の栗林さんは、以前は佐賀が嫌いだったと語り、しかしいまでは、佐賀にもいいものがたくさんあると、思えるとある。
佐賀ってまんざらじゃないよなーと思ったのは、個人的には、やはり幕末維新期の偉人たちの存在が大きい。蒼々たる人物群を知ると、佐賀って一体どんな国だったんだ!と驚いてしまう。
リアルに想像できないのが、やるせない思いがするが、日本一の技術力、日本一の海外通、日本一の軍事力。いや、ほんとうのところは知らんよ。でもそういう風に紹介されていたりするし、実際にそういう言説を知ると、そうだったかもと信じる。
ある人が、自分のルーツを知る事は、いまの自分の生き方に刺激を与えてくれる、という風なことをいった。
佐賀という風土、歴史、生活、人物、学問、教養、品格。
いいなーとつくづく思う。
という私も福岡大学の一年生のときは、佐賀出身というのが嫌だったのだけどね・・
あー、ダメのは商売っ気がないところ。もちろん他にもたくさんあるが
新聞を見ていたら・・武雄の大楠らへん
2006年7月13日(木)佐賀新聞朝刊25頁より
なみログなどやっているくせに、まともに佐賀新聞を読まないとダメだなという良い例。
25面に、武雄市若木町に移り住んだという夫婦の話が載っている。
あれ・・・どこかで見たような名前が。
何が書いてあるかというと、武雄市でインターネットを使って空家バンクを立ち上げ、物件情報を提供したりしている、循環たてもの研究塾。そこに関わる夫婦が、自分たちが武雄市外から武雄の田舎に移り住んだという話。
■空家バンク(循環たてもの研究塾運営)
話は飛ぶが、今日も武雄に行ってきました。
武雄が、PRベタという話を聞いたけど、佐賀県はどこをとってもPRベタという感じなので、日本のサッカーだけが決定力不足ではなくて、世界サッカー全体が決定力不足というのと議論は似ている。(ちがうか・・)
ちなみに、嬉野温泉と武雄温泉というキーワードが月にどれくらいひかれているか、というのをキーワードアドバイスツールで調べると、
嬉野温泉 15407
武雄温泉 4473
という結果に。客観的数字としては、嬉野温泉の1/3以下の検索率。
絶対数は推測なので、議論できないが、相対比としてはこの認識はもっていていいかもしれない。
ちなみに古湯温泉は、2424。
武雄あたりが活気がでてくると、佐賀県全体としても活気づくような感じがする。
なぜかというと、武雄ってなんだかんだいって、佐賀県の真中に位置していて、唐津に行くときは通らないが、有田、伊万里、鹿島、太良など西域に行くときは必ず通る要所だからだ。
かといって、市がなんでもいいから活気付けばいいというものでもなく、若木や武内あたりの自然はそのままであってほしいと思うし、温泉街ももうちっと情緒がある町づくりが必要だし、かといって、マックスバリュあたりの風景はこの2、3年で一変した感があるし。これはいいのか悪いのか・・
なかなか難しい地域だと思う。
なみログなどやっているくせに、まともに佐賀新聞を読まないとダメだなという良い例。
25面に、武雄市若木町に移り住んだという夫婦の話が載っている。
あれ・・・どこかで見たような名前が。
何が書いてあるかというと、武雄市でインターネットを使って空家バンクを立ち上げ、物件情報を提供したりしている、循環たてもの研究塾。そこに関わる夫婦が、自分たちが武雄市外から武雄の田舎に移り住んだという話。
■空家バンク(循環たてもの研究塾運営)
話は飛ぶが、今日も武雄に行ってきました。
武雄が、PRベタという話を聞いたけど、佐賀県はどこをとってもPRベタという感じなので、日本のサッカーだけが決定力不足ではなくて、世界サッカー全体が決定力不足というのと議論は似ている。(ちがうか・・)
ちなみに、嬉野温泉と武雄温泉というキーワードが月にどれくらいひかれているか、というのをキーワードアドバイスツールで調べると、
嬉野温泉 15407
武雄温泉 4473
という結果に。客観的数字としては、嬉野温泉の1/3以下の検索率。
絶対数は推測なので、議論できないが、相対比としてはこの認識はもっていていいかもしれない。
ちなみに古湯温泉は、2424。
武雄あたりが活気がでてくると、佐賀県全体としても活気づくような感じがする。
なぜかというと、武雄ってなんだかんだいって、佐賀県の真中に位置していて、唐津に行くときは通らないが、有田、伊万里、鹿島、太良など西域に行くときは必ず通る要所だからだ。
かといって、市がなんでもいいから活気付けばいいというものでもなく、若木や武内あたりの自然はそのままであってほしいと思うし、温泉街ももうちっと情緒がある町づくりが必要だし、かといって、マックスバリュあたりの風景はこの2、3年で一変した感があるし。これはいいのか悪いのか・・
なかなか難しい地域だと思う。
武雄市と玄海町
2006年7月12日(水)佐賀新聞朝刊1頁より
武雄市と玄海町。
二つの自治体について、地域活性化を模索する記事がある。
武雄市といえば、先日のW杯の日本VSクロアチア戦。武雄競輪場の大型ビジョンをつかったPVが行なわれた。気になる来場者数はというと、
1800人の若者を中心とした応援者が、武雄競輪場に駆けつけた。
なみログでも新聞紙面発表とともに、いち早く呼びかけたので、集客の足しになってればいいと思う。
それにしても、主催者は、800人くらいを想定していたというから、予想以上の集客だったという。
(800人というのもどこから来た数字かはさだかではないが、控えめだったのだろう)
さて、その武雄市だが、縁あって武雄へは毎週とまではいかないが、最近よく足を運ぶ。
先日は楼門の名物うどん屋で昼飯でも思って行った。ら、なぜか閉まっていた。平日のまっぴるまだぞ~。(あ、観光地だから平日閉まるのか・・)
非常に残念。
そういうのが、細かいところでひずみを生んでいるのか、大きなひずみとしては、楼門の真正面のホテルに、売却中か、閉鎖中か、白い張り紙が貼られているた。←これは見た目にも悪い印象を観光客に与える。
新聞記事によると、ホタル鑑賞の企画が、人気を呼んだということで、いちはやくそういう企画を打った旅館の行動力は素晴らしいと思うが、ホタルは年中行事ではないので、年に何本かそのような企画が必要だということ。
それから、玄海町だが、こっちは20面に「原発の町」の課題と題して、記事があり、人口減少、九電からの固定資産税の収入減がこれからも続くとったマイナス要因を見据えて、どう町を活性化させるかというような記事。
さてどうしたものかしらん。
※玄海町の花火大会は、佐賀県内で最大級だそうだ。さがファンのメルマガに書いてあった。
話は変わるが、8月のどこかの日曜日に、多久市の今出川でハヤ釣りをしようと思っている。だれか一緒に行きませんか?初心者大歓迎。ちなみにハヤのサイズは小ぶりです。文句を言わないように。
武雄市と玄海町。
二つの自治体について、地域活性化を模索する記事がある。
武雄市といえば、先日のW杯の日本VSクロアチア戦。武雄競輪場の大型ビジョンをつかったPVが行なわれた。気になる来場者数はというと、
1800人の若者を中心とした応援者が、武雄競輪場に駆けつけた。
なみログでも新聞紙面発表とともに、いち早く呼びかけたので、集客の足しになってればいいと思う。
それにしても、主催者は、800人くらいを想定していたというから、予想以上の集客だったという。
(800人というのもどこから来た数字かはさだかではないが、控えめだったのだろう)
さて、その武雄市だが、縁あって武雄へは毎週とまではいかないが、最近よく足を運ぶ。
先日は楼門の名物うどん屋で昼飯でも思って行った。ら、なぜか閉まっていた。平日のまっぴるまだぞ~。(あ、観光地だから平日閉まるのか・・)
非常に残念。
そういうのが、細かいところでひずみを生んでいるのか、大きなひずみとしては、楼門の真正面のホテルに、売却中か、閉鎖中か、白い張り紙が貼られているた。←これは見た目にも悪い印象を観光客に与える。
新聞記事によると、ホタル鑑賞の企画が、人気を呼んだということで、いちはやくそういう企画を打った旅館の行動力は素晴らしいと思うが、ホタルは年中行事ではないので、年に何本かそのような企画が必要だということ。
それから、玄海町だが、こっちは20面に「原発の町」の課題と題して、記事があり、人口減少、九電からの固定資産税の収入減がこれからも続くとったマイナス要因を見据えて、どう町を活性化させるかというような記事。
さてどうしたものかしらん。
※玄海町の花火大会は、佐賀県内で最大級だそうだ。さがファンのメルマガに書いてあった。
話は変わるが、8月のどこかの日曜日に、多久市の今出川でハヤ釣りをしようと思っている。だれか一緒に行きませんか?初心者大歓迎。ちなみにハヤのサイズは小ぶりです。文句を言わないように。
唐津市商店街の取り組み
2006年6月22日(木)佐賀新聞朝刊23頁より
JR唐津駅の北側に連なる中心商店街を活性化しようとする取り組みについて、記事が掲載されている。
どういう取り組みかというと、佐賀県と市と地域住民が連携して、商店街の商店の外観改装する事業だ。
どのように改装するかというと、大正・昭和初期風に改装し、レトロな商店街作りをするというもの。すでに2004年度と05年度に、計10店舗の外観を改装したとあり、今年度は、初めて行政の支援を得る取り組みとなるということだ。
唐津市の中心商店街のアーケードを数年前に何度か歩いたことがあるが、こじんまりとはしているが、路地が入り込んだりしていて、それなりに面白いアーケードだなと思った。
歩いている人は確かに少なかったが、駅から遠くないということもあり、ひょっとすると佐賀市の中心商店街よりも早く活性化するのではないかと期待を持った。
記事中に、かまぼこ店のコメントで、「お土産のかまぼこも並べたい」とあったが、日曜などは、どんどん商品を軒先に出して、賑わいを演出するのはいい手だと思う。
アルピノの駐車場もまあまあ広いし、福岡市内からも車で有料使うと40分くらいで来ると思う。上手く商店街の活性化作戦を練ることができれば、唐津市中心商店街は化けるかもしれないな、と思う。
それから、車走らせてでも食べに行きたい、フーズやスイーツを作って、広告作戦を展開するのもお忘れなく。(佐世保のさせぼバーガーみたいに)
JR唐津駅の北側に連なる中心商店街を活性化しようとする取り組みについて、記事が掲載されている。
どういう取り組みかというと、佐賀県と市と地域住民が連携して、商店街の商店の外観改装する事業だ。
どのように改装するかというと、大正・昭和初期風に改装し、レトロな商店街作りをするというもの。すでに2004年度と05年度に、計10店舗の外観を改装したとあり、今年度は、初めて行政の支援を得る取り組みとなるということだ。
唐津市の中心商店街のアーケードを数年前に何度か歩いたことがあるが、こじんまりとはしているが、路地が入り込んだりしていて、それなりに面白いアーケードだなと思った。
歩いている人は確かに少なかったが、駅から遠くないということもあり、ひょっとすると佐賀市の中心商店街よりも早く活性化するのではないかと期待を持った。
記事中に、かまぼこ店のコメントで、「お土産のかまぼこも並べたい」とあったが、日曜などは、どんどん商品を軒先に出して、賑わいを演出するのはいい手だと思う。
アルピノの駐車場もまあまあ広いし、福岡市内からも車で有料使うと40分くらいで来ると思う。上手く商店街の活性化作戦を練ることができれば、唐津市中心商店街は化けるかもしれないな、と思う。
それから、車走らせてでも食べに行きたい、フーズやスイーツを作って、広告作戦を展開するのもお忘れなく。(佐世保のさせぼバーガーみたいに)
佐賀の大学事情と町づくり
2006年6月17日(土)佐賀新聞1頁より
今日の佐賀新聞1面には、市街地の空洞化を見過せないと、県が推進本部を設置した記事が載っている。
川上副知事を座長に各本部長らで構成する「市街地再生推進本部」というのがそれだ。
記事によると、10月までに市街地再生指針を出して、県内各地での取り組みを支援するという。
写真は佐賀市中心商店街を視察する様子だったが、佐賀市だけに限らない取り組みのようだ。
唐津市もアーケード街があり、たしかに人どおりは少ないが、佐賀市よりはいくぶんマシのように思えたりもした。規模が佐賀市より小さいと思うので、そう感じただけで、1店舗あたりの売上ではさほどかわらなく低いのだろう。
そう書きながら思ったが、人どおりは確かに少ないが、中心商店街1店舗あたりの売上の推移はどうなのだろう?
例えば、来客数と直販売は減っているが、ネット通販が伸び始めた、という店舗があってもおかしくは無い。
バック屋とか洋服屋とか、陶磁器屋とか、スポーツ用品店などだ。
まあ、たぶんネット通販もそう本格的にやっているところは無いと思うので、期待はできないが、なんらかの形で生き残り策を模索している動きがあるかもしれない。そのあたりの売上構成などは見てみたい。直売り、カタログ通販、ネット通販、卸販売というような構成を。
さて、タイトルに、佐賀の大学事情と町づくりと書いた。
何をいいたいかというと、佐賀新聞を見てたら、大学や専門学校のオープンキャンパス、入試説明会の広告が載っていた。そろそろそういう時期なのかと思ったのと、福岡の学校が、佐賀新聞に広告を載せているので、佐賀ってほんとうに福岡のターゲットになっているんだなーと感じたからだ。
佐賀から福岡に出て、住んでいる人はもの凄く多いが、学生のときに福岡の学校に行き、そのまま福岡で就職という人も多いだろう。
私は福大を出て、佐賀に戻ってきたが、福岡でも就職活動をした。
佐賀から人が出て行くさまざまな要因があるが、高校卒業した若者を佐賀に留めておく場が無いのも、要因の大きな部分ではないか、と思った。
福岡の大名は私が大学のころも既に人通りが多かったが、なぜ多いのかの根本は、あの辺に専門学校がいくつかあったというのも大きな理由だろう。
佐賀市内に限って言えば、魅力ある学校をひとつでも多く作って、そこに人を集めるのも、町づくりのきっかけになるかもしれない。それは若者だけに限らなくてもいい。前に提案していた、高齢者大学などもいいだろう。
特色のある学校と、人の流れと、町づくりと。必然的に人が行き交うようなしくみづくりを考えてみてはどうか。
今日の佐賀新聞1面には、市街地の空洞化を見過せないと、県が推進本部を設置した記事が載っている。
川上副知事を座長に各本部長らで構成する「市街地再生推進本部」というのがそれだ。
記事によると、10月までに市街地再生指針を出して、県内各地での取り組みを支援するという。
写真は佐賀市中心商店街を視察する様子だったが、佐賀市だけに限らない取り組みのようだ。
唐津市もアーケード街があり、たしかに人どおりは少ないが、佐賀市よりはいくぶんマシのように思えたりもした。規模が佐賀市より小さいと思うので、そう感じただけで、1店舗あたりの売上ではさほどかわらなく低いのだろう。
そう書きながら思ったが、人どおりは確かに少ないが、中心商店街1店舗あたりの売上の推移はどうなのだろう?
例えば、来客数と直販売は減っているが、ネット通販が伸び始めた、という店舗があってもおかしくは無い。
バック屋とか洋服屋とか、陶磁器屋とか、スポーツ用品店などだ。
まあ、たぶんネット通販もそう本格的にやっているところは無いと思うので、期待はできないが、なんらかの形で生き残り策を模索している動きがあるかもしれない。そのあたりの売上構成などは見てみたい。直売り、カタログ通販、ネット通販、卸販売というような構成を。
さて、タイトルに、佐賀の大学事情と町づくりと書いた。
何をいいたいかというと、佐賀新聞を見てたら、大学や専門学校のオープンキャンパス、入試説明会の広告が載っていた。そろそろそういう時期なのかと思ったのと、福岡の学校が、佐賀新聞に広告を載せているので、佐賀ってほんとうに福岡のターゲットになっているんだなーと感じたからだ。
佐賀から福岡に出て、住んでいる人はもの凄く多いが、学生のときに福岡の学校に行き、そのまま福岡で就職という人も多いだろう。
私は福大を出て、佐賀に戻ってきたが、福岡でも就職活動をした。
佐賀から人が出て行くさまざまな要因があるが、高校卒業した若者を佐賀に留めておく場が無いのも、要因の大きな部分ではないか、と思った。
福岡の大名は私が大学のころも既に人通りが多かったが、なぜ多いのかの根本は、あの辺に専門学校がいくつかあったというのも大きな理由だろう。
佐賀市内に限って言えば、魅力ある学校をひとつでも多く作って、そこに人を集めるのも、町づくりのきっかけになるかもしれない。それは若者だけに限らなくてもいい。前に提案していた、高齢者大学などもいいだろう。
特色のある学校と、人の流れと、町づくりと。必然的に人が行き交うようなしくみづくりを考えてみてはどうか。
NPO雑感
2006年6月14日(水)佐賀新聞朝刊26頁より
佐賀県内で3年間でNPOがどれくらい増えたか。
なんと200近くあるそうだ。
ここでいうNPOは法人化されていない組織も含めて、どこかに登録されている団体を指すのだろう。それにしても200とは凄い。
ただ、よその県がどれくらいNPOがあるかというと、たぶん佐賀よりはどこも多いのではないかと思われるので、もっともっと増えることが望ましいことなのだろう。(人口比だと全国でNPOの組織率はどれくらいなのか、気になるところではある)
私も、2つ、いや3つ、NPOに所属している。ひとつが休業中の災害ボランティア、ひとつが、環境団体、もうひとつが中間支援団体。それから、4つ加えるとすると、佐賀文学なる同人会もNPOといっていいかも知れない。
という私の例をあげるまでもなく、佐賀市内のNPO団体の方々を見ていると結構ダブりがあるような気もする。あっちの団体、こっちの団体。まあ他人のことは言えないが。
だから、NPOを知っていてあれこれ活動している人と、まったく関わりの無い人との間には、通ずることのない距離があるような気がしてならない。
今後NPOをもっと活性化させようと思ったら、いままで関心のなかった人をどれだけ巻き込んでいけるかが、重要ではないだろうか。
新しくNPO団体つくって活動しようとしたときに、知っている顔ばかりという構図はよくある構図だ。
今朝の佐賀新聞のNPOに関する記事中に、NPO同士の足引っ張りについて触れた箇所があったが、そういう問題も起っているんだろうなあ、というくらいにしか思わない。
あえて、記事で書くほどのことでもないような気がするが、文章に紛れ込ませて、軽く牽制をしておいたほうがいいということなのだろう。
※個人的にはNPOの活動にまで力を注ぐ体力も気力もない毎日だ。頼まれている仕事の量が半端じゃないので、そっちを完ぺきにやることがすべてで、そのほかはしばらくはノータッチ。文学もあと回し。
佐賀県内で3年間でNPOがどれくらい増えたか。
なんと200近くあるそうだ。
ここでいうNPOは法人化されていない組織も含めて、どこかに登録されている団体を指すのだろう。それにしても200とは凄い。
ただ、よその県がどれくらいNPOがあるかというと、たぶん佐賀よりはどこも多いのではないかと思われるので、もっともっと増えることが望ましいことなのだろう。(人口比だと全国でNPOの組織率はどれくらいなのか、気になるところではある)
私も、2つ、いや3つ、NPOに所属している。ひとつが休業中の災害ボランティア、ひとつが、環境団体、もうひとつが中間支援団体。それから、4つ加えるとすると、佐賀文学なる同人会もNPOといっていいかも知れない。
という私の例をあげるまでもなく、佐賀市内のNPO団体の方々を見ていると結構ダブりがあるような気もする。あっちの団体、こっちの団体。まあ他人のことは言えないが。
だから、NPOを知っていてあれこれ活動している人と、まったく関わりの無い人との間には、通ずることのない距離があるような気がしてならない。
今後NPOをもっと活性化させようと思ったら、いままで関心のなかった人をどれだけ巻き込んでいけるかが、重要ではないだろうか。
新しくNPO団体つくって活動しようとしたときに、知っている顔ばかりという構図はよくある構図だ。
今朝の佐賀新聞のNPOに関する記事中に、NPO同士の足引っ張りについて触れた箇所があったが、そういう問題も起っているんだろうなあ、というくらいにしか思わない。
あえて、記事で書くほどのことでもないような気がするが、文章に紛れ込ませて、軽く牽制をしておいたほうがいいということなのだろう。
※個人的にはNPOの活動にまで力を注ぐ体力も気力もない毎日だ。頼まれている仕事の量が半端じゃないので、そっちを完ぺきにやることがすべてで、そのほかはしばらくはノータッチ。文学もあと回し。
CSO(市民社会組織)への助成金事業
2006年5月25日(木)佐賀新聞朝刊25頁より
今日の佐賀新聞朝刊の25面に、県が本年度のCSO(市民社会組織)への助成金事業で県内81団体への助成金交付が決まったいう記事が載っている。
地域づくり活動部門の団体を分野別にみると、
まちづくり団体が13、
学術・文化・芸術・スポーツが11、
子供の健全育成が8、
となっている。
気になるのは中見出しになっている、不正使用防止へ説明会・・・というくだり。
記事によると、同助成事業で2001から2003年度で川副町の民間団体が補助金を不正使用していたことが発覚したということで、県は今回、会計処理に関する説明会を行い注意を促すという。
・・・不正使用。。
補助金を不正使用して何をしてたのか、というのはかかれていないが、不正使用という言い方なので、経費に足が出たということではないだろう。
せっかくの市民活動の助成金事業。不正してまでやりたい事業であるならいざしらず、そこまでしてまで、助成金事業に手をあげる必要もないわけで、おかしなことにならないようにしてもらいたいものだ。
それからCSOつながりで紹介すると、24面には、嬉野市の「NPO法人まつり嬉野」の事務局長小池氏のコラムが掲載されている。
嬉野は観光地なので、まつり=観光客を呼ぶもの、という発想でまつりをプロデュースしている様子がよく伝わるコラムだ。
さらに、観光客だけが楽しむものであればいいのかという課題については、まつりを住民も参加しやすいものにすることにより、観光客と住民の交流を促進するものにしたということが書かれていて、観光客だけをターゲットにしたまつりからの脱却も考えてあるようだ。
なにはともあれ、温泉業界は5月中旬から6月、7月にかけては、1年で最も観光客が少なくなる時期のようなので、なんとかこの数ヶ月を乗り切る工夫が必要だ。
今日の佐賀新聞朝刊の25面に、県が本年度のCSO(市民社会組織)への助成金事業で県内81団体への助成金交付が決まったいう記事が載っている。
地域づくり活動部門の団体を分野別にみると、
まちづくり団体が13、
学術・文化・芸術・スポーツが11、
子供の健全育成が8、
となっている。
気になるのは中見出しになっている、不正使用防止へ説明会・・・というくだり。
記事によると、同助成事業で2001から2003年度で川副町の民間団体が補助金を不正使用していたことが発覚したということで、県は今回、会計処理に関する説明会を行い注意を促すという。
・・・不正使用。。
補助金を不正使用して何をしてたのか、というのはかかれていないが、不正使用という言い方なので、経費に足が出たということではないだろう。
せっかくの市民活動の助成金事業。不正してまでやりたい事業であるならいざしらず、そこまでしてまで、助成金事業に手をあげる必要もないわけで、おかしなことにならないようにしてもらいたいものだ。
それからCSOつながりで紹介すると、24面には、嬉野市の「NPO法人まつり嬉野」の事務局長小池氏のコラムが掲載されている。
嬉野は観光地なので、まつり=観光客を呼ぶもの、という発想でまつりをプロデュースしている様子がよく伝わるコラムだ。
さらに、観光客だけが楽しむものであればいいのかという課題については、まつりを住民も参加しやすいものにすることにより、観光客と住民の交流を促進するものにしたということが書かれていて、観光客だけをターゲットにしたまつりからの脱却も考えてあるようだ。
なにはともあれ、温泉業界は5月中旬から6月、7月にかけては、1年で最も観光客が少なくなる時期のようなので、なんとかこの数ヶ月を乗り切る工夫が必要だ。