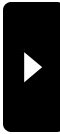スポンサーサイト
佐賀駅デイトスのスーパーが閉鎖に
2005年6月24日(金)佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀市の小売業をとりまくニュースは、明るいものは、大型ショッピングセンターや、大型家電ショップの進出など、大資本によるところが大きいが、県内地場もしくは、九州地場の小売のニュースとなると、とたんに暗いものが多くなる。
24日の佐賀新聞に佐賀駅デイトスに展開していた、「鮮ど市場」(本社熊本市)が25日で閉店とある。
売上の伸び悩みの原因は、駐車場不足によるもの。それから、車以外の買物客の購入単価が低かったことなどがあるという。
佐賀県は、一人一台車を持っている世帯も多く、車での買い物があたりまえ、おのずと郊外の大型ショッピングセンターなど、交通が便利で無料駐車場があるところに買物客が集まる。
ショッピングセンター側は、車で訪れた買物客に、センター内でカートを使って買い物をしてもらい、レジ精算後も買い物袋をカートに乗せたまま車のあるところまで運んでもらうよう、利便性を高めている。
スーパー内でカートを使った場合と、カートを使わなかった場合の購買金額に差があることは、スーパーマーケットの売れるしくみづくりを勉強すれば、初級の定説として教わるが、買い物をしている私たちは、カートでの買い物は、カートを使わないときよりも購買金額が多くなるなどは、いちいち考えたことはない。
なので、少し大きめのカートを使えるスーパーでは、いかに入口でカートに手を伸ばしてもらうかも、売上を上げる重要な作戦のひとつになっている。(カートを探さないとならなかったり、カートがとりにくかったりするのはもっての他なのだ)
スーパーマーケットの売れるしくみを少しだけ勉強したことがあるが、非常に興味深かった。もう少し本気になってスーパーマーケットの売れるしくみは勉強してみたかったが、Webをやる以上は、Webに専門化しなければならず、いまは勉強がストップしている。でも機会があればもっといろいろ知りたいと思う。
ECショップもリアルの店舗同様の競争力が求められている。
売れるしくみはリアル、バーチャルを問わない商売の原理原則のことであろうから、ECショップもいち早くその原理原則を知ったうえで取り組むところが、より成功を確実にしていくだろう。
じゃあ、その原理原則は何?といわれれば、私が知っているのは、立地をさておいたとして、小売業の戦略は、とどのつまり「商品戦略」と「価格戦略」に集約されること、価格戦略には「荒利ミックス」の戦略があるということくらいだ。
あることくらいだ、といっておきながら、少し書くと、商品戦略には、関連商品を買ってもらう、クロスセリングやアップセリングもある。単に単品商品をどうするかだけではない。
佐賀市の小売業をとりまくニュースは、明るいものは、大型ショッピングセンターや、大型家電ショップの進出など、大資本によるところが大きいが、県内地場もしくは、九州地場の小売のニュースとなると、とたんに暗いものが多くなる。
24日の佐賀新聞に佐賀駅デイトスに展開していた、「鮮ど市場」(本社熊本市)が25日で閉店とある。
売上の伸び悩みの原因は、駐車場不足によるもの。それから、車以外の買物客の購入単価が低かったことなどがあるという。
佐賀県は、一人一台車を持っている世帯も多く、車での買い物があたりまえ、おのずと郊外の大型ショッピングセンターなど、交通が便利で無料駐車場があるところに買物客が集まる。
ショッピングセンター側は、車で訪れた買物客に、センター内でカートを使って買い物をしてもらい、レジ精算後も買い物袋をカートに乗せたまま車のあるところまで運んでもらうよう、利便性を高めている。
スーパー内でカートを使った場合と、カートを使わなかった場合の購買金額に差があることは、スーパーマーケットの売れるしくみづくりを勉強すれば、初級の定説として教わるが、買い物をしている私たちは、カートでの買い物は、カートを使わないときよりも購買金額が多くなるなどは、いちいち考えたことはない。
なので、少し大きめのカートを使えるスーパーでは、いかに入口でカートに手を伸ばしてもらうかも、売上を上げる重要な作戦のひとつになっている。(カートを探さないとならなかったり、カートがとりにくかったりするのはもっての他なのだ)
スーパーマーケットの売れるしくみを少しだけ勉強したことがあるが、非常に興味深かった。もう少し本気になってスーパーマーケットの売れるしくみは勉強してみたかったが、Webをやる以上は、Webに専門化しなければならず、いまは勉強がストップしている。でも機会があればもっといろいろ知りたいと思う。
ECショップもリアルの店舗同様の競争力が求められている。
売れるしくみはリアル、バーチャルを問わない商売の原理原則のことであろうから、ECショップもいち早くその原理原則を知ったうえで取り組むところが、より成功を確実にしていくだろう。
じゃあ、その原理原則は何?といわれれば、私が知っているのは、立地をさておいたとして、小売業の戦略は、とどのつまり「商品戦略」と「価格戦略」に集約されること、価格戦略には「荒利ミックス」の戦略があるということくらいだ。
あることくらいだ、といっておきながら、少し書くと、商品戦略には、関連商品を買ってもらう、クロスセリングやアップセリングもある。単に単品商品をどうするかだけではない。
佐賀県ベンチャー交流ネットワーク
2005年6月4日佐賀新聞朝刊佐賀経済面より
佐賀県ベンチャーネットワーク交流会が、6月2日佐賀市のはがくれ荘であった。
100名以上の参加者があり、第一回目の定例会だけに熱気のあるものだった。
私も、さがファンの事業展開とういことで、テーマ別ミーティングのプレゼンテーターとして説明を行なった。
テーマ別ミーティングに入る前に、何を話そうかと思っていたら、さがファンのことを話しても仕方がないと思い、佐賀のファンにどのようにしてネット上で集まってもらうかというようなことを話したいと思った。
そもそも、さがファンとは何か。これについては、オープン前夜のブログでも書いている。
さがファンの特徴はいくつかあげられるが、まず佐賀が好きな人、佐賀に関心がある人が、県産品を買いたいと思ったときに、商品が簡単に探せて、ネットで買うことができるのが特徴だ。
ただそれだけでは、企画人の私の考えをすべては説明してくれない。今日は少しそのことにも触れておきたい。
■さがファンとは何か。
【さがファンとは佐賀のファンのためのサービスの総体であり、サービス提供のしくみである。】
さがファンはあくまで佐賀のファンの満足を満たすものでなければならない。そのために、さがファンがおもてなしをするのである。
昨日、東京のある方からオープンの励ましのメールをもらった。その中で書かれていたことは、「満足体験」を提供できるよう頑張ってください、というものだった。
「満足体験」・・・どうだろうか?
佐賀県のあらゆるサイト。情報系、ECショップ、自治体、満足体験を与えていますか? 満足体験を与えていないなと思ったら、満足体験とは何かを考えて、ぜひ取り組みましょう!
もちろん、さがファンだって、これからである。
さがファンは、全国の佐賀が好きなファンひとりひとりと、ネット上で満足体験を分かち合うものにしたいと思う。そしてそういう試みに参加したいと思う人たちとともに佐賀を盛り上げていきたいと思う。
さがファンというコミュニケーションの場の創造は、我々のチームだけが、無い頭をひねって取り組むようなちっぽけなものではないのだから。
佐賀県ベンチャーネットワーク交流会が、6月2日佐賀市のはがくれ荘であった。
100名以上の参加者があり、第一回目の定例会だけに熱気のあるものだった。
私も、さがファンの事業展開とういことで、テーマ別ミーティングのプレゼンテーターとして説明を行なった。
テーマ別ミーティングに入る前に、何を話そうかと思っていたら、さがファンのことを話しても仕方がないと思い、佐賀のファンにどのようにしてネット上で集まってもらうかというようなことを話したいと思った。
そもそも、さがファンとは何か。これについては、オープン前夜のブログでも書いている。
さがファンの特徴はいくつかあげられるが、まず佐賀が好きな人、佐賀に関心がある人が、県産品を買いたいと思ったときに、商品が簡単に探せて、ネットで買うことができるのが特徴だ。
ただそれだけでは、企画人の私の考えをすべては説明してくれない。今日は少しそのことにも触れておきたい。
■さがファンとは何か。
【さがファンとは佐賀のファンのためのサービスの総体であり、サービス提供のしくみである。】
さがファンはあくまで佐賀のファンの満足を満たすものでなければならない。そのために、さがファンがおもてなしをするのである。
昨日、東京のある方からオープンの励ましのメールをもらった。その中で書かれていたことは、「満足体験」を提供できるよう頑張ってください、というものだった。
「満足体験」・・・どうだろうか?
佐賀県のあらゆるサイト。情報系、ECショップ、自治体、満足体験を与えていますか? 満足体験を与えていないなと思ったら、満足体験とは何かを考えて、ぜひ取り組みましょう!
もちろん、さがファンだって、これからである。
さがファンは、全国の佐賀が好きなファンひとりひとりと、ネット上で満足体験を分かち合うものにしたいと思う。そしてそういう試みに参加したいと思う人たちとともに佐賀を盛り上げていきたいと思う。
さがファンというコミュニケーションの場の創造は、我々のチームだけが、無い頭をひねって取り組むようなちっぽけなものではないのだから。
情報発信は収益の設計もセットで
2005年5月18日佐賀新聞朝刊9頁「ロビー」より
昨日18日の18頁にも掲載されていた、電通最高顧問成田氏の講演について、今朝の新聞ではインタビュー記事が掲載されている。
成田氏は母校である旧制佐賀高校の記念行事に合わせて佐賀を訪れ、5月16日に佐賀市の弘学館中学・高校で生徒を前に講演を行なった。
今朝の記事の中では、ふるさとの良さを発見し、創造的な情報発信に取り組むべきだ、と話し、有田陶器市が年に1回というのはもったいない、という意見もある。
(そういわれると、有田陶器市が年1回ではなく、2回あってもいいかも、と思ってしまう。が、そう簡単ではないんだろうな。。)
話のポイントは、創造的な情報発信をということで、ネット事業をやるものにとっては、情報発信がきちんと収益の設計されているかということも大事だと思ってしまう。
もちろん情報を発信して認知が進めばおのずとさまざまな収益を生み出すサービスが考えられるので、収益のことはあとでもいいが、収益の設計が無視されたままだとどうしようもない。
情報発信のアイデアを考えるのとおなじくらいの脳みそを使って、いや、それ以上の脳みそを使って、収益の設計をしないとならないだろう。
昨日18日の18頁にも掲載されていた、電通最高顧問成田氏の講演について、今朝の新聞ではインタビュー記事が掲載されている。
成田氏は母校である旧制佐賀高校の記念行事に合わせて佐賀を訪れ、5月16日に佐賀市の弘学館中学・高校で生徒を前に講演を行なった。
今朝の記事の中では、ふるさとの良さを発見し、創造的な情報発信に取り組むべきだ、と話し、有田陶器市が年に1回というのはもったいない、という意見もある。
(そういわれると、有田陶器市が年1回ではなく、2回あってもいいかも、と思ってしまう。が、そう簡単ではないんだろうな。。)
話のポイントは、創造的な情報発信をということで、ネット事業をやるものにとっては、情報発信がきちんと収益の設計されているかということも大事だと思ってしまう。
もちろん情報を発信して認知が進めばおのずとさまざまな収益を生み出すサービスが考えられるので、収益のことはあとでもいいが、収益の設計が無視されたままだとどうしようもない。
情報発信のアイデアを考えるのとおなじくらいの脳みそを使って、いや、それ以上の脳みそを使って、収益の設計をしないとならないだろう。
佐賀の焼酎、酒と原産地呼称管理
2005年4月26日佐賀新聞20頁より
佐賀県が創設した「原産地呼称管理制度」の第一弾認定品に選出された純米酒と焼酎38の銘柄の出荷が始まった。県内産原料を100%使い、味や香りも厳選された酒だ。
原産地呼称制度とは、原産地表示の信頼を高め、味や香りにお墨付きを与えて販路拡大を狙うのが目的とある。
本格焼酎ブームで鹿児島、熊本、宮崎、大分、沖縄などはかつてないほど潤っているようだが、佐賀は九州で一番、焼酎の消費量が少ない県で、全国区になった焼酎はあまり聞かない。
しかし、実は良い焼酎が佐賀にもあり、なかなか手に入らないものもあるようだ。
さて、PRについて。
県が制度を整えた。メーカーが認知を進める。そのような役割分担のようだ。
インターネット上でどれくらい佐賀の酒、焼酎が露出しているかというと、戦略的な取り組みがなされていないので、ほとんどない。
全国を見ても県が積極的にネットでのPRをするのは聞いたことがないが、佐賀県は他県と同じようにしていてもだめなんじゃないかと思う。
県に頼ってしまってはダメかも知れないが、県はネットにも力を入れていくと宣言しているはずなので、県の地場産業の浮揚のために、ぜひともネット戦略を立ててもらいたいものだ。
佐賀県が創設した「原産地呼称管理制度」の第一弾認定品に選出された純米酒と焼酎38の銘柄の出荷が始まった。県内産原料を100%使い、味や香りも厳選された酒だ。
原産地呼称制度とは、原産地表示の信頼を高め、味や香りにお墨付きを与えて販路拡大を狙うのが目的とある。
本格焼酎ブームで鹿児島、熊本、宮崎、大分、沖縄などはかつてないほど潤っているようだが、佐賀は九州で一番、焼酎の消費量が少ない県で、全国区になった焼酎はあまり聞かない。
しかし、実は良い焼酎が佐賀にもあり、なかなか手に入らないものもあるようだ。
さて、PRについて。
県が制度を整えた。メーカーが認知を進める。そのような役割分担のようだ。
インターネット上でどれくらい佐賀の酒、焼酎が露出しているかというと、戦略的な取り組みがなされていないので、ほとんどない。
全国を見ても県が積極的にネットでのPRをするのは聞いたことがないが、佐賀県は他県と同じようにしていてもだめなんじゃないかと思う。
県に頼ってしまってはダメかも知れないが、県はネットにも力を入れていくと宣言しているはずなので、県の地場産業の浮揚のために、ぜひともネット戦略を立ててもらいたいものだ。
大型店の雇用環境と中心商店街
2005年4月18日佐賀新聞朝刊2頁より
ろんだん佐賀で、商店街活性化について、その意義にふれた部分があり、ここ数年考えていたことが書かれてある。その部分を流用する。
郊外型の店舗群の多くは、大型店やフランチャイズなどの出店で、どこも似たような街並みとなり、地域性を感じることはない。それらは、雇用の確保にはなっているかも知れないが、多くは外部資本であり、明らかにお金は地域から逃げているはずだ。それは、地域でお金が循環しなくなる要因でもあり、時間の経過とともにボディーブローのように効いてくるのではないかと心配される。
この中で大事な要素が二つある。ひとつは、大型店が雇用の受け皿になっているということ。
二つ目は、時間の経過とともにボディーブローのように効いてくる心配があるということ。
とくに、雇用の受け皿になっているというのは、地方に生活するものにとって切実な問題だ。
地場に雇用の受け皿がないので、県外からの企業の誘致を行なう。大型店の出店がなかったら、働く場所に困ったという人も多いだろう。雇用を確保するというのは、何を置いても大事なことだと思う。
雇用環境は欲しい。でもあまり大型店ばかり進出してきてもらっては、中心商店街がさらに衰退する。ジレンマがある。
ろんだん佐賀で、商店街活性化について、その意義にふれた部分があり、ここ数年考えていたことが書かれてある。その部分を流用する。
郊外型の店舗群の多くは、大型店やフランチャイズなどの出店で、どこも似たような街並みとなり、地域性を感じることはない。それらは、雇用の確保にはなっているかも知れないが、多くは外部資本であり、明らかにお金は地域から逃げているはずだ。それは、地域でお金が循環しなくなる要因でもあり、時間の経過とともにボディーブローのように効いてくるのではないかと心配される。
この中で大事な要素が二つある。ひとつは、大型店が雇用の受け皿になっているということ。
二つ目は、時間の経過とともにボディーブローのように効いてくる心配があるということ。
とくに、雇用の受け皿になっているというのは、地方に生活するものにとって切実な問題だ。
地場に雇用の受け皿がないので、県外からの企業の誘致を行なう。大型店の出店がなかったら、働く場所に困ったという人も多いだろう。雇用を確保するというのは、何を置いても大事なことだと思う。
雇用環境は欲しい。でもあまり大型店ばかり進出してきてもらっては、中心商店街がさらに衰退する。ジレンマがある。
損害保険ジャパンが佐賀市にコールセンター
2005年4月12日佐賀新聞朝刊1頁より
今朝の1面は、「損保がコールセンター」という見出しで、東京本社の損害保険ジャパンが、佐賀市のどん3の森にコールセンターを開設するというニュースが掲載してある。
損保ジャパンのページはこちら
新聞によると、来年4月以降の操業を予定し、当初約300人、2007年度末には約700人の雇用を見込むとある。
進出方法は、損保ジャパン以外の会社が建設するビルを県が15年間の長期賃貸契約で借り上げ、ビルの一部を損保ジャパンに有料で貸し出すという。
佐賀市は従業員の給与取得だけで10年間で122億円の経済効果を見込むとある。
コールセンターの運営については市場通信サイトが詳しいので紹介しておく。
県立病院の移転といい、損保ジャパンの誘致といい、どん3の森に動きが出てきた。
今朝の1面は、「損保がコールセンター」という見出しで、東京本社の損害保険ジャパンが、佐賀市のどん3の森にコールセンターを開設するというニュースが掲載してある。
損保ジャパンのページはこちら
新聞によると、来年4月以降の操業を予定し、当初約300人、2007年度末には約700人の雇用を見込むとある。
進出方法は、損保ジャパン以外の会社が建設するビルを県が15年間の長期賃貸契約で借り上げ、ビルの一部を損保ジャパンに有料で貸し出すという。
佐賀市は従業員の給与取得だけで10年間で122億円の経済効果を見込むとある。
コールセンターの運営については市場通信サイトが詳しいので紹介しておく。
県立病院の移転といい、損保ジャパンの誘致といい、どん3の森に動きが出てきた。
佐賀のミュージカル活動
2005年4月10日佐賀新聞朝刊17頁より
ティーンズミュージカルSAGAと鳥栖の子どもミュージカルの活動のことが取り上げられている。
両方とも、佐賀の演劇のすそ野を広げる試みとして注目をされている活動だ。
ティーンズミュージカルSAGAについては、代表を務める栗原氏と以前子どもと芸術についてトークセッションを行ったこともあり、陰ながら注目をしている。
両団体とも、ミュージカルの総合芸術性を強調し、各分野の才能を伸ばすことはもちろんだが、子どもの情操教育にも役に立つということのようだ。
佐賀の演劇のレベルは全国的にはまだまだ低いかもしれないが、誰かが声をあげて取り組みをはじめなければ3年後も5年後も変わらないままであろう。
そういう意味においても、この2つの団体の取り組みは価値の高いものだと思う。
私ももうちょっと仕事が落ち着いたら、文学で佐賀を盛り上げる活動をしたいと思う。しばしお待ちあれ。
ティーンズミュージカルSAGAと鳥栖の子どもミュージカルの活動のことが取り上げられている。
両方とも、佐賀の演劇のすそ野を広げる試みとして注目をされている活動だ。
ティーンズミュージカルSAGAについては、代表を務める栗原氏と以前子どもと芸術についてトークセッションを行ったこともあり、陰ながら注目をしている。
両団体とも、ミュージカルの総合芸術性を強調し、各分野の才能を伸ばすことはもちろんだが、子どもの情操教育にも役に立つということのようだ。
佐賀の演劇のレベルは全国的にはまだまだ低いかもしれないが、誰かが声をあげて取り組みをはじめなければ3年後も5年後も変わらないままであろう。
そういう意味においても、この2つの団体の取り組みは価値の高いものだと思う。
私ももうちょっと仕事が落ち着いたら、文学で佐賀を盛り上げる活動をしたいと思う。しばしお待ちあれ。
書店の会員制ポイントカード
2005年3月27日佐賀新聞朝刊14頁「ブックびじねす」より
ブックビジネスというコーナーは全国共通の記事の中で、書店の会員制ポイントカードについて書かれている。全国展開する三省堂がこの度導入したということで、再販制度の関係もあって、賛否が分かれているという。
書店の会員制ポイントカードの書店側のメリットとしたら、記事にもあるように、アマゾンに代表されるように、ネット通販ではあたりまえに個人の購買履歴を収集し、ユーザー自身が購入履歴を知ることができたり、関連本をレコメンドしたりすることで、運営側、ユーザー側、どちらにとってもなくてはならない機能となっている。
それに比べて、会員制カードの導入が進まなかったリアルの書店は、誰がどのような商品をいつ、買ったかというような、スーパーマーケットなどではカードとPOSレジをつかって当たり前にやっている情報の収集と分析をやっていなかった。
もちろん、書店側としては、どのような本が売れているかを知ることのできるツールとなる。
年齢別、性別、種別、価格帯。地域、来店時間や曜日まで、さまざまな統計がとれる。
カードリーダーがついた、本の検索端末が登場し、カードを差し込むと個人の購入履歴を見ることができたり、趣味嗜好を判断しておすすめの本を案内してくれるといったこともできるだろう。
どのようなサービスが可能か、今後の展開に期待したい。
ブックビジネスというコーナーは全国共通の記事の中で、書店の会員制ポイントカードについて書かれている。全国展開する三省堂がこの度導入したということで、再販制度の関係もあって、賛否が分かれているという。
書店の会員制ポイントカードの書店側のメリットとしたら、記事にもあるように、アマゾンに代表されるように、ネット通販ではあたりまえに個人の購買履歴を収集し、ユーザー自身が購入履歴を知ることができたり、関連本をレコメンドしたりすることで、運営側、ユーザー側、どちらにとってもなくてはならない機能となっている。
それに比べて、会員制カードの導入が進まなかったリアルの書店は、誰がどのような商品をいつ、買ったかというような、スーパーマーケットなどではカードとPOSレジをつかって当たり前にやっている情報の収集と分析をやっていなかった。
もちろん、書店側としては、どのような本が売れているかを知ることのできるツールとなる。
年齢別、性別、種別、価格帯。地域、来店時間や曜日まで、さまざまな統計がとれる。
カードリーダーがついた、本の検索端末が登場し、カードを差し込むと個人の購入履歴を見ることができたり、趣味嗜好を判断しておすすめの本を案内してくれるといったこともできるだろう。
どのようなサービスが可能か、今後の展開に期待したい。
佐賀県産農産物の中国展開
2005年3月3日佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀市のマリトピアで、県産農産物輸出促進セミナーが行なわれたとある。
いまは国内青果物で中国に輸出できる品目がリンゴとナシに限られているが、農水省はイチゴなど12品目の輸出の許可を求めているということで、経済発展が著しい中国に照準を合わせたセミナーだ。
貿易コンサルティングのアジアネット代表の田中氏の言葉が掲載されていて、「日持ちが短いものを輸出できれば勝てる。佐賀はその点でメリットがある。」と地理的優位性を強調した。
日持ちが短いものが、競争力があるという発想が意外な感じを受けたが、日持ちが短いものはそれだけ距離の近さを最大限に差別化要因として使えるということである。
佐賀以外の産地との競争になったとき、佐賀のものは鮮度が保たれているが、他の地域は輸送時間がネックになるということか。
日持ちの短いものといえばどのようなものがあるのか詳しくはわからないが、イチゴなどはそれに当てはまるだろう。
イチゴといえばケーキ用途の需要が多いはず。中国でケーキを食する需要が増えれば、おのずとイチゴの需要も増えるだろう。クリスマスにケーキが売れるのかどうか知らないが、そういうイベントから仕掛けていけばいいのかもしれない。中国の文化に合わせたものとして。
われわれは国内ネットユーザー向けにこの5月に「さがファン」というオンラインショッピングモールを開設する予定だ。
佐賀市のマリトピアで、県産農産物輸出促進セミナーが行なわれたとある。
いまは国内青果物で中国に輸出できる品目がリンゴとナシに限られているが、農水省はイチゴなど12品目の輸出の許可を求めているということで、経済発展が著しい中国に照準を合わせたセミナーだ。
貿易コンサルティングのアジアネット代表の田中氏の言葉が掲載されていて、「日持ちが短いものを輸出できれば勝てる。佐賀はその点でメリットがある。」と地理的優位性を強調した。
日持ちが短いものが、競争力があるという発想が意外な感じを受けたが、日持ちが短いものはそれだけ距離の近さを最大限に差別化要因として使えるということである。
佐賀以外の産地との競争になったとき、佐賀のものは鮮度が保たれているが、他の地域は輸送時間がネックになるということか。
日持ちの短いものといえばどのようなものがあるのか詳しくはわからないが、イチゴなどはそれに当てはまるだろう。
イチゴといえばケーキ用途の需要が多いはず。中国でケーキを食する需要が増えれば、おのずとイチゴの需要も増えるだろう。クリスマスにケーキが売れるのかどうか知らないが、そういうイベントから仕掛けていけばいいのかもしれない。中国の文化に合わせたものとして。
われわれは国内ネットユーザー向けにこの5月に「さがファン」というオンラインショッピングモールを開設する予定だ。
故郷からの縁故市場
2005年2月17日佐賀新聞朝刊7頁より
東京の米穀店「スズノブ」の西島社長が、「さが21水田農業パワーアップ運動推進協議会」で講演を行い、売れるコメづくりへ向けた話をしている。
東京ではコメが売れなくなってきているという。故郷からの縁故米が大量に入ってきているのがその影響のひとつだそうだ。
私も大学が福岡で独り暮しをしていたとき、おふくろの実家が農家だったため、コメを送ってもらっていた。
そういう学生や独身の独り暮しに送られる故郷の米は相当数にのぼるのだろう。
それから、こだわり米を消費する家庭が増えてきたので、一般にスーパーで売られている米にも産地米だったり、こだわり製法だったりするものがあたりまえになってきたとあり、普通のお米ではもう売れなくなってきているということのようだ。
氏いわく、さらに突っ込んだ話として、東京は情報があふれ、佐賀のわたしたちが知らないことも消費者は知っているといい、生産者も研究を怠ってはいけないという。
それにしても、縁故米の市場が馬鹿にならないほどあるというのは、どういうことだろうか?米以外ではどのような産品が縁故で動いているのか、ちょっと興味がある。みかんなどのくだものは、縁故でかなり動いているような気がするが。
東京の米穀店「スズノブ」の西島社長が、「さが21水田農業パワーアップ運動推進協議会」で講演を行い、売れるコメづくりへ向けた話をしている。
東京ではコメが売れなくなってきているという。故郷からの縁故米が大量に入ってきているのがその影響のひとつだそうだ。
私も大学が福岡で独り暮しをしていたとき、おふくろの実家が農家だったため、コメを送ってもらっていた。
そういう学生や独身の独り暮しに送られる故郷の米は相当数にのぼるのだろう。
それから、こだわり米を消費する家庭が増えてきたので、一般にスーパーで売られている米にも産地米だったり、こだわり製法だったりするものがあたりまえになってきたとあり、普通のお米ではもう売れなくなってきているということのようだ。
氏いわく、さらに突っ込んだ話として、東京は情報があふれ、佐賀のわたしたちが知らないことも消費者は知っているといい、生産者も研究を怠ってはいけないという。
それにしても、縁故米の市場が馬鹿にならないほどあるというのは、どういうことだろうか?米以外ではどのような産品が縁故で動いているのか、ちょっと興味がある。みかんなどのくだものは、縁故でかなり動いているような気がするが。
キリン一番搾りといかしゅうまいと懐郷マーケティング
2005年1月7日佐賀新聞朝刊7頁より
なみログにもってこいのニュースが掲載してある。
キリン一番搾りのCMに唐津市呼子町の名物いかしゅうまいが登場する。
二月中旬から約二ヶ月間の放映らしい。
どういう経緯でいかしゅうまいが選ばれたのかは不明だが、いかしゅうまいを売り込む絶好のチャンスが到来したといえるだろう。
記事によると99年には、ざる豆腐が登場しているとあり、佐賀の特産品は今回で二回目。
ざる豆腐も唐津で、いまでは佐賀市内の居酒屋でもざる豆腐という名称だったり似たような名前だったりするが、ざるに入った豆腐のメニューがある。
全国のみなさん、呼子のいかしゅうまいが出てくるCMを楽しみにしてください。
このようなご当地CMはこの頃増えてきたような気がする。
以前、北海道物産展が東京で流行る理由のひとつに、北海道から東京へ移り住んだ方たちが多いので、北海道物産展が人気があるという文章を目にしたことがある。
そう考えると、福岡と佐賀の関係を考えると、このような推測も成り立たないだろうか?福岡市に移り住んだ佐賀県民が増えるにしたがって、佐賀関連の情報に対するニーズの高まりがある。ご当地マーケティングというより、懐郷マーケティングだ。
なみログにもってこいのニュースが掲載してある。
キリン一番搾りのCMに唐津市呼子町の名物いかしゅうまいが登場する。
二月中旬から約二ヶ月間の放映らしい。
どういう経緯でいかしゅうまいが選ばれたのかは不明だが、いかしゅうまいを売り込む絶好のチャンスが到来したといえるだろう。
記事によると99年には、ざる豆腐が登場しているとあり、佐賀の特産品は今回で二回目。
ざる豆腐も唐津で、いまでは佐賀市内の居酒屋でもざる豆腐という名称だったり似たような名前だったりするが、ざるに入った豆腐のメニューがある。
全国のみなさん、呼子のいかしゅうまいが出てくるCMを楽しみにしてください。
このようなご当地CMはこの頃増えてきたような気がする。
以前、北海道物産展が東京で流行る理由のひとつに、北海道から東京へ移り住んだ方たちが多いので、北海道物産展が人気があるという文章を目にしたことがある。
そう考えると、福岡と佐賀の関係を考えると、このような推測も成り立たないだろうか?福岡市に移り住んだ佐賀県民が増えるにしたがって、佐賀関連の情報に対するニーズの高まりがある。ご当地マーケティングというより、懐郷マーケティングだ。
佐賀空港の貨物便
2004年12月29日佐賀新聞朝刊1頁より
今年もあとわずかになった。
佐賀空港を使った夜間の貨物便が、貨物専用機になるというニュースが掲載されている。
いつからかというと、2006年1月からということなので、一年先の話なのだが、興味あるニュースだ。
羽田佐賀間で就航している夜間貨物便は、現在中型旅客ジェット機の貨物室を使っていた。
7月に就航を始めてから、12月で取り扱い量が倍に増え、積載スペースも8、9割は埋まっているという。
また名古屋空港への便も新たに開設されるということで、名古屋空港経由の国際貨物便の輸送が可能になるとある。
貨物拠点としての利便性が高まり、佐賀空港が大きく発展する可能性が出てきた。
今年もあとわずかになった。
佐賀空港を使った夜間の貨物便が、貨物専用機になるというニュースが掲載されている。
いつからかというと、2006年1月からということなので、一年先の話なのだが、興味あるニュースだ。
羽田佐賀間で就航している夜間貨物便は、現在中型旅客ジェット機の貨物室を使っていた。
7月に就航を始めてから、12月で取り扱い量が倍に増え、積載スペースも8、9割は埋まっているという。
また名古屋空港への便も新たに開設されるということで、名古屋空港経由の国際貨物便の輸送が可能になるとある。
貨物拠点としての利便性が高まり、佐賀空港が大きく発展する可能性が出てきた。
「角の文房具屋」ではいけない
2004年12月11日佐賀新聞朝刊7頁より
「角の文房具屋」ではいけない。
なぜかというと屋号すら覚えられていない。その程度の認識でしかない商売は続かない。
厳しい意見だと思う。
伊万里・有田政経セミナーで講師の中村氏(日本福祉大助教授)が言った講演内容の一部だ。
「角の文房具屋」と、屋号を言わずとも通じた時代は、どこかわきあいあいとした雰囲気がある。けっして悪くないと思うのだが、冒頭のように解説されると、なるほどそういうものかと思ってしまう。
たしかに、ラーメン屋があったとして、「ラーメン屋です」と言って出前を配達するのと、「○○軒です」と言って出前を運ぶのでは、違いがある。
なるほど、そういう視点でお店を見てみると、屋号を聞けば何屋か分かるお店は、県内産業の各ジャンルにそう多くないのに気が付く。
全国に屋号が知れ渡るようになれば、一流企業の証しなのであろう。
「角の文房具屋」ではいけない。
なぜかというと屋号すら覚えられていない。その程度の認識でしかない商売は続かない。
厳しい意見だと思う。
伊万里・有田政経セミナーで講師の中村氏(日本福祉大助教授)が言った講演内容の一部だ。
「角の文房具屋」と、屋号を言わずとも通じた時代は、どこかわきあいあいとした雰囲気がある。けっして悪くないと思うのだが、冒頭のように解説されると、なるほどそういうものかと思ってしまう。
たしかに、ラーメン屋があったとして、「ラーメン屋です」と言って出前を配達するのと、「○○軒です」と言って出前を運ぶのでは、違いがある。
なるほど、そういう視点でお店を見てみると、屋号を聞けば何屋か分かるお店は、県内産業の各ジャンルにそう多くないのに気が付く。
全国に屋号が知れ渡るようになれば、一流企業の証しなのであろう。
深川製磁が東京にブランド研究所設立
2004年11月30日佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀県有田町にある陶磁器会社、深川製磁が東京・代官山にブランド研究所を設立するとある。
研究所の正式名称は、「ブランド・マネジメント部」。
専属の女性社員二名を配置し、12月1日から本格的に業務を始める。
記事によると、ブランド・マネジメント部は東京営業所から独立した組織として機能するようで、全国の百貨店に和食器の活かし方を提案。新商品の企画も意見交換をしていくとある。
ブランド・マネジメントという意味合い以上に、マーケティングの意味合いが強いようだ。もちろんブランド戦略はマーケティング戦略の中のひとつにすぎない。
マーティング研究所ではなく、ブランド・マネジメント部とフォーカスを絞り込んであるところに、会社としてかにブランドに力を注いでいるかがわかる。
何でもいいから売れるための仕組みを作ろうなどという、単なる目先だけのことではないのだ。
マーケティングを考えるときにブランドは考え方が難しく、広義のマーケティング戦略の中にはブランド戦略はもちろん入ると思うが、狭義のマーケティング戦略に固執すると、ブランドを構築できないこともあるだろう。うむむ、ブランドは難しい。。
深川製磁サイト
佐賀県有田町にある陶磁器会社、深川製磁が東京・代官山にブランド研究所を設立するとある。
研究所の正式名称は、「ブランド・マネジメント部」。
専属の女性社員二名を配置し、12月1日から本格的に業務を始める。
記事によると、ブランド・マネジメント部は東京営業所から独立した組織として機能するようで、全国の百貨店に和食器の活かし方を提案。新商品の企画も意見交換をしていくとある。
ブランド・マネジメントという意味合い以上に、マーケティングの意味合いが強いようだ。もちろんブランド戦略はマーケティング戦略の中のひとつにすぎない。
マーティング研究所ではなく、ブランド・マネジメント部とフォーカスを絞り込んであるところに、会社としてかにブランドに力を注いでいるかがわかる。
何でもいいから売れるための仕組みを作ろうなどという、単なる目先だけのことではないのだ。
マーケティングを考えるときにブランドは考え方が難しく、広義のマーケティング戦略の中にはブランド戦略はもちろん入ると思うが、狭義のマーケティング戦略に固執すると、ブランドを構築できないこともあるだろう。うむむ、ブランドは難しい。。
深川製磁サイト
あの棒ラーメンは佐賀で作られている
2004年11月2日佐賀新聞朝刊7頁より
棒ラーメンをご存知だろうか。
普通の袋ラーメンとは違い、そうめんのように棒状の麺が束ねてあるラーメンだ。
佐賀、福岡では一般的に知られているラーメンで、小さい頃からよく食べた。ほとんどの棒ラーメンが麺とスープだけしか入っておらず、かやくはせいぜい海苔とか胡麻くらい。
その棒ラーメン。全国的にはどの程度食べられているのだろうか?
福岡に本社を置くマルタイという会社が棒ラーメンの会社であるが、なんとマルタイで生産される棒ラーメンの全国シェアは90%というから驚きだ。(JAS認定の棒ラーメンの中で)
さらにそのすべての棒ラーメンが、佐賀の北波多村にある、佐賀工場で生産されているというからなおびっくり。そんな事実はまったく知らなかった。。
棒ラーメンのいいところは、いくつかある。まず2つの束が入っていて、ひとつだと腹八分目くらいの量だ。だから食べ過ぎることがない。もうひとつはかやくがないので、具を自分で足すことを考えざるを得ないから、野菜などをトッピングして食べる習慣がつく。これは近頃の健康志向の観点からも奨励されるべき食べ方だろう。
味のマルタイWebサイト
棒ラーメンをご存知だろうか。
普通の袋ラーメンとは違い、そうめんのように棒状の麺が束ねてあるラーメンだ。
佐賀、福岡では一般的に知られているラーメンで、小さい頃からよく食べた。ほとんどの棒ラーメンが麺とスープだけしか入っておらず、かやくはせいぜい海苔とか胡麻くらい。
その棒ラーメン。全国的にはどの程度食べられているのだろうか?
福岡に本社を置くマルタイという会社が棒ラーメンの会社であるが、なんとマルタイで生産される棒ラーメンの全国シェアは90%というから驚きだ。(JAS認定の棒ラーメンの中で)
さらにそのすべての棒ラーメンが、佐賀の北波多村にある、佐賀工場で生産されているというからなおびっくり。そんな事実はまったく知らなかった。。
棒ラーメンのいいところは、いくつかある。まず2つの束が入っていて、ひとつだと腹八分目くらいの量だ。だから食べ過ぎることがない。もうひとつはかやくがないので、具を自分で足すことを考えざるを得ないから、野菜などをトッピングして食べる習慣がつく。これは近頃の健康志向の観点からも奨励されるべき食べ方だろう。
味のマルタイWebサイト
靴販売の訪問計測
2004年10月20日佐賀新聞朝刊7頁より
婦人靴専門店「JUMBO」(本社富士町)が靴の販売のために訪問計測を行なっている、とある。
訪問は無料で、電話で予約を受け付け、コンピュータをつかってサイズを測り、靴の選び方も指導するとある。距離的な問題、足が不自由な人、高齢者らの需要を見込んでいるとのこと。
ニーズに対応した新たなサービスだ。
ニーズに応じたサービスを、とこのコラムでも何度も書いている。ニーズは商品自体に対するもの以外にも、問い合わせから購入、購入後といった過程のなかにも転がっている。
婦人靴専門店「JUMBO」(本社富士町)が靴の販売のために訪問計測を行なっている、とある。
訪問は無料で、電話で予約を受け付け、コンピュータをつかってサイズを測り、靴の選び方も指導するとある。距離的な問題、足が不自由な人、高齢者らの需要を見込んでいるとのこと。
ニーズに対応した新たなサービスだ。
ニーズに応じたサービスを、とこのコラムでも何度も書いている。ニーズは商品自体に対するもの以外にも、問い合わせから購入、購入後といった過程のなかにも転がっている。
03年度県内小売業売上高
2004年10月9日佐賀新聞朝刊11頁より
03年度県内小売業売上高ランキングが掲載されている。
1位がサンクスジャパンで約683億円、2位がオサダ 約189億円、3位があんくるふじや 約137億円、4位が祐徳自動車、5位佐賀玉屋、6位鈴花、7位まいづる百貨店、8位スーパーモリナガ、9位 コープさが(生協)と続く。
九州沖縄八県では、売上高50億円を超えた社数、総売上とも最も少ないとのこと。人口が少ないので、企業数も少ないのは当然と思えるが、総額の下げ幅が18.18%とあるから、以前厳しい経済情勢だといえる。
Webプロデューサーの立場からみると、上記の企業でWebサイトを本格的に展開しているのはまだない。県内有数の企業がWebサイトに力をいれていない状況は、とても心配に思える。
03年度県内小売業売上高ランキングが掲載されている。
1位がサンクスジャパンで約683億円、2位がオサダ 約189億円、3位があんくるふじや 約137億円、4位が祐徳自動車、5位佐賀玉屋、6位鈴花、7位まいづる百貨店、8位スーパーモリナガ、9位 コープさが(生協)と続く。
九州沖縄八県では、売上高50億円を超えた社数、総売上とも最も少ないとのこと。人口が少ないので、企業数も少ないのは当然と思えるが、総額の下げ幅が18.18%とあるから、以前厳しい経済情勢だといえる。
Webプロデューサーの立場からみると、上記の企業でWebサイトを本格的に展開しているのはまだない。県内有数の企業がWebサイトに力をいれていない状況は、とても心配に思える。
地酒バーの営業時間
2004年10月7日佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀市唐人町にある地酒バー「ノンドット」がオープン一年を迎えた。
来客6000人ということで、手ごたえを感じているとある。
私はオープン初日に行ったきりで、その後行っていないから、客の入りはよく知らなかったが、健闘しているようだ。ただし、経営状況は赤とあるので、赤字でいつまでも続くものでもないので一層の努力が必要な状態だ。
気になる点がある。営業時間が二十三時半までという点だ。白山や愛敬などから少し離れたところにあるので、夜の人通りは少ないかもしれないが、閉店が早すぎはしないだろうか。
適正な営業時間を調査して延長した方がよいという判断がでれば営業時間を延長してはどうだろう。
佐賀市唐人町にある地酒バー「ノンドット」がオープン一年を迎えた。
来客6000人ということで、手ごたえを感じているとある。
私はオープン初日に行ったきりで、その後行っていないから、客の入りはよく知らなかったが、健闘しているようだ。ただし、経営状況は赤とあるので、赤字でいつまでも続くものでもないので一層の努力が必要な状態だ。
気になる点がある。営業時間が二十三時半までという点だ。白山や愛敬などから少し離れたところにあるので、夜の人通りは少ないかもしれないが、閉店が早すぎはしないだろうか。
適正な営業時間を調査して延長した方がよいという判断がでれば営業時間を延長してはどうだろう。
プレゼンテーションの演出
2004年9月4日佐賀新聞朝刊8頁より
昨日の佐賀市文化会館イベントホールで行なわれたオンリーワンフェアの模様が載っている。当グループでも携帯電話向けメール配信サービスを紹介するブースを出展した。
来場者も多くあり、賑わい感があった。聞くところでは昼のNHKニュースでも流れたということで、メディアも後押%しをしてくれたのだろう。
プレゼンテーションでは第一番目のおはちがまわっており、極度に緊張した。前の夜に遅くまで練習した成果があったかどうか定かではないが、会話形式のプレゼンは、聞く人を飽きさせない効果はあったようだ。プレゼンテーションの演出をいかにするか。出品する商品やサービスを魅力的にみせるうえでもかかせない。
昨日の佐賀市文化会館イベントホールで行なわれたオンリーワンフェアの模様が載っている。当グループでも携帯電話向けメール配信サービスを紹介するブースを出展した。
来場者も多くあり、賑わい感があった。聞くところでは昼のNHKニュースでも流れたということで、メディアも後押%しをしてくれたのだろう。
プレゼンテーションでは第一番目のおはちがまわっており、極度に緊張した。前の夜に遅くまで練習した成果があったかどうか定かではないが、会話形式のプレゼンは、聞く人を飽きさせない効果はあったようだ。プレゼンテーションの演出をいかにするか。出品する商品やサービスを魅力的にみせるうえでもかかせない。
東与賀にスーパーセンター
2004年9月3日佐賀新聞朝刊1頁より
佐賀郡東与賀町に進出を予定しているイオン九州の大型商業施設の概要があきらかになった。
「スーパーセンター」を核に、24時間営業を行なうとある。
佐賀市域は、九州でも有数のスーパー激戦地区にあげられている。既に大和ジャスコ、モラージュの大型商業施設があり、これから、ゆめ%1タウン、記事にあるイオンのスーパーセンターと、流通戦争はまだはじまったばかりのような勢いだ。まだまだ目が離せない展開が続く。
なみログのサーバか、ネットワークの障害はまだ復旧しておらず、短い文章しかかけない。
佐賀郡東与賀町に進出を予定しているイオン九州の大型商業施設の概要があきらかになった。
「スーパーセンター」を核に、24時間営業を行なうとある。
佐賀市域は、九州でも有数のスーパー激戦地区にあげられている。既に大和ジャスコ、モラージュの大型商業施設があり、これから、ゆめ%1タウン、記事にあるイオンのスーパーセンターと、流通戦争はまだはじまったばかりのような勢いだ。まだまだ目が離せない展開が続く。
なみログのサーバか、ネットワークの障害はまだ復旧しておらず、短い文章しかかけない。