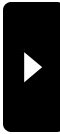スポンサーサイト
メガネ店 オンデーズ
2007年3月5日(月)佐賀新聞朝刊2頁「ろんだん佐賀」より
オンデーズというメガネ店を知っているだろうか。
私は初めて知った。
■オンデーズ
今朝の佐賀新聞の2面、ろんだん佐賀に、オンデーズの代表取締役会長の森部好樹氏の論説が載っていて、面白く読んだ。
安くていいメガネを顧客に販売すべく、小規模店舗による営業。駅のテナントに入り営業を開始した。東京駅と横浜駅。横浜駅は14坪の店。2001年9月のことである。
オープン当日からお客が殺到し、売上も一ヶ月で2000万円以上。7000円の単価である格安メガネだから販売数が凄い。
駅中とショッピングセンター、小規模という設定で店舗を増やしている。
とどのつまり、小は大に勝ることもあるという主旨の話なのだが、商品を絞り込み、小規模店舗に絞り込んだ結果、成功したという例だ。
小は大に勝ることもある、というよりも、
<絞り込んだほうが成功する。>
といういい例だ。
オンデーズというメガネ店を知っているだろうか。
私は初めて知った。
■オンデーズ
今朝の佐賀新聞の2面、ろんだん佐賀に、オンデーズの代表取締役会長の森部好樹氏の論説が載っていて、面白く読んだ。
安くていいメガネを顧客に販売すべく、小規模店舗による営業。駅のテナントに入り営業を開始した。東京駅と横浜駅。横浜駅は14坪の店。2001年9月のことである。
オープン当日からお客が殺到し、売上も一ヶ月で2000万円以上。7000円の単価である格安メガネだから販売数が凄い。
駅中とショッピングセンター、小規模という設定で店舗を増やしている。
とどのつまり、小は大に勝ることもあるという主旨の話なのだが、商品を絞り込み、小規模店舗に絞り込んだ結果、成功したという例だ。
小は大に勝ることもある、というよりも、
<絞り込んだほうが成功する。>
といういい例だ。
ホームセンターのコメリが佐賀に2店舗進出
2007年1月30日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
先週は水曜日から日曜日の朝まで東京出張でした。
さて、今日の佐賀新聞に、ホームセンターの大手である「コメリ」が、佐賀に2店舗進出するとある。
場所は、鹿島と基山。
いよいよ、食品小売業だけでなく、ホームセンターも大手の九州進出かあ。それも超大手だもんね。
新聞記事によると、同社は今月1月16日に長崎県雲仙に九州1号店をオープンした。2月1日には、宮崎県に九州5号店を開くなど、出店攻勢をかけているという。
おっとっと、2号店、3号店、4号店はどこだ???
熊本県宇城市小川町にもあるようだ。
大牟田市に物流センターも作ったというから一歩も引けない体制ということだろう。
先週は水曜日から日曜日の朝まで東京出張でした。
さて、今日の佐賀新聞に、ホームセンターの大手である「コメリ」が、佐賀に2店舗進出するとある。
場所は、鹿島と基山。
いよいよ、食品小売業だけでなく、ホームセンターも大手の九州進出かあ。それも超大手だもんね。
新聞記事によると、同社は今月1月16日に長崎県雲仙に九州1号店をオープンした。2月1日には、宮崎県に九州5号店を開くなど、出店攻勢をかけているという。
おっとっと、2号店、3号店、4号店はどこだ???
熊本県宇城市小川町にもあるようだ。
大牟田市に物流センターも作ったというから一歩も引けない体制ということだろう。
県内企業の人材不足8割!!
2007年1月19日(金)佐賀新聞朝刊1頁より
佐賀県内企業の約8割に、人材不足感がある。
ほほう。
最近常に思っていた課題だったので、他の県内企業でもそうかあ、と納得。
記事によると、昨年夏に従業員30人以上の佐賀県内企業1194社にアンケートをしたところ(回答企業数は454社)、76.7%の企業が不足感があると回答。とくに技術・製品分野、販売・マーケティング分野が30%台ととくに多い。
ちなみにIT活用や情報化部門ではそれぞれ7%、5%とそうでもなかった・・・
経理や人事職の不足感にも負けていた・・・
おいおいおい。
経理や人事職との比較対照をしても意味が無いが、需要が少ないというより、情報化やIT活用人材が必要なことに、まだ気づいていない企業が多いということではないかい?
それから、このアンケートは県外大手企業に勤める人やOBにもアンケートをとっており、Uターンの意向についても聞いてあり、なんと22%もの人が(といっていいだろう)、Uターンを考えているということだ。
さらには、そのなかの5割の人が、県内企業就職を希望しているとな。
県内企業=人手不足
県外Uターン希望者=待遇面で県内企業に選ぶ企業が無い
という構図のようだ。
もちっとマッチングがうまく行くようになれば、Uターンする人も増えて県内企業にも大きなメリットがもたらされると思うのだが。
それからなんべんも書くが、当社Webビジネスグループでは事業拡大のため人材を急募しているので、やる気のある人は問い合わせを。
佐賀県内企業の約8割に、人材不足感がある。
ほほう。
最近常に思っていた課題だったので、他の県内企業でもそうかあ、と納得。
記事によると、昨年夏に従業員30人以上の佐賀県内企業1194社にアンケートをしたところ(回答企業数は454社)、76.7%の企業が不足感があると回答。とくに技術・製品分野、販売・マーケティング分野が30%台ととくに多い。
ちなみにIT活用や情報化部門ではそれぞれ7%、5%とそうでもなかった・・・
経理や人事職の不足感にも負けていた・・・
おいおいおい。
経理や人事職との比較対照をしても意味が無いが、需要が少ないというより、情報化やIT活用人材が必要なことに、まだ気づいていない企業が多いということではないかい?
それから、このアンケートは県外大手企業に勤める人やOBにもアンケートをとっており、Uターンの意向についても聞いてあり、なんと22%もの人が(といっていいだろう)、Uターンを考えているということだ。
さらには、そのなかの5割の人が、県内企業就職を希望しているとな。
県内企業=人手不足
県外Uターン希望者=待遇面で県内企業に選ぶ企業が無い
という構図のようだ。
もちっとマッチングがうまく行くようになれば、Uターンする人も増えて県内企業にも大きなメリットがもたらされると思うのだが。
それからなんべんも書くが、当社Webビジネスグループでは事業拡大のため人材を急募しているので、やる気のある人は問い合わせを。
ゆめタウン佐賀フロアガイド
佐賀県内でIT人材不足!!
2006年12月9日(土)佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀県内のIT関連企業等で、IT人材が不足しているという記事。
(私が勤める福博印刷Webビジネスカンパニーでもそうだ。)
いやいや、景気が上向いてきたと思えば、一気に人手不足になるこの状況。
IT企業希望者にとっては、追い風の雇用状況だ。
と楽観視していると、じつはそうとはいえない問題もあるようだ。
どうも、県内の希望者のスキルレベルは、受け入れ側が希望するスキルレベルと乖離があり、適任者は少ないということのようだ。
うーん。。
実情としてそうだろうなーと思ったりする。
原因はなにかというと、いろいろあると思うが、プロの仕事ぶりと、IT技術取得の大学、専門学校、職業訓練校の仕事の教え方と、そこに違いがあって、その差が採用する側にとって適任とはいえないケースもあるということだろう。
ベンチャー企業の社長が書いた、成功本に書いてある話に、「採用基準は、ITに詳しくなくてもやる気さえあればいい」
というようなことが書いてあるが、(ネットプライス社長の池本氏の本にはそう書いてあった)
まさにそのとおりで、案外、やる気の部分で、もうちょっとという感じを抱く希望者も少なくない。
新聞記事に書かれている内容だけでは、どのような印象を受けて、県内応募者には適任者が少ないとあるのかよく伝わってこないので、ただ単にITのスキルの話だろうと思っていると、実はそれだけの理由ではなく、単にやる気の問題であったりすることもあるだろうと思うのが私の意見。
佐賀県内のIT関連企業等で、IT人材が不足しているという記事。
(私が勤める福博印刷Webビジネスカンパニーでもそうだ。)
いやいや、景気が上向いてきたと思えば、一気に人手不足になるこの状況。
IT企業希望者にとっては、追い風の雇用状況だ。
と楽観視していると、じつはそうとはいえない問題もあるようだ。
どうも、県内の希望者のスキルレベルは、受け入れ側が希望するスキルレベルと乖離があり、適任者は少ないということのようだ。
うーん。。
実情としてそうだろうなーと思ったりする。
原因はなにかというと、いろいろあると思うが、プロの仕事ぶりと、IT技術取得の大学、専門学校、職業訓練校の仕事の教え方と、そこに違いがあって、その差が採用する側にとって適任とはいえないケースもあるということだろう。
ベンチャー企業の社長が書いた、成功本に書いてある話に、「採用基準は、ITに詳しくなくてもやる気さえあればいい」
というようなことが書いてあるが、(ネットプライス社長の池本氏の本にはそう書いてあった)
まさにそのとおりで、案外、やる気の部分で、もうちょっとという感じを抱く希望者も少なくない。
新聞記事に書かれている内容だけでは、どのような印象を受けて、県内応募者には適任者が少ないとあるのかよく伝わってこないので、ただ単にITのスキルの話だろうと思っていると、実はそれだけの理由ではなく、単にやる気の問題であったりすることもあるだろうと思うのが私の意見。
ゆめタウン佐賀オープン
2006年12月5日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
佐賀新聞経済面に、ゆめタウン佐賀の、竣工披露宴が4日にあったとある。
そして今日から、ゆめタウン佐賀がオープン。(グランドオープンは7日)
新聞記事によると、佐賀駅から、ゆめタウン線のバス便もでき、1日計82便も運行するとある。
(佐賀は公共交通網が発達していないため、いつのまにか誰もバスに乗らなくなった。。)
それにしても佐賀市内は、北はイオンショッピングタウン大和、南はモラージュ佐賀、そしてやや東よりの中央部にゆめタウン佐賀。
(ほんとうの中央部は、佐賀玉屋や、エスプラッツがある所あたりか。。)
もう福岡まで買い物に出なくても、十分にお好みのモノが揃うんではないだろうか。
モラージュ佐賀には映画館も出来たし。
この人口規模(約20万人)でこれくらい商業施設がある都市ってあるんだろうか?全国的に見ても、恵まれてきている気がするが、まだまだなのかな??
さて、これ以上、商業面積が増えたとしても、消費が上向かないと、進出した側はあてが外れた格好に終る。
消費が上向くには、所得が伸びないとならず、所得を延ばす為には、佐賀県民が働く企業の業績が上向かないとならないのだ。
消費社会は着実に充実してきている。
つぎは佐賀県が、どう創造社会をどう作っていくかだろう。
消費する側ではなくて、創造する側に回る人(企業はもちろん)をもっと輩出しないとなるまいな。
佐賀新聞経済面に、ゆめタウン佐賀の、竣工披露宴が4日にあったとある。
そして今日から、ゆめタウン佐賀がオープン。(グランドオープンは7日)
新聞記事によると、佐賀駅から、ゆめタウン線のバス便もでき、1日計82便も運行するとある。
(佐賀は公共交通網が発達していないため、いつのまにか誰もバスに乗らなくなった。。)
それにしても佐賀市内は、北はイオンショッピングタウン大和、南はモラージュ佐賀、そしてやや東よりの中央部にゆめタウン佐賀。
(ほんとうの中央部は、佐賀玉屋や、エスプラッツがある所あたりか。。)
もう福岡まで買い物に出なくても、十分にお好みのモノが揃うんではないだろうか。
モラージュ佐賀には映画館も出来たし。
この人口規模(約20万人)でこれくらい商業施設がある都市ってあるんだろうか?全国的に見ても、恵まれてきている気がするが、まだまだなのかな??
さて、これ以上、商業面積が増えたとしても、消費が上向かないと、進出した側はあてが外れた格好に終る。
消費が上向くには、所得が伸びないとならず、所得を延ばす為には、佐賀県民が働く企業の業績が上向かないとならないのだ。
消費社会は着実に充実してきている。
つぎは佐賀県が、どう創造社会をどう作っていくかだろう。
消費する側ではなくて、創造する側に回る人(企業はもちろん)をもっと輩出しないとなるまいな。
ドイツ見本市にラックワンが佐賀県産品を出店
2006年12月1日(金)佐賀新聞朝刊8頁より
佐賀玉屋の横で、ギャラリー楽庵を運営する「ラックワン」が、先ごろドイツのハノーバー市で開催された国際見本市「infa」に出展した。
佐賀県内の特産品や県内作家の作品を1000点以上出展し、佐賀の魅力をアピールしたと記事にある。
記事には、ラックワンが、来年にもドイツ支店開設をするということもかかれていて、
ドイツと佐賀を結ぶ商品をとおした交流が面白そうだ。
ドイツで売れるのなら、ヨーロッパどこでも売れるような気がするが、輸送賃とか現地での人件費など換算すると、例えば、佐賀で店頭で1万円で売っているものは、どのくらいの値段で売れるものなのだろうか???
佐賀玉屋の横で、ギャラリー楽庵を運営する「ラックワン」が、先ごろドイツのハノーバー市で開催された国際見本市「infa」に出展した。
佐賀県内の特産品や県内作家の作品を1000点以上出展し、佐賀の魅力をアピールしたと記事にある。
記事には、ラックワンが、来年にもドイツ支店開設をするということもかかれていて、
ドイツと佐賀を結ぶ商品をとおした交流が面白そうだ。
ドイツで売れるのなら、ヨーロッパどこでも売れるような気がするが、輸送賃とか現地での人件費など換算すると、例えば、佐賀で店頭で1万円で売っているものは、どのくらいの値段で売れるものなのだろうか???
佐賀玉屋 創業200年特集記事
2006年11月14日(火)佐賀新聞朝刊26頁より
なみログをよく見ている人によれば、佐賀の経済や商業についてどうコメントしているのか、それが楽しみという声がある。
また、切り込んでコメントしたことはほとんどないので、切り口が浅いとか、物足りないという意見も多い・・・
と前置きはそのくらいにして、佐賀玉屋の創業200年に合わせた特集記事が、26面に掲載されている。
仕事以外ではほとんど行く機会のなかった佐賀玉屋だが、先日、玉屋で大きな買い物をした。その日は日曜日でついでにポイント3倍セール?かだったので、買い物客も多く、結構賑わっていた。
記事によると、玉屋の売上は前年比減の状態が数年続いているが、来店者数は今年から微増に変わったということだ。
ポンパドウルというパン屋さんや、本館7階の和のフロアなどが、主婦に人気がでてきた結果ではないかということで、売上増の期待ももてる。
消費者ニーズをとらえることが大事な小売業だが、消費者にニーズは無いという話もよく聞く話だ。
たまたま今日、会社でミーティングがあり、その中で、自信を持って提案することの必要性を説いた人がいたが、一理あると思った。
私たちは、なにか満足をさせてもらうものを買いには行くのだが、例えばなにかおいしいものと漠然とした買い物のとき、(主婦が買い物のときに献立を事前に考えている割合とかあったな・・)、売場で目に付く食材が提案されていれば、それを買ってみようかと思うだろう。
風呂敷がブームみたいなので、そういえば玉屋にあったな、と思った主婦は、玉屋にでかけて、風呂敷をながめるが、そこでおすすめの風呂敷を店員が広げて、実際に箱などを包んで見せたりすると、買ってみようと思うだろう。
買いたいと思わせる一工夫は、消費者にとっては嫌なものではなく、逆にありがたかったりするときも多い。ただ、そのときに粗悪品を売りつけようと思ったり、品質以上に値の高いものを売りつけようと思うとダメだ。消費者の気持ちになって、決めあぐねている消費者に、自分が自信を持っておすすめできるものを、勧める。
話は変わるが、玉屋がもっと元気になるには、どうしても大通りに面するお店とのコラボレーションが必要だろう。玉屋を出て、駐車場まで行く道すがらに、ちょっと喫茶店によるとか、おいしいランチを食べるとか、なんでもかんでも玉屋だけで済まそうという人ばかりではないからだ。
なみログをよく見ている人によれば、佐賀の経済や商業についてどうコメントしているのか、それが楽しみという声がある。
また、切り込んでコメントしたことはほとんどないので、切り口が浅いとか、物足りないという意見も多い・・・
と前置きはそのくらいにして、佐賀玉屋の創業200年に合わせた特集記事が、26面に掲載されている。
仕事以外ではほとんど行く機会のなかった佐賀玉屋だが、先日、玉屋で大きな買い物をした。その日は日曜日でついでにポイント3倍セール?かだったので、買い物客も多く、結構賑わっていた。
記事によると、玉屋の売上は前年比減の状態が数年続いているが、来店者数は今年から微増に変わったということだ。
ポンパドウルというパン屋さんや、本館7階の和のフロアなどが、主婦に人気がでてきた結果ではないかということで、売上増の期待ももてる。
消費者ニーズをとらえることが大事な小売業だが、消費者にニーズは無いという話もよく聞く話だ。
たまたま今日、会社でミーティングがあり、その中で、自信を持って提案することの必要性を説いた人がいたが、一理あると思った。
私たちは、なにか満足をさせてもらうものを買いには行くのだが、例えばなにかおいしいものと漠然とした買い物のとき、(主婦が買い物のときに献立を事前に考えている割合とかあったな・・)、売場で目に付く食材が提案されていれば、それを買ってみようかと思うだろう。
風呂敷がブームみたいなので、そういえば玉屋にあったな、と思った主婦は、玉屋にでかけて、風呂敷をながめるが、そこでおすすめの風呂敷を店員が広げて、実際に箱などを包んで見せたりすると、買ってみようと思うだろう。
買いたいと思わせる一工夫は、消費者にとっては嫌なものではなく、逆にありがたかったりするときも多い。ただ、そのときに粗悪品を売りつけようと思ったり、品質以上に値の高いものを売りつけようと思うとダメだ。消費者の気持ちになって、決めあぐねている消費者に、自分が自信を持っておすすめできるものを、勧める。
話は変わるが、玉屋がもっと元気になるには、どうしても大通りに面するお店とのコラボレーションが必要だろう。玉屋を出て、駐車場まで行く道すがらに、ちょっと喫茶店によるとか、おいしいランチを食べるとか、なんでもかんでも玉屋だけで済まそうという人ばかりではないからだ。
佐賀県の電子申請の利用が増加
2006年9月30日(土)佐賀新聞朝刊29頁より
佐賀県がWebサイトで利用できるようにしている、電子申請の利用者が増えているという。
2004年度の利用件数が73件だったのに対し、2005年度は2091件。
かなり増加している。
じわじわと佐賀県民もネットを利用するようになっているようだ。
最近仕事先で話しに出るのが、60歳代以上の人のネット人口についてだ。
サービスや商品が60歳代以上を対象顧客としているとき、Webサービスを実践することの費用対効果に懐疑的な経営者が多い。
自社のWebサービスをお金をかけて実施したところで、どのくらい効果があがるのか。
という疑念だ。
よくわかる。
放題な販売促進費をそこに投入しようというのであれば、それはやめたほうがいいだろう。
しかし、単価にもよるが、商品のひとつが数万円、数十万円、数百万円するようなもので、年間を通じて、その層からの購買が多い商品を扱っているばあいは、Webビジネスへの挑戦をぜひおすすめしたい。
例えば、家が一番わかりやすい例だろう。
家は数千万円する商品であるにも関わらず、いまでは多くの人がネットで情報を探している商品だ。
車に比べて、販売会社が限られていないし、販売会社がどこにあるのかも判らない。また、同じ商品を目にすることが物理的にできないという代物だ。
車であれば、展示車を見ることもできるし、店もロードサイドにあるので判りやすい。
家は?どの土地が売りに出されているのか?どのような家ができるのか?そういうことがまるっきり判らない商品だ。
そりゃ、とりあえずネットで調べてみようか、ということになるだろう。
60歳以上あなどることなかれ、多くの人がいまではネットを見ている。メールもしている。
佐賀県の中小企業の人が思っているほど、ネットとは関係の無い層ではない。イメージ以上に多いと思っていたほうがいいくらいだ。
佐賀県で高齢者を対象顧客としたWebサービスはまだ投資の無駄遣いだと思う気持ちは、
ちゃっかりとWebサービスを実践していたり、その準備を急ピッチでしている企業にとってありがたいだけのことである。
佐賀県がWebサイトで利用できるようにしている、電子申請の利用者が増えているという。
2004年度の利用件数が73件だったのに対し、2005年度は2091件。
かなり増加している。
じわじわと佐賀県民もネットを利用するようになっているようだ。
最近仕事先で話しに出るのが、60歳代以上の人のネット人口についてだ。
サービスや商品が60歳代以上を対象顧客としているとき、Webサービスを実践することの費用対効果に懐疑的な経営者が多い。
自社のWebサービスをお金をかけて実施したところで、どのくらい効果があがるのか。
という疑念だ。
よくわかる。
放題な販売促進費をそこに投入しようというのであれば、それはやめたほうがいいだろう。
しかし、単価にもよるが、商品のひとつが数万円、数十万円、数百万円するようなもので、年間を通じて、その層からの購買が多い商品を扱っているばあいは、Webビジネスへの挑戦をぜひおすすめしたい。
例えば、家が一番わかりやすい例だろう。
家は数千万円する商品であるにも関わらず、いまでは多くの人がネットで情報を探している商品だ。
車に比べて、販売会社が限られていないし、販売会社がどこにあるのかも判らない。また、同じ商品を目にすることが物理的にできないという代物だ。
車であれば、展示車を見ることもできるし、店もロードサイドにあるので判りやすい。
家は?どの土地が売りに出されているのか?どのような家ができるのか?そういうことがまるっきり判らない商品だ。
そりゃ、とりあえずネットで調べてみようか、ということになるだろう。
60歳以上あなどることなかれ、多くの人がいまではネットを見ている。メールもしている。
佐賀県の中小企業の人が思っているほど、ネットとは関係の無い層ではない。イメージ以上に多いと思っていたほうがいいくらいだ。
佐賀県で高齢者を対象顧客としたWebサービスはまだ投資の無駄遣いだと思う気持ちは、
ちゃっかりとWebサービスを実践していたり、その準備を急ピッチでしている企業にとってありがたいだけのことである。
佐賀SOHOコミュニティ
昨日の佐賀新聞に、「佐賀SOHOコミュニティ」についての記事が載ったということを知った。
佐賀SOHOコミュニティ http://sns.isagai.jp
は、SOHOの分野で活躍する飯盛氏が代表を務める、SOHO SAGAが運営しているもので、佐賀のSOHOが集い情報を交流するSNSだ。(SNS:ソーシャルネットワークシステム)
私も、案内のメールをもらったので、早速参加した。
なみログ書くのでさえ、最近は頻度が落ちているので、さらにSNSを使ってなにが書けるか自信がないが、Webについては、一応県内ではトップクラスの構築実績とノウハウを持っていると思うので、どんどん、SNSに書き込んで、佐賀のSOHOのみんなの役に立てればと思う。
それにしても、飯盛氏のやることのスピードの速さには圧倒される。
構想を聞いたのもつかの間、あっという間に、SNSができていた。
こんなにSNSが早く立ち上がるのなら、あのSNSだったり、このSNSだったり、さくっと作って運営しようかと思ったりしている。全国展開できそうなものを。
やっぱり我々民間人がどんどんスピードをあげてWebサービスを切り開いていかないとならないな、と思ったりした。
Webサービスを切り開くといえば、私の構想で立ち上げたさがファン。
おかげさまで、20社の加盟がもうすぐといったところ。
先週末には、サガン鳥栖公式ショップもオープンした。
まだまだ力不足は否めないが、佐賀県のWebサービスサイトとしては、代表的なサイトに育っている。
地域創造型のWebサービスをどんどん立ち上げていって、県民メリットはもとより、サービスを全国展開していくなどして、具体的にIT立県につなげていきたいと思っている。
■佐賀SOHOコミュニティ
■さがファン
■サガン鳥栖公式ショップ
佐賀SOHOコミュニティ http://sns.isagai.jp
は、SOHOの分野で活躍する飯盛氏が代表を務める、SOHO SAGAが運営しているもので、佐賀のSOHOが集い情報を交流するSNSだ。(SNS:ソーシャルネットワークシステム)
私も、案内のメールをもらったので、早速参加した。
なみログ書くのでさえ、最近は頻度が落ちているので、さらにSNSを使ってなにが書けるか自信がないが、Webについては、一応県内ではトップクラスの構築実績とノウハウを持っていると思うので、どんどん、SNSに書き込んで、佐賀のSOHOのみんなの役に立てればと思う。
それにしても、飯盛氏のやることのスピードの速さには圧倒される。
構想を聞いたのもつかの間、あっという間に、SNSができていた。
こんなにSNSが早く立ち上がるのなら、あのSNSだったり、このSNSだったり、さくっと作って運営しようかと思ったりしている。全国展開できそうなものを。
やっぱり我々民間人がどんどんスピードをあげてWebサービスを切り開いていかないとならないな、と思ったりした。
Webサービスを切り開くといえば、私の構想で立ち上げたさがファン。
おかげさまで、20社の加盟がもうすぐといったところ。
先週末には、サガン鳥栖公式ショップもオープンした。
まだまだ力不足は否めないが、佐賀県のWebサービスサイトとしては、代表的なサイトに育っている。
地域創造型のWebサービスをどんどん立ち上げていって、県民メリットはもとより、サービスを全国展開していくなどして、具体的にIT立県につなげていきたいと思っている。
■佐賀SOHOコミュニティ
■さがファン
■サガン鳥栖公式ショップ
多久のゆうらくが売却へ
2006年6月2日(金)佐賀新聞朝刊26頁より
多久市にある温泉施設「ゆうらく」が、投資会社に売却される、という記事。
たしかに来場者数は厳しそうだったが、そうなのかぁ、と心配だ。
小学生のころから、ゆうらくのある場所は、遊園地構想があって、小学校のときは本当になにかできるのかと心配していたら、いつの間にか山が削られて、田んぼに道が走り、規模は思ったより小さかったが温泉施設ができた。
(規模でいうと、ゆうらくに行く手前にある、多久ショッピングセンターの付近まで含めた形で、開発じゃなかったのかなあ・・・)
あ、思い出した。
ローラースケート場もできた。中学一年生のときだったか。一瞬だけ利用者が多かった。が、ローラースケート場は1年持っただろうか。。すぐ閉鎖されて、いまも施設は残っているが、なににも使われていないような。
それにしても、ゆうらくは良い売却先が出てきて、再び来場者が伸びればいいと思う。
んー。県内は、富士、大和、七山や、呼子以外はどこも入りこみ客数は減っているのではないだろうか。増えている地区の共通点は、福岡からの客が多いということだ。ドライブしながら訪れて、自然に接して昼ご飯。帰りもそんなに遅くならない。そんなところが人気だ。
多久まで高速道路使ったら近いけど。わざわざ高速道路使ってまでもねえ。
多久市にある温泉施設「ゆうらく」が、投資会社に売却される、という記事。
たしかに来場者数は厳しそうだったが、そうなのかぁ、と心配だ。
小学生のころから、ゆうらくのある場所は、遊園地構想があって、小学校のときは本当になにかできるのかと心配していたら、いつの間にか山が削られて、田んぼに道が走り、規模は思ったより小さかったが温泉施設ができた。
(規模でいうと、ゆうらくに行く手前にある、多久ショッピングセンターの付近まで含めた形で、開発じゃなかったのかなあ・・・)
あ、思い出した。
ローラースケート場もできた。中学一年生のときだったか。一瞬だけ利用者が多かった。が、ローラースケート場は1年持っただろうか。。すぐ閉鎖されて、いまも施設は残っているが、なににも使われていないような。
それにしても、ゆうらくは良い売却先が出てきて、再び来場者が伸びればいいと思う。
んー。県内は、富士、大和、七山や、呼子以外はどこも入りこみ客数は減っているのではないだろうか。増えている地区の共通点は、福岡からの客が多いということだ。ドライブしながら訪れて、自然に接して昼ご飯。帰りもそんなに遅くならない。そんなところが人気だ。
多久まで高速道路使ったら近いけど。わざわざ高速道路使ってまでもねえ。
有田焼ショップのチェーンストア化は可能か?
2006年4月28日(金)佐賀新聞朝刊9頁より
昨日の佐賀新聞に、有田焼05年売上高が78億円、9年連続減少という記事がある。
4月29日(土)から有田町では全国的にも有名なイベントである、有田陶器市が開催されるというというのに、昨年の数字とはいえ、厳しい業界の現状が突きつけられるような記事だ。
2004年の前年比でも10%減という数字は、2005年の企業売上がおしなべて前年よりは上向いているという状況と比べると、一段と深刻だ。もちろん、中央と地方、業種別、勝ち組みと負け組みといわれるように、ある業種だけの問題や地域間格差の問題だけでもないが、業種の問題と、地域の問題が、有田においてはどちらもマイナスに作用しているといってもいいような問題だ。
ところで、陶磁器だけを扱うカテゴリーキラーの郊外型チェーンストア、もしくは、大型ショッピングセンターへのテナント出店ってあるのだろうか?とふと思った。
前者でいえば、ホームセンターや、ディスカウントストアのように売場の一部で陶磁器を売るのではなく、ほとんど全てが陶磁器というショップだ。
後者でいえば、イオンやゆめタウンなどの大型ショッピングセンターに、テナントとして入るパターンだ。
そういう陶磁器だけをメインで扱うカテゴリーキラーのチェーンストアってあるんだろうか?
新聞の記事によると、有田焼の売上構成が、料亭やホテル、旅館向けの業務用食器が7割を占めているとある。ということは、個人消費の部分をもう少し増やしていくというのも大きな課題にはなっているのだろう。
有田にまで足を運んでもらうことなく、また、百貨店や、都市の小さな陶磁器ショップで買ってもらうだけではない、車で行けて、いろいろ種類を選べて、家族で行って楽しい雰囲気のする、有田焼ショップがあってもいいのではないかと思ったりした。
ストアの運営は、チェーンストア理論に基礎をおいた取組みで。
陶磁器や陶磁器の市場にも疎いし、チェーンストア理論も素人に毛が生えた程度の知識なので、素人の浅知恵ではある。
昨日の佐賀新聞に、有田焼05年売上高が78億円、9年連続減少という記事がある。
4月29日(土)から有田町では全国的にも有名なイベントである、有田陶器市が開催されるというというのに、昨年の数字とはいえ、厳しい業界の現状が突きつけられるような記事だ。
2004年の前年比でも10%減という数字は、2005年の企業売上がおしなべて前年よりは上向いているという状況と比べると、一段と深刻だ。もちろん、中央と地方、業種別、勝ち組みと負け組みといわれるように、ある業種だけの問題や地域間格差の問題だけでもないが、業種の問題と、地域の問題が、有田においてはどちらもマイナスに作用しているといってもいいような問題だ。
ところで、陶磁器だけを扱うカテゴリーキラーの郊外型チェーンストア、もしくは、大型ショッピングセンターへのテナント出店ってあるのだろうか?とふと思った。
前者でいえば、ホームセンターや、ディスカウントストアのように売場の一部で陶磁器を売るのではなく、ほとんど全てが陶磁器というショップだ。
後者でいえば、イオンやゆめタウンなどの大型ショッピングセンターに、テナントとして入るパターンだ。
そういう陶磁器だけをメインで扱うカテゴリーキラーのチェーンストアってあるんだろうか?
新聞の記事によると、有田焼の売上構成が、料亭やホテル、旅館向けの業務用食器が7割を占めているとある。ということは、個人消費の部分をもう少し増やしていくというのも大きな課題にはなっているのだろう。
有田にまで足を運んでもらうことなく、また、百貨店や、都市の小さな陶磁器ショップで買ってもらうだけではない、車で行けて、いろいろ種類を選べて、家族で行って楽しい雰囲気のする、有田焼ショップがあってもいいのではないかと思ったりした。
ストアの運営は、チェーンストア理論に基礎をおいた取組みで。
陶磁器や陶磁器の市場にも疎いし、チェーンストア理論も素人に毛が生えた程度の知識なので、素人の浅知恵ではある。
新北九州空港が開港
2006年3月17日(金)佐賀新聞朝刊27頁より
新北九州空港が16日開港した。
だから何なの?と思ってしまう人もいるだろうが、そうはいってられないというのが、佐賀空港だ。
新北九州空港の開港で何が佐賀空港としてピーンチかというと、(ピンチという言葉も久しぶり使うが・・)夜間の貨物便の就航で先を行く佐賀空港に、新北九州空港が参入するという図式で、それも、最大の市場である福岡市の貨物の取り合いになるということみたいだ。
いまのところはもちろん佐賀空港に分があるようなので、なんとかこれまで以上に貨物量が増えるように期待したいものだ。
新北九州空港が16日開港した。
だから何なの?と思ってしまう人もいるだろうが、そうはいってられないというのが、佐賀空港だ。
新北九州空港の開港で何が佐賀空港としてピーンチかというと、(ピンチという言葉も久しぶり使うが・・)夜間の貨物便の就航で先を行く佐賀空港に、新北九州空港が参入するという図式で、それも、最大の市場である福岡市の貨物の取り合いになるということみたいだ。
いまのところはもちろん佐賀空港に分があるようなので、なんとかこれまで以上に貨物量が増えるように期待したいものだ。
多久市に三谷電子進出
2006年2月15日(水)佐賀新聞朝刊23頁より
多久市の多久北部工業団地内に、東京に本社を置く三谷電子工業が進出するということで、進出協定を結んだとある。
三谷電子工業
多久北部工業団地は、九州自動車道の多久ICの付近に整備された工業団地で、サガシキ印刷の工場などがある辺りだ。
新聞によると同団地は計7区画あり、これまで3社が進出し、残り4区画が空き地だったとある。
多久市では、その工業団地を一坪100円で貸し出すという企業誘致策を打ち出していた。
多久ICも目の前だし、伊万里にも山越えていけるので、伊万里港から中国向けの輸出も面白い。思った以上に交通には便利なところだと思う。
多久市の多久北部工業団地内に、東京に本社を置く三谷電子工業が進出するということで、進出協定を結んだとある。
三谷電子工業
多久北部工業団地は、九州自動車道の多久ICの付近に整備された工業団地で、サガシキ印刷の工場などがある辺りだ。
新聞によると同団地は計7区画あり、これまで3社が進出し、残り4区画が空き地だったとある。
多久市では、その工業団地を一坪100円で貸し出すという企業誘致策を打ち出していた。
多久ICも目の前だし、伊万里にも山越えていけるので、伊万里港から中国向けの輸出も面白い。思った以上に交通には便利なところだと思う。
県内のスーパーに無人レジ登場!
2006年2月7日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
ミズ、首都圏進出
今朝の佐賀県版経済面には、県内企業のミズが、今年秋から来年春にかけて、首都圏の4つの商業施設に化粧品店を出店するとある。
ミズといえば、競争が激しいドラッグストア業界で、地場企業として非常に頑張っていて、福岡、佐賀、長崎に47のドラッグストア、化粧品店、調剤薬局を展開しているというから、元気のある会社だ。
これまでは大型商業施設を例にあげるまでもなく、県内流通企業は県外企業の出店によって厳しい状況を強いられてきた。それはそれで、消費者のニーズだったり、交通の便利さだったり、大きな意味で社会環境だったりしたわけで、いい面が大いにあった。
ただ県内企業が県外にまで展開しているケースは、流通業ではやっぱり少なく、いや、もちろんあの企業だって、この企業だって県外に展開しているじゃないか、というのはあるので、より以上に、県外に出店拡大する店舗がでてくれば、元気がでてきて面白いと思う。
佐賀県の企業らしい特徴がでるのであれば、なおさらいい。たとえば、社員以下パート、アルバイトまでの接客教育が徹底しているとか。地域社会への社会貢献を積極的に展開しているとか。エコに力を入れているとか。なにか、企業経営の背景に佐賀県らしさがでれば面白いと思ったりする。
とまあ、ミズの話はここまでで、その下には、伊万里のスーパー(rocco伊万里店)に無人レジが登場したという記事。
とうとう無人レジの登場か。と思ったニュースだ。
自分で買った商品を自分でバーコードリーダーにかざして、隣のカゴに移していく。そしてお金を払う。
こまかい動作は見にいかないことには、書けないが、子どもにも人気のようで、親子連れで楽しみながら、レジ精算をしたという感想も。
無人の分だけコストを下げられ、その結果商品価格に還元されれば、なおさらいいと思うが、いかがなものか。安いだけのスーパーの時代も終っているかもしれないが、安いというのは、スーパーのコンセプトであるので、安さに還元してもらうのはありがたい。
ミズ、首都圏進出
今朝の佐賀県版経済面には、県内企業のミズが、今年秋から来年春にかけて、首都圏の4つの商業施設に化粧品店を出店するとある。
ミズといえば、競争が激しいドラッグストア業界で、地場企業として非常に頑張っていて、福岡、佐賀、長崎に47のドラッグストア、化粧品店、調剤薬局を展開しているというから、元気のある会社だ。
これまでは大型商業施設を例にあげるまでもなく、県内流通企業は県外企業の出店によって厳しい状況を強いられてきた。それはそれで、消費者のニーズだったり、交通の便利さだったり、大きな意味で社会環境だったりしたわけで、いい面が大いにあった。
ただ県内企業が県外にまで展開しているケースは、流通業ではやっぱり少なく、いや、もちろんあの企業だって、この企業だって県外に展開しているじゃないか、というのはあるので、より以上に、県外に出店拡大する店舗がでてくれば、元気がでてきて面白いと思う。
佐賀県の企業らしい特徴がでるのであれば、なおさらいい。たとえば、社員以下パート、アルバイトまでの接客教育が徹底しているとか。地域社会への社会貢献を積極的に展開しているとか。エコに力を入れているとか。なにか、企業経営の背景に佐賀県らしさがでれば面白いと思ったりする。
とまあ、ミズの話はここまでで、その下には、伊万里のスーパー(rocco伊万里店)に無人レジが登場したという記事。
とうとう無人レジの登場か。と思ったニュースだ。
自分で買った商品を自分でバーコードリーダーにかざして、隣のカゴに移していく。そしてお金を払う。
こまかい動作は見にいかないことには、書けないが、子どもにも人気のようで、親子連れで楽しみながら、レジ精算をしたという感想も。
無人の分だけコストを下げられ、その結果商品価格に還元されれば、なおさらいいと思うが、いかがなものか。安いだけのスーパーの時代も終っているかもしれないが、安いというのは、スーパーのコンセプトであるので、安さに還元してもらうのはありがたい。
佐賀のSOHO事業者へ
2006年1月24日(火)佐賀新聞朝刊9頁より
オピニオンさが 甘くち辛くち
というコーナーで、財団法人SOHO協会理事の飯盛氏がコラムを寄せている。
コラムには、SOHOとIT、SOHOと地域活性化を考えるとき、ITとは単なる道具にしかすぎないという前提から、地域活性化はあくまで「人」が基本でなくてはならないとしている。
以前、なみログでは、SOHOはいまやワークスタイルのSOHOという捉え方ではだめで、SOHOスピリッツなり、SOHOマインド、SOHOなライフスタイルというのが大事ではないかと提起した。
SOHOはブームではなく、生き方、仕事の仕方そのものではないだろうかという意味もこめてだ。
先日、2月3日(金)に佐賀市文化会館で開催されるSOHOビジネスフェアの出展者説明会に顔を出したが、出展者がまだまだ少ないなーという印象をもった。(私たちはもちろんSOHOではなくて、SOHOを支援するエージェント、もしくはクライアントという立場での出展になる)
県内のWebビジネスの活性化のために、私たちもたくさんやりたいことがあるので、ITに強いSOHOと連携を図って一緒に佐賀を盛り上げていきたいと思っているのだが。
飯盛氏のコラムの最後あたりには、地域活性化は人ごとではない、と書かれてある。
連携できるSOHOがいないかなーと、ただ待っているだけではなく、SOHOを支援して育てる取り組みもしていく必要があると考えている。
ということで、Webビジネス、Webデザイン制作、Webサイト構築、Webアプリケーション構築、マーケティングを事業としてされているSOHOの方、一緒に佐賀のWebビジネスを盛り上げていきませんか。
関心ある方、メールください。
オピニオンさが 甘くち辛くち
というコーナーで、財団法人SOHO協会理事の飯盛氏がコラムを寄せている。
コラムには、SOHOとIT、SOHOと地域活性化を考えるとき、ITとは単なる道具にしかすぎないという前提から、地域活性化はあくまで「人」が基本でなくてはならないとしている。
以前、なみログでは、SOHOはいまやワークスタイルのSOHOという捉え方ではだめで、SOHOスピリッツなり、SOHOマインド、SOHOなライフスタイルというのが大事ではないかと提起した。
SOHOはブームではなく、生き方、仕事の仕方そのものではないだろうかという意味もこめてだ。
先日、2月3日(金)に佐賀市文化会館で開催されるSOHOビジネスフェアの出展者説明会に顔を出したが、出展者がまだまだ少ないなーという印象をもった。(私たちはもちろんSOHOではなくて、SOHOを支援するエージェント、もしくはクライアントという立場での出展になる)
県内のWebビジネスの活性化のために、私たちもたくさんやりたいことがあるので、ITに強いSOHOと連携を図って一緒に佐賀を盛り上げていきたいと思っているのだが。
飯盛氏のコラムの最後あたりには、地域活性化は人ごとではない、と書かれてある。
連携できるSOHOがいないかなーと、ただ待っているだけではなく、SOHOを支援して育てる取り組みもしていく必要があると考えている。
ということで、Webビジネス、Webデザイン制作、Webサイト構築、Webアプリケーション構築、マーケティングを事業としてされているSOHOの方、一緒に佐賀のWebビジネスを盛り上げていきませんか。
関心ある方、メールください。
ゆめタウン佐賀
2005年11月22日(火)佐賀新聞朝刊28頁より
佐賀市にまたまた大型ショッピングセンターができるのは、このブログでも紹介してきたが、その「ゆめタウン佐賀」の起工式が行なわれた。
オープンは来年秋を予定しているとある。
新聞には、160のテナントを展開。年商は260億。地元採用1200人を見込むとある。
敷地となる兵庫地区は地ならしの整備が着々と進んでいる。
佐賀市は、北の大和町に大和ジャスコ、南の巨勢町にはモラージュ佐賀、があり流通小売の競争が激化している地域だ。
話は変わるが、先日テレビ番組を見ていると(ワールドビジネスサテライト?報道特集?忘れた・・)、大手流通企業が、地元の自治体とも連携をとって、地域の商店街とタイアップして集客やセールのノウハウを提供するというのがあっていた。
地域の商店街活性化という取り組みに、大手流通企業のノウハウを注入するのは、違和感はあるかもしれないが、それもまた一つの活性化の方策なのかも知れない。
佐賀市にまたまた大型ショッピングセンターができるのは、このブログでも紹介してきたが、その「ゆめタウン佐賀」の起工式が行なわれた。
オープンは来年秋を予定しているとある。
新聞には、160のテナントを展開。年商は260億。地元採用1200人を見込むとある。
敷地となる兵庫地区は地ならしの整備が着々と進んでいる。
佐賀市は、北の大和町に大和ジャスコ、南の巨勢町にはモラージュ佐賀、があり流通小売の競争が激化している地域だ。
話は変わるが、先日テレビ番組を見ていると(ワールドビジネスサテライト?報道特集?忘れた・・)、大手流通企業が、地元の自治体とも連携をとって、地域の商店街とタイアップして集客やセールのノウハウを提供するというのがあっていた。
地域の商店街活性化という取り組みに、大手流通企業のノウハウを注入するのは、違和感はあるかもしれないが、それもまた一つの活性化の方策なのかも知れない。
業務用スーパー
2005年10月4日(火)佐賀新聞朝刊7頁より
業務用スーパー。
私の会社の近くにもある。佐賀県内で業務用スーパーの出店攻勢が続いているという記事が掲載されている。
業務用スーパーとは、飲食店向けに食材を提供するスーパーで、最近では飲食店のニーズのほかに、一般の家庭からの消費も増えてきているという。
こだわり、少量で品揃えをするなど、地域のスーパーが生き残りをかける中、方や業務用スーパー。
なんだか相反する業態のようだが、記事を読むと業務用スーパーの品揃えも、こだわり商品の開発が進んでいるというから、違うニーズを持つ消費者を対象にしているというわけでもなさそうだ。
となると、何が差別化要因なのだろう?と考え込む。
業務用スーパーは、商品ひとつひとつの容量が多いのが特徴。冷凍ものなど買いだめができるし、おのずと容量単価も下がる。
買いだめができる商品は、業務用スーパーでの買い物がお徳といえるだろう。
消費者は偏った消費行動をすることはないと考えていいと思う。業務用スーパーで、安価な買いだめ商品を買った帰りに、コンビニで1個300円近くもするデザートを買って帰るという光景だって考えられるだろう。
業務用スーパー。
私の会社の近くにもある。佐賀県内で業務用スーパーの出店攻勢が続いているという記事が掲載されている。
業務用スーパーとは、飲食店向けに食材を提供するスーパーで、最近では飲食店のニーズのほかに、一般の家庭からの消費も増えてきているという。
こだわり、少量で品揃えをするなど、地域のスーパーが生き残りをかける中、方や業務用スーパー。
なんだか相反する業態のようだが、記事を読むと業務用スーパーの品揃えも、こだわり商品の開発が進んでいるというから、違うニーズを持つ消費者を対象にしているというわけでもなさそうだ。
となると、何が差別化要因なのだろう?と考え込む。
業務用スーパーは、商品ひとつひとつの容量が多いのが特徴。冷凍ものなど買いだめができるし、おのずと容量単価も下がる。
買いだめができる商品は、業務用スーパーでの買い物がお徳といえるだろう。
消費者は偏った消費行動をすることはないと考えていいと思う。業務用スーパーで、安価な買いだめ商品を買った帰りに、コンビニで1個300円近くもするデザートを買って帰るという光景だって考えられるだろう。
宅配会社のネット活用
2005年8月12日(金)佐賀新聞朝刊6頁より
宅配会社のオレンジライフ(本社久留米市)が、バーコードを使ったネット注文を開始するとある。
カタログにバーコードを記載し、それをバーコードリーダーで読み込むというもの。
もちろんネットにつながる環境でないと注文はできないが、会員の40%の世帯がネット環境にあるということで、導入を開始したとある。
バーコードリーダーを使って、ネット注文を行おうという試みはこれまでもあったが、宅配会社で導入をしたのは九州では始めて、全国でも4例目だそうだ。
携帯電話用のQRコードをつかって、ネット注文を行うしくみは、カタログや冊子でも取り入れていられていると思うが、いよいよ佐賀の地でもそのようなネット注文の形が現実になったか、という印象だ。
宅配事業はますます広がると思う。この数年でも宅配を手がけるようになった業種が増えた。
佐賀でもそういう感じがするので、都会ではもっと進んでいるのではないだろうか。
私の無い頭でもいくつかアイデアが浮かんでいる。実験事業でもしようかとも思っている。
なにかというのはナイショだけど。(笑)
それから、今日は、さがファンのショップで、JA佐賀経済連運営の季楽ショップがオープンした。なかなかのショップ構えなので、ぜひご覧いただきたい。
季楽ショップで売っている、手作り味噌・健こうじセットは、他のネットショップで紹介されて、ヒットしているという味噌キット。
ぜひぜひお買い求めの上、手作りの味噌を楽しんで欲しい。
さが風土館 季楽ショップ http://shop.sagafan.com/kira/
さらに、もうひとつ、伊之助めんショップでも店長ブログがはじまった。麺の町、佐賀県神埼より、麺にまつわるいろいろを情報発信していくということなので、こちらも見てほしい。
伊之助めん店長ブログ http://blog.sagafan.com/inosuke/
宅配会社のオレンジライフ(本社久留米市)が、バーコードを使ったネット注文を開始するとある。
カタログにバーコードを記載し、それをバーコードリーダーで読み込むというもの。
もちろんネットにつながる環境でないと注文はできないが、会員の40%の世帯がネット環境にあるということで、導入を開始したとある。
バーコードリーダーを使って、ネット注文を行おうという試みはこれまでもあったが、宅配会社で導入をしたのは九州では始めて、全国でも4例目だそうだ。
携帯電話用のQRコードをつかって、ネット注文を行うしくみは、カタログや冊子でも取り入れていられていると思うが、いよいよ佐賀の地でもそのようなネット注文の形が現実になったか、という印象だ。
宅配事業はますます広がると思う。この数年でも宅配を手がけるようになった業種が増えた。
佐賀でもそういう感じがするので、都会ではもっと進んでいるのではないだろうか。
私の無い頭でもいくつかアイデアが浮かんでいる。実験事業でもしようかとも思っている。
なにかというのはナイショだけど。(笑)
それから、今日は、さがファンのショップで、JA佐賀経済連運営の季楽ショップがオープンした。なかなかのショップ構えなので、ぜひご覧いただきたい。
季楽ショップで売っている、手作り味噌・健こうじセットは、他のネットショップで紹介されて、ヒットしているという味噌キット。
ぜひぜひお買い求めの上、手作りの味噌を楽しんで欲しい。
さが風土館 季楽ショップ http://shop.sagafan.com/kira/
さらに、もうひとつ、伊之助めんショップでも店長ブログがはじまった。麺の町、佐賀県神埼より、麺にまつわるいろいろを情報発信していくということなので、こちらも見てほしい。
伊之助めん店長ブログ http://blog.sagafan.com/inosuke/
本屋とブックビジネスと本のソムリエ
2005年7月11日(日)佐賀新聞朝刊16頁より
ブックびじねすというコラムがある。(佐賀だけではなく全国版)
「テレビの紹介で売れる本」ということで、本屋さんが、本を売るために、テレビで紹介されました。とPOPを作って売っていることについて書かれている。
ブックびじねす危うしと思える記事だなと思う。
スーパーなどの小売店ではとっくの昔にやっていることなのに、なにをいまさらと思う。
それでも取り掛かるに遅くは無いので、売れるのであれば、取り掛かればいい。
食品なんて、ネットでテレビ番組情報まで流れる時代でっせー。
POPそのものの導入も遅かった。
「白い犬とワルツ」だったかの成功で、どこの本屋もPOPに力を入れるようになった。
どうやら、本屋とブックビジネスとイクオールで考えているところに、問題の根本原因があるようだ。
本屋とブックビジネスどちらの肩を持つということではなく考えると、本屋は、おすすめの本が何かを知りたい消費者のニーズに対応してこなかったし、ブックビジネスでは、一般的な売れ筋本以外はまったく消費者におすすめすることができなくなってきている。
この件だけの結論をいえば、どちらもまだ消費者ニーズに対応していないということだ。
本のソムリエという言葉も聞くようになったが、本のソムリエみたいな人がいる本屋があれば、面白いと思う。そこにかかる人件費は相当かかるけど。
だいたいその辺の本屋に行っても、本の予備知識がなさすぎる店員が多い。
ビッグカメラとかヤマダ電器とか、ほんとうのところはどうかしらないが、PCに詳しい人とか、携帯電話に詳しい人とかをアルバイトで雇っていて、彼らは精一杯自分の知識を仕事に活かして、購入者に応対している。
ソムリエとまではいかなくてもいいけど、ネットの世界ではリコメンドによって購買を決める頻度も少なくないのを知ると、リアルではなおさらやらないとならないのではと思ったりする。
あ、い、う、え、お、男性、女性順に並ぶのもいいけど、系統別に並べるとかもあっていい。
佐賀県内には大きな本屋が少ないので、どこも金太郎飴みたいな品揃えなのが残念でならない。
どの町にとっても本屋さんは、その町に住む人々の知的生活を担う大事な場所なのだ。
ブックびじねすというコラムがある。(佐賀だけではなく全国版)
「テレビの紹介で売れる本」ということで、本屋さんが、本を売るために、テレビで紹介されました。とPOPを作って売っていることについて書かれている。
ブックびじねす危うしと思える記事だなと思う。
スーパーなどの小売店ではとっくの昔にやっていることなのに、なにをいまさらと思う。
それでも取り掛かるに遅くは無いので、売れるのであれば、取り掛かればいい。
食品なんて、ネットでテレビ番組情報まで流れる時代でっせー。
POPそのものの導入も遅かった。
「白い犬とワルツ」だったかの成功で、どこの本屋もPOPに力を入れるようになった。
どうやら、本屋とブックビジネスとイクオールで考えているところに、問題の根本原因があるようだ。
本屋とブックビジネスどちらの肩を持つということではなく考えると、本屋は、おすすめの本が何かを知りたい消費者のニーズに対応してこなかったし、ブックビジネスでは、一般的な売れ筋本以外はまったく消費者におすすめすることができなくなってきている。
この件だけの結論をいえば、どちらもまだ消費者ニーズに対応していないということだ。
本のソムリエという言葉も聞くようになったが、本のソムリエみたいな人がいる本屋があれば、面白いと思う。そこにかかる人件費は相当かかるけど。
だいたいその辺の本屋に行っても、本の予備知識がなさすぎる店員が多い。
ビッグカメラとかヤマダ電器とか、ほんとうのところはどうかしらないが、PCに詳しい人とか、携帯電話に詳しい人とかをアルバイトで雇っていて、彼らは精一杯自分の知識を仕事に活かして、購入者に応対している。
ソムリエとまではいかなくてもいいけど、ネットの世界ではリコメンドによって購買を決める頻度も少なくないのを知ると、リアルではなおさらやらないとならないのではと思ったりする。
あ、い、う、え、お、男性、女性順に並ぶのもいいけど、系統別に並べるとかもあっていい。
佐賀県内には大きな本屋が少ないので、どこも金太郎飴みたいな品揃えなのが残念でならない。
どの町にとっても本屋さんは、その町に住む人々の知的生活を担う大事な場所なのだ。